

1930年12月3日、パリ生まれ。アンリ・ラングロワのシネマテークに通い詰め、アンドレ・バザン主宰の「カイエ・デュ・シネマ」誌などで映画評や映画論を執筆する。短編を経て、『勝手にしやがれ』(59)で長編監督デビュー。ベルリン国際映画祭銀熊賞及びジャン・ヴィゴ賞を獲得する。以来、ヌーヴェル・ヴァーグの旗手として精力的に活動。
68年に「ジガ・ヴェルトフ集団」を結成して革命映画に邁進し、73年、アンヌ=マリー・ミエヴィルと共に、グルノーブルに「ソニマージュ」を設立。80〜90年代には、スイスに拠点を移し、映像と音の可能性を追求する。98年に『映画史』全8章を完成。2014年、初の3D作品『さらば、愛の言葉よ』でカンヌ国際映画祭審査員賞を受賞する。

・コンクリート作線(1954)*短編
・コケティッシュな女(1955)*短編
・男の名前はみんなパトリックっていうの(1957)*短編
・水の話(1958)
・シャルロットとジュール(1959)*短編
・勝手にしやがれ(1959)
・小さな兵隊(1960)
・女は女である(1961)
・怠惰の罪*『新7つの大罪』の一篇(1962)
・女と男のいる舗道(1962)
・新世界*『ロゴパグ』の一篇(1963)
・カラビニエ(1963)
・軽蔑(1963)
・立派な詐欺師*『世界詐欺物語』の一篇(1964)
・はなればなれに(1964)
・恋人のいる時間(1964)
・モンパルナスとルヴァロア*『パリところどころ』の一篇(1965)
・アルファヴィル(1965)
・気狂いピエロ(1965)
・男性・女性(1966)
・メイド・イン・USA(1967)
・彼女について私が知っている二、三の事柄(1967)
・未来展望*『愛すべき女・女たち』の一篇(1967)
・カメラ・アイ*『ベトナムから遠く離れて』の一篇(1967)
・中国女(1967)
・ウイークエンド(1967)
・たのしい知識(1969)
・ワン・プラス・ワン(1968)
・ブリティッシュ・サウンズ(1970)
・プラウダ(真実)(1970)
・東風(1969)
・イタリアにおける闘争(1971)
・万事快調(1972)
・うまくいってる?(1975)
・パート2(1975)
・ヒア&ゼア こことよそ(1976)
・勝手に逃げろ/人生(1979)
・パッション(1982)
・フレディ・ビアシュへの手紙(1982)*短編
・カルメンという名の女(1983)
・ゴダールのマリア(1985)
・ゴダールの探偵(1985)
・映画というささやかな商売の栄華と衰退(1986)
・右側に気をつけろ(1987)
・ゴダールのリア王(1987)
・アルミード*『アリア』の一篇(1987)
・ゴダールの映画史 第1章 すべての歴史(1989)
・ゴダールの映画史 第2章 単独の歴史(1989)
・ヌーヴェルヴァーグ(1990)
・新ドイツ零年(1991)
・ゴダールの決別(1993)
・JLG/自画像(1995)
・フォーエヴァー・モーツァルト(1996)
・映画史(1998)
・愛の世紀(2001)
・時間の闇の中で*『10ミニッツ・オールダー イデアの森』の一篇(2002)
・アワーミュージック(2004)
・映画史特別編 選ばれた瞬間(2005)
・ゴダール・ソシアリズム(2010)
・さらば、愛の言葉よ(2014)
60年代ゴダールを語るうえで、当時のミューズだったアンナ・カリーナの存在を無視することはできません。『女と男のいる舗道』など彼女の存在なしでは想像もできない作品は言わずもがな、彼女の出ない『勝手にしやがれ』も当初のヒロインにはやっぱりアンナが想定されていたそうですし、『軽蔑』や『恋人のいる時間』などで描かれた移り気な女性の不可解さは、アンナの浮気に悩んでいた当時のゴダールの実感そのものでした。そんなアンナで始まりアンナで終わったゴダールの甘酸っぱい青春期(!?)を象徴するのが、今回上映する2作品です。

女は女である
Une femme est une femme
 (1961年 フランス/イタリア 84分
(1961年 フランス/イタリア 84分  シネスコ/MONO)
シネスコ/MONO)
2017年6月3日-6月9日上映
■監督・脚本 ジャン=リュック・ゴダール
■原案 ジュヌヴィエーヴ・クリュニ
■撮影 ラウル・クタール
■編集 アニュス・ギュモ
■音楽 ミシェル・ルグラン
■出演 アンナ・カリーナ/ジャン=クロード・ブリアリ/ジャン=ポール・ベルモンド/マリー・デュボワ/ジャンヌ・モロー
■1961年ベルリン国際映画祭銀熊賞・女優賞受賞
© 1961 STUDIOCANAL IMAGE - EURO INTERNATIONAL FILMS,S.p.A.
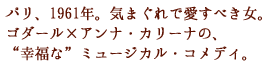
 パリの下町の小さな本屋の店で働くエミールは、ストリップ・ガールのアンジェラと同棲している。そのアンジェラが急に赤ん坊が欲しいと言い出した。そのことで、二人は意見が合わず、喧嘩がたえない。男のエミールにしてみれば、子供はいらないし、正式な結婚なんかしない方が都合がいいからだ。だが、どうしても子供を生むと意地になったアンジェラは他の男に頼んでつくってもらうと、おだやかならぬ宣告をして…。
パリの下町の小さな本屋の店で働くエミールは、ストリップ・ガールのアンジェラと同棲している。そのアンジェラが急に赤ん坊が欲しいと言い出した。そのことで、二人は意見が合わず、喧嘩がたえない。男のエミールにしてみれば、子供はいらないし、正式な結婚なんかしない方が都合がいいからだ。だが、どうしても子供を生むと意地になったアンジェラは他の男に頼んでつくってもらうと、おだやかならぬ宣告をして…。
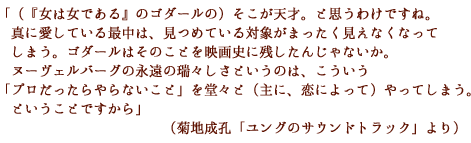
 本作はゴダール&アンナという、映画史上に残る最高のカップルの誕生を高らかに歌い上げた記念碑的傑作であり、つき合い始めて間もないゴダールとアンナの多幸感が爆発した作品です。ゴダールにとって初のカラー映画、そしてシネスコでミュージカルだからはしゃいでいたというのもあるのでしょうが、その創作衝動の根本にアンナがいたことは疑いようがありません。菊地成孔氏の言う通り、自由奔放に歌い踊るキュートなアンナはもちろん、一般的には「斬新な実験精神」と評されるカラフルな色彩の洪水やミシェル・ルグランの音楽の無茶苦茶な使い方ですら、実際にはアンナに撮影現場でも編集室でもデレデレしていたゴダールの「恋の盲目」症状のなせる業だったと考えるほうがしっくりきます。その浮つき具合は傍目にはちょっと気恥ずかしいくらいなのですが、だからこそこの時にしか撮れない瑞々しさに溢れた特別なフィルムになったのだと思います。
本作はゴダール&アンナという、映画史上に残る最高のカップルの誕生を高らかに歌い上げた記念碑的傑作であり、つき合い始めて間もないゴダールとアンナの多幸感が爆発した作品です。ゴダールにとって初のカラー映画、そしてシネスコでミュージカルだからはしゃいでいたというのもあるのでしょうが、その創作衝動の根本にアンナがいたことは疑いようがありません。菊地成孔氏の言う通り、自由奔放に歌い踊るキュートなアンナはもちろん、一般的には「斬新な実験精神」と評されるカラフルな色彩の洪水やミシェル・ルグランの音楽の無茶苦茶な使い方ですら、実際にはアンナに撮影現場でも編集室でもデレデレしていたゴダールの「恋の盲目」症状のなせる業だったと考えるほうがしっくりきます。その浮つき具合は傍目にはちょっと気恥ずかしいくらいなのですが、だからこそこの時にしか撮れない瑞々しさに溢れた特別なフィルムになったのだと思います。
トリュフォーの『ピアニストを撃て』のヒロインのマリー・デュボアが出てきたり、「早く家に帰ってテレビで『勝手にしやがれ』を観たいんだ」なんて台詞をベルモンドが口にしたりといった愉快な楽屋落ちも、当時のヌーヴェルバーグの牧歌的な雰囲気を伝えてくれます。

はなればなれに
Bande à part
 (1964年 フランス 96分
(1964年 フランス 96分  SD)
SD)
2017年6月3日-6月9日上映
■監督・脚本 ジャン=リュック・ゴダール
■原作 ドロレス・ヒチェンズ『愚か者たちの黄金』
■撮影 ラウル・クタール
■編集 アニュス・ギュモ
■音楽 ミシェル・ルグラン
■出演 アンナ・カリーナ/クロード・ブラッスール/サミ・フレ/ルイザ・コルペイン
© 1964 Gaumont - Orsay Films
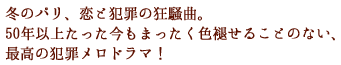
 ある日偶然出会った小悪党の男ふたりと、無垢な女。パリ郊外にある女の叔母の家から大金を盗む計画を立てる3人だが、予期せぬハプニングから計画は殺人事件へと発展する。強欲なアルチュールに惹かれるちょっと奥手なオディールと、彼女をひたむきに愛する優しいフランツ。アマチュア強盗団3人のバランスは、逃亡生活のなかで徐々に崩壊していく…。
ある日偶然出会った小悪党の男ふたりと、無垢な女。パリ郊外にある女の叔母の家から大金を盗む計画を立てる3人だが、予期せぬハプニングから計画は殺人事件へと発展する。強欲なアルチュールに惹かれるちょっと奥手なオディールと、彼女をひたむきに愛する優しいフランツ。アマチュア強盗団3人のバランスは、逃亡生活のなかで徐々に崩壊していく…。
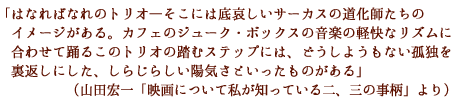
 本作もまた遊び心に満ちたギャグに溢れた軽快な作品です。主人公たちがルーブル美術館を駆け抜けたり、印象的なダンスを踊ったり、一分間黙ったりする愉快な名シーンが満載なのですが、カラフルだった『女は女である』から一転したモノクロ映像は、主人公たちの冒険をどこかクールに見つめている様な雰囲気を漂わせています。そして服装や仕草が最高にキュートなアンナも、その表情は心なしか寂しげに見えます。何故でしょう?
本作もまた遊び心に満ちたギャグに溢れた軽快な作品です。主人公たちがルーブル美術館を駆け抜けたり、印象的なダンスを踊ったり、一分間黙ったりする愉快な名シーンが満載なのですが、カラフルだった『女は女である』から一転したモノクロ映像は、主人公たちの冒険をどこかクールに見つめている様な雰囲気を漂わせています。そして服装や仕草が最高にキュートなアンナも、その表情は心なしか寂しげに見えます。何故でしょう?
 推測ですが、この時期のアンナとゴダールのブルーな気分が作品に影を落としてしまったのではないでしょうか。なにしろ、本作は二人が共同で設立したプロダクション「アヌーシュカ・フィルム」の第一回作品にして、彼らの離婚がほぼ決定した時期に撮られた作品なのですから(ちなみに「アヌーシュカ」はアンナの愛称。そのネーミングからだけでも、ゴダールのいじらしいまでにピュアな心情が伝わってきます…)。実生活が作品に影響するのは、二人の望むべきところではなかったのかもしれません。
推測ですが、この時期のアンナとゴダールのブルーな気分が作品に影を落としてしまったのではないでしょうか。なにしろ、本作は二人が共同で設立したプロダクション「アヌーシュカ・フィルム」の第一回作品にして、彼らの離婚がほぼ決定した時期に撮られた作品なのですから(ちなみに「アヌーシュカ」はアンナの愛称。そのネーミングからだけでも、ゴダールのいじらしいまでにピュアな心情が伝わってきます…)。実生活が作品に影響するのは、二人の望むべきところではなかったのかもしれません。
でも、だからこそ!本作には底抜けに陽気な『女は女である』とは対照的に、切ない終わりの予感と表裏一体となった青春の儚さがまるでドキュメンタリーのように記録されて(しまって)おり、そこに特別な魅力があると思うのです。アンナも含めてそこそこいい大人たちがまるで子どもみたいにはしゃいでいるのも、「青春の末期症状」という微笑ましくも切ない感覚を強めるチャームポイントです!
この時点で互いにアンビバレントな想いを抱きながらコラボレーションするしかなかった二人は、その後どうなってしまったのでしょう? 今回の特集でこのカップルに出会ったという幸運な方や未見の方は、『アルファヴィル』『気狂いピエロ』『未来展望』と連なっていく彼らの哀しくも感動的な軌跡も是非追いかけて観て下さい!
(ルー)
