
60年代のゴダール映画は、どれもどこか青春映画のような印象がある。
それは描かれる題材が何かという次元を超え、彼の自伝的要素が青臭いといっていいくらい赤裸々に作品に刻印されている故だと思う。公私共にパートナーだったアンナ・カリーナへのアンビバレントな想いを原動力に映画を作っていた、この頃の作品のシンプルで繊細な感触は、60年代末から70年代にかけてのジガ・ヴェルトフ集団での作品や、商業映画に復帰した79年『勝手に逃げろ/人生』以降の作品からも失われてしまったものだ(もちろん、どの時代のゴダールもそれぞれに魅力的で愛着があるけれど)。
今回上映するのは、65年パリの若者たちを取り巻く空気をドキュメンタリーのように真空パックした『男性・女性』と、アンナ・カリーナとのコラボレーションという意味では最高傑作の『女と男のいる舗道』だ。
男性・女性
MASCULIN FEMININ
(1966年 フランス/スウェーデン 105分  SD/MONO)
SD/MONO)  2016年4月9日から4月15日まで上映
■監督・脚本 ジャン=リュック・ゴダール
2016年4月9日から4月15日まで上映
■監督・脚本 ジャン=リュック・ゴダール
■原作 ギ・ド・モーパッサン
■製作 アナトール・ドーマン
■撮影 ウィリー・クラント
■編集 アニエス・ギュモ
■音楽 フランシス・レイ
■出演 ジャン=ピエール・レオー/シャンタル・ゴヤ/マルレーヌ・ジョベール/カトリーヌ=イザベル・デュポール/フランソワーズ・アルディ
■1966年ベルリン国際映画祭男優賞受賞
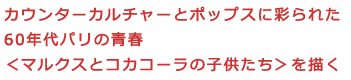
 軍隊帰りの現代のヴェルテル的青年ポール、その恋人のイェー・イェー歌手のマドレーヌ、ポールの友人で、ベトナムに平和をと叫ぶ、組合連合の活動家ロベール、マドレーヌの女友達でポールの恋を妨げるカトリーヌ、ロベールが愛するおとなしい娘エリザベート。60年代後半フランスの若者たちの15の明白な事実。
軍隊帰りの現代のヴェルテル的青年ポール、その恋人のイェー・イェー歌手のマドレーヌ、ポールの友人で、ベトナムに平和をと叫ぶ、組合連合の活動家ロベール、マドレーヌの女友達でポールの恋を妨げるカトリーヌ、ロベールが愛するおとなしい娘エリザベート。60年代後半フランスの若者たちの15の明白な事実。
『男性・女性』は、ベトナム戦争やビートルズ旋風など、撮影された65年当時のヒア&ゼアで起こっていた現象を取り込んで、パリの若者群像を半ばドキュメンタリーのように描いた作品だ(台詞やキャラクターは俳優たちへのインタビューから作り上げていったという)。「アンナ・カリーナ時代」の集大成ともいうべき前作『気狂いピエロ』のロマン主義的な色彩は影を潜め、政治と恋に明け暮れつつ、消費社会に取り込まれていく若者たちの姿が、ジャン=ピエール・レオー演じる主人公の目を通してドライに描かれていく。
 とはいえ、本作の最大の魅力は、レオーという俳優のドキュメントにもなっているところだろう。歌手の恋人シャンタル・ゴヤ相手に空回りし続ける、レオーの一挙手一投足は愛おしくも、何ともイタい。「世界の中心は愛だ」と恥ずかしげもなく言うレオーに、「世界の中心は自分よ」としたたかに返すゴヤは最高にチャーミングだが、夢見がちなレオーとリアリストの彼女との温度差は際立ってしまうばかり(「男性」と「女性」の間の・には「深くて暗い河がある」のだ・・・)。ゴダール特有のロマンティシズムをレオーに託し、痛切な悲喜劇として完結させた本作を境に、映画作家ゴダールの青春期も徐々に終わりを告げていく・・・。
とはいえ、本作の最大の魅力は、レオーという俳優のドキュメントにもなっているところだろう。歌手の恋人シャンタル・ゴヤ相手に空回りし続ける、レオーの一挙手一投足は愛おしくも、何ともイタい。「世界の中心は愛だ」と恥ずかしげもなく言うレオーに、「世界の中心は自分よ」としたたかに返すゴヤは最高にチャーミングだが、夢見がちなレオーとリアリストの彼女との温度差は際立ってしまうばかり(「男性」と「女性」の間の・には「深くて暗い河がある」のだ・・・)。ゴダール特有のロマンティシズムをレオーに託し、痛切な悲喜劇として完結させた本作を境に、映画作家ゴダールの青春期も徐々に終わりを告げていく・・・。
女と男のいる舗道
VIVRE SA VIE
(1962年 フランス 85分  SD)
SD)
 2016年4月9日から4月15日まで上映
■監督・脚本 ジャン=リュック・ゴダール
2016年4月9日から4月15日まで上映
■監督・脚本 ジャン=リュック・ゴダール
■製作 ピエール・ブロンベルジェ
■撮影 ラウル・クタール
■編集 アニエス・ギュモ
■音楽 ミシェル・ルグラン
■出演 アンナ・カリーナ/サディ・レボ/アンドレ・S・ラバルト/ギレーヌ・シュランベルジェ/ペテ・カソヴィッツ
■1962年ヴェネチア国際映画祭審査員特別賞受賞
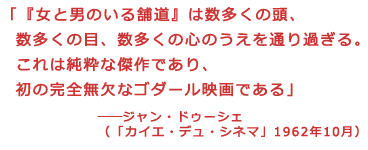
 パリのあるカフェ。ナナは別れた夫と疲れきった人生を語りあっている。現在の報告をしあって別れる。夢も希望もない。ナナはそんなある日、舗道で男に誘われ、体を与えてその代償を得た。そして彼女は古い女友達イヴェットに会う。彼女は街の女達に客を紹介してはピンはねする商売の女だ。ナナは完全な売春婦になった――。
パリのあるカフェ。ナナは別れた夫と疲れきった人生を語りあっている。現在の報告をしあって別れる。夢も希望もない。ナナはそんなある日、舗道で男に誘われ、体を与えてその代償を得た。そして彼女は古い女友達イヴェットに会う。彼女は街の女達に客を紹介してはピンはねする商売の女だ。ナナは完全な売春婦になった――。
 『女と男のいる舗道』は、ゴダールの長編4作目(原題は「自分らしく生きる」)。アンナ・カリーナとの新婚直後に撮影された(多分にのろ気の入った)幸福感でいっぱいだった前作『女は女である』から一転、モノクロで描かれるひとりの娼婦の悲劇が、極めてストイックな映像と音響で綴られていく。ゴダール自身「人間の存在を顔に集約した肖像画のような映画を撮りたかった」というように、本作の全てはアンナ・カリーナという女優/女性の美しさを、そしてその内面の魂を写し取るためにある。彼女がカール・ドライヤー監督の『裁かるゝジャンヌ』を劇場で見ながら涙を流す場面の素晴らしさは永遠だ。
『女と男のいる舗道』は、ゴダールの長編4作目(原題は「自分らしく生きる」)。アンナ・カリーナとの新婚直後に撮影された(多分にのろ気の入った)幸福感でいっぱいだった前作『女は女である』から一転、モノクロで描かれるひとりの娼婦の悲劇が、極めてストイックな映像と音響で綴られていく。ゴダール自身「人間の存在を顔に集約した肖像画のような映画を撮りたかった」というように、本作の全てはアンナ・カリーナという女優/女性の美しさを、そしてその内面の魂を写し取るためにある。彼女がカール・ドライヤー監督の『裁かるゝジャンヌ』を劇場で見ながら涙を流す場面の素晴らしさは永遠だ。
ゴダールは愛する女性の美を通して、この世界で「自分らしく生きる」ことの難しさと哀しさを突き詰め、問いかけていく。ペシミスティックな世界観の根底に流れる、その人間らしい感情のあたたかさに胸をうたれる作品。ゴダールを喰わず嫌いな人にこそ観てほしい!
(ルー)

