
![]()
1906年イタリア・ミラノ生まれ。
イタリア有数の名門貴族の家系に生まれ、芸術的環境で育つ。30年代初頭にパリで暮らしはじめ、ジャン・コクトー、ココ・シャネルらと出会い、シャネルからジャン・ルノワールを紹介される。
ルノワールの助監督を務め、42年には自ら脚本を書いた『郵便配達は二度ベルを鳴らす』で長編監督デビュー。ネオレアリズモの主翼を担う存在として『揺れる大地』('48)や『若者のすべて』('60)等の名作を発表する。
カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した『山猫』('63)以降は、自身の出自でもある貴族の没落や芸術家を描いた重厚で耽美的な作風に傾倒していく。
『地獄に落ちた勇者ども』('69)、『ベニスに死す』('71)、『ルートヴィヒ』('73)の"ドイツ三部作"を完成させた後、発作で倒れ半身不随となる。だが車椅子生活を強いられながらも、舞台やオペラの演出を続けた。
76年3月17日、ローマの自宅で死去。『イノセント』('76)が遺作となった。
![]()
・郵便配達は二度ベルを鳴らす('42)監督/脚本
・トスカ('44)協力監督
・揺れる大地('48)監督/脚本/原案
・ベリッシマ('51)監督/脚本
・われら女性('53)監督(オムニバスのうち一編)
・夏の嵐('54)監督/脚本
・白夜('57)監督/脚本
・若者のすべて('60)監督/脚本/原案
・ボッカチオ'70('62)監督/脚本(オムニバスのうち一編)
・山猫('63)監督/脚本
・熊座の淡き星影('65)監督/脚本
・華やかな魔女たち('66)監督(オムニバスのうち一編)
・異邦人('68)監督
・地獄に堕ちた勇者ども('69)監督/脚本
・ベニスに死す('71)監督/脚本/製作
・ルートヴィヒ('72)監督/脚本
・家族の肖像('74)監督
・イノセント('75)監督
イタリア映画は、例えばフランス映画の華やかさや、ポップさ、チャーミングさに比べると重厚で、社会的要素が濃く、ハードルが高そうに感じます。ですが、観始めてみると斬新で刺激的な映像、歴史的、宗教的な要素が魅力となっている物語、そして何よりもイタリアの風景や建物の美しさは、他のどの国の映画よりも充足感を与えてくれる作品ばかりです。
例えば、まだイタリア映画の名作を観たことがないという方がいたなら、どの監督の作品をすすめるでしょうか。ロッセリーニでしょうか。フェリーニでしょうか。ベルトルッチでしょうか…。悩みますが、私なら、ルキーノ・ヴィスコンティ監督を一番にお勧めします。
今週の上映作品『若者のすべて』と『家族の肖像』は、両作品とも“家族”という身近で、共感しやすい存在をテーマにした作品です。ヴィスコンティの描く人物たちは、どのキャラクターも個性的で人間味に溢れ、魅力的です。時代背景や、文学的な知識が何もなくても、登場人物の関係性に夢中になり、感情移入しているうちにそれぞれの作品の魅力が見えてきます。
『若者のすべて』では、イタリアにおける南北の経済格差、生活の豊かさを求めて北上する移民、その苦難を描いたヴィスコンティですが、彼はこの作品についてこう語っています。
「魂の状態や、心理、人間の葛藤を描くことこそ、私にとってそれが社会的な問題に近づく方法なのだ。この物語の場合にも、兄弟同士の関係とか兄弟と母親との間柄などという事が、この一家が南部から移住してきたという社会的事実に劣らず、私の興味を惹くのだ。私の場合いつもこうして心理的な探索、人間ドラマの構築ということを通して、社会的、政治的結論に到達しているのである。」(『世界の映画作家4』キネマ旬報社より抜粋)
この言葉は『若者のすべて』に限らず、全ヴィスコンティ作品に通じるものだと思うのです。
そして『家族の肖像』で描かれている人間模様が、私はヴィスコンティ作品の中でも特に好きです。遠慮なく生活に介入してくる若者と、世間と関わることを断ち孤独を選んだ老人、衰退していくものと変化し続ける時代、血のつながりのない者たちが家族の形を模索し衝突しあう姿。孤独と苦悩を抱えながらも、理解し合いたいと願っている様は、どこか現代の家族の形との繋がりも感じてしまうのです。
イタリアの社会を綿密に描くことに重きを置いていた彼がネオレアリズモ作品群の集大成として生み出した『若者のすべて』。そして、自身の公家の血筋を振り返るような退廃的で、豪華で、耽美な後期の作品群の集大成ともいえる『家族の肖像』。今週はヴィスコンティの作風を満喫するには、最高の二本立てです。いつ観ても色あせない傑作を、どうぞお楽しみください。
若者のすべて デジタル完全修復版
ROCCO E I SUOI FRATELLI
 (1960年 イタリア/フランス 179分
(1960年 イタリア/フランス 179分  ビスタ)
ビスタ)
2017年8月5日-8月11日上映
■監督・原案・脚本 ルキーノ・ヴィスコンティ
■原案 ヴァスコ・プラトリーニ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ
■脚本 スーゾ・チェッキ・ダミーコ/パスクァーレ・フェスタ・カンパニーレ/マッシモ・フランチョーザ/エンリコ・メディオーリ
■撮影 ジュゼッペ・ロトゥンノ
■音楽 ニーノ・ロータ
■出演 アラン・ドロン/レナート・サルヴァトーリ/アニー・ジラルド/カティーナ・パクシー/ロジェ・アナン/パオロ・ストッパ/シュジ・ドレール/クラウディア・カルディナーレ/スピロス・フォカス
■ヴェネツィア国際映画祭審査員特別賞受賞
© 1960 TF1 Droits Audiovisuels - Titanus
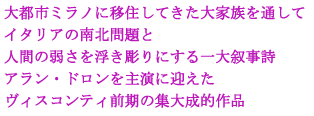
 父親を失った一家は貧しい南部の農村ルカーニアから、北部の大都市ミラノに長男ヴィンチェンツォを頼りに越してきた。ヴィンチェンツォはプロ・ボクサーを志し、次男シモーネと三男ロッコもクラブに出入りするようになった。シモーネは貧困と不遇の青春のうっぷんをグローブに賭け、悪の世界に足を踏み入れる。シモーネはナディアという女に溺れていた。だが彼女は気立てが優しく真面目なロッコを好きになってしまう――。
父親を失った一家は貧しい南部の農村ルカーニアから、北部の大都市ミラノに長男ヴィンチェンツォを頼りに越してきた。ヴィンチェンツォはプロ・ボクサーを志し、次男シモーネと三男ロッコもクラブに出入りするようになった。シモーネは貧困と不遇の青春のうっぷんをグローブに賭け、悪の世界に足を踏み入れる。シモーネはナディアという女に溺れていた。だが彼女は気立てが優しく真面目なロッコを好きになってしまう――。
 前作『白夜』でリアリズムからの逸脱を批判されたヴィスコンティが、当時のイタリア社会、とくに北部先進工業地帯で重要問題となっていた、南部からの移住民との社会的文化的摩擦を真正面からとりあげた一種の社会告発映画であり、リアリズムの巨匠としての名声をふたたび確立した。
前作『白夜』でリアリズムからの逸脱を批判されたヴィスコンティが、当時のイタリア社会、とくに北部先進工業地帯で重要問題となっていた、南部からの移住民との社会的文化的摩擦を真正面からとりあげた一種の社会告発映画であり、リアリズムの巨匠としての名声をふたたび確立した。
ヴィスコンティ個人としてもこの作品に対する愛情はひとしおであり、もっとも好きな作品のひとつにあげている。彼はその生涯で故郷の地ミラノを舞台にしてつくった作品は『ボッカチオ'70』の挿話をのぞいてはこの作品一本であり、また当時のほかの誰よりもはやく国内移民問題をとりあげたという自負心からでもあろう。お気に入りのレナート・サルヴァトーリ、アラン・ドロンと初の仕事でもある。
※「ヴィスコンティ集成」(フィルムアート社)より解説引用
家族の肖像 デジタル完全修復版
Gruppo di famiglia in un interno
 (1974年 イタリア/フランス 121分
(1974年 イタリア/フランス 121分  シネスコ)
シネスコ)
2017年8月5日-8月11日上映
■監督・脚本 ルキーノ・ヴィスコンティ
■製作 ジョヴァンニ・ベルトルッチ
■原案・脚本 エンリコ・メディオーリ
■脚本 スーゾ・チェッキ・ダミーコ
■撮影 パスクァリーノ・デ・サンティス
■衣装 ヴェーラ・マルツォ/ピエロ・トージ
■美術 マリオ・ガルブリア
■編集 ルッジェーロ・マストロヤンニ
■音楽 フランコ・マンニーノ
■出演 バート・ランカスター/シルヴァーナ・マンガーノ/ヘルムート・バーガー/クラウディア・マルサーニ/ステファーノ・パトリッツィ/ロモーロ・ヴァッリ/ドミニク・サンダ/クラウディア・カルディナーレ
©Minerva Pictures
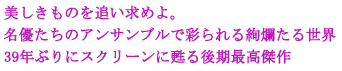
 18世紀イギリスで流行した<家族の肖像>と呼ばれる家族の団欒画のコレクションに囲まれて、ローマの豪邸に一人暮らす老教授。失われゆくものたちに埋もれ、孤独に生きていた彼の生活が、ある家族の闖入によって掻き乱されていく…。
18世紀イギリスで流行した<家族の肖像>と呼ばれる家族の団欒画のコレクションに囲まれて、ローマの豪邸に一人暮らす老教授。失われゆくものたちに埋もれ、孤独に生きていた彼の生活が、ある家族の闖入によって掻き乱されていく…。
1972年、前作『ルートヴィヒ』の完成間際に病いに倒れ、ライフワークとしていた諸作品の映画化を断念せざるを得なくなった彼が、共同脚本のエンリコ・メディオーリに口にした「単純で簡潔な、一室内で終始する物語。登場人物は二人」というアイデアから生まれたのが本作。美術のマリオ・ガルブリア指揮の下、制作されたスタジオのセット内ですべて撮影、車椅子を操りながら気迫と執念で撮り上げた。
 長年に渡り協力関係にあった名優たちが奏でる、室内楽にも似た名演のアンサンブル。『山猫』で、最もヴィスコンティ自身に近い、と言われた滅びゆく貴族を見事に体現したバート・ランカスターが、ここでもまた、ヴィスコンティ自身の精神的な肖像とも言うべき教授役を味わい深く演じている。
長年に渡り協力関係にあった名優たちが奏でる、室内楽にも似た名演のアンサンブル。『山猫』で、最もヴィスコンティ自身に近い、と言われた滅びゆく貴族を見事に体現したバート・ランカスターが、ここでもまた、ヴィスコンティ自身の精神的な肖像とも言うべき教授役を味わい深く演じている。
始めは反目しながらも次第に強く惹かれていく、粗野な面と知性を同時に持つ美青年コンラッドには、公私にわたり監督から寵愛を受けたヘルムート・バーガー。気品あふれる存在感を過去作に焼き付けてきたシルヴァーナ・マンガーノが、貴族ならではの傍若無人さをまき散らす伯爵夫人に扮し、強烈な存在感を示している。回想場面で登場する、クラウディア・カルディナーレ、ドミニク・サンダの美しさも特筆すべきた。
