
![]()
監督・脚本■ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ
兄のジャン=ピエールは1951年4月21日、弟のリュックは1954年3月10日にベルギーのリエージュ近郊で生まれる。リエージュは工業地帯であり、労働闘争のメッカでもあった。
ジャン=ピエールは舞台演出家を目指してブリュッセルへ移り、そこで演劇界、映画界で活躍していたアルマン・ガッティと出会う。その後、ふたりはガッティの下で暮らすようになり、芸術や政治の面で多大な影響を彼から受け、映画製作を手伝う。原子力発電所で働いて得た資金で機材を買い、労働者階級の団地に住み込み、土地整備や都市計画の問題を描くドキュメンタリー作品を74年から制作しはじめる。同時に75年にはドキュメンタリー制作会社「Derives」を設立する。
78年に初のドキュメンタリー映画“Le chant du Rossignol”を監督し、その後もレジスタンス活動、ゼネスト、ポーランド移民といった様々な題材のドキュメンタリー映画を撮りつづける。86年、ルネ・カリスキーの戯曲を脚色した初の長編劇映画「ファルシュ」を監督、ベルリン・カンヌなどの映画祭に出品される。92年に第2作「あなたを想う」を撮るが、会社側の圧力による妥協の連続で、ふたりには全く満足できない作品となってしまう。
前作での失敗に懲りた彼らは、第3作『イゴールの約束』では決して妥協することのない環境で作品を製作、カンヌ国際映画祭 国際芸術映画評論連盟賞をはじめ、多くの賞を獲得するなど、世界中で絶賛された。続く第4作『ロゼッタ』ではカンヌ国際映画祭でパルムドール大賞を受賞、本国ベルギーでの成功はもとより、フランスでも100館あまりで公開され大きな反響を呼んだ。さらに2002年、第5作『息子のまなざし』でもカンヌ国際映画祭・主演男優賞とエキュメニック賞特別賞をW受賞した。2005年カンヌ国際映画祭では、『ある子供』が史上5組目となる2度目のパルムドール大賞に輝く。 第7作『ロルナの祈り』では、2008年の同映画祭において脚本賞を受賞。
そして最新作『少年と自転車』は2011年のカンヌ国際映画祭グランプリを受賞。史上初の5作品連続主要賞受賞の快挙を成し遂げた。近年では共同プロデューサーとして若手監督のサポートも積極的に行っている。名実共にいまや他の追随を許さない、21世紀を代表する世界の名匠である。
![]()
・イゴールの約束(1996)監督/脚本/製作
・ロゼッタ(1999)監督
・息子のまなざし(2002)監督/脚本/製作
・陽のあたる場所から(2003)製作
・ある子供(2005)監督/脚本/製作
・それぞれのシネマ 〜カンヌ国際映画祭60回記念製作映画〜(2007)監督
・ロルナの祈り(2008)監督/脚本/製作
・少年と自転車(2011)監督/脚本/製作
*日本公開作品のみ
ダルデンヌ兄弟の作る映画は、余計なものが削ぎ落とされ、洗練されている。
人、場所、物、そして人。
これらを動かしてフィルムに収める。
このシンプルさで観る者の感情を揺さぶるのが、彼らの映画の醍醐味であろう。
兄のジャン=ピエールと弟のリュックの二人は、伝える為に必要なモノを話し合うのか、
はたまた、阿吽の呼吸で分かり合っているのか僕にはわからない。
ただ、鈍感で頓珍漢な僕にでも、映画を観れば登場人物たちの気持ちがよく分かる。
多過ぎず、少な過ぎず、伝える事で我々から素直な感情が溢れ出してくるのだ。
モノ、情報、人で溢れかえる世の中で、
彼らの映画を観るとホッとしてしまうのは僕だけではないはずだ。
しかし、ダルデンヌ兄弟の映画が見せてくれるのは、
人間の営みの厳しさだけれども。
今週は最新作『少年と自転車』と、劇映画三作目であり、
日本での公開一作目の『イゴールの約束』の二本立て。
ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督特集です。
イゴールの約束
LA PROMESSE
 (1996年 ベルギー/フランス/ルクセンブルク/チュニジア 93分 ビスタ/ドルビーA)
(1996年 ベルギー/フランス/ルクセンブルク/チュニジア 93分 ビスタ/ドルビーA)
2012年9月22日から9月28日まで上映
■監督・製作・脚本 ジャン=ピエール・ダルデンヌ/リュック・ダルデンヌ
■脚本 レオン・ミショー/アルフォンソ・バドロ
■撮影 アラン・マルコアン
■音楽 ジャン=マリー・ビリー/デニ・M・プンガ
■出演 ジェレミー・レニエ/オリヴィエ・グルメ/アシタ・ウエドラオゴ/フレデリック・ボドソン/ラスマネ・ウエドラオゴ
■カンヌ国際映画祭国際芸術映画評論連盟賞受賞/全米批評家協会賞外国語映画賞/LA批評家協会賞外国映画賞受賞 ほか多数
![]()
イゴールはベルギーの自動車修理工場で働く、15歳の少年。罪の意識もなく、客の車から財布を盗んだりしている。その一方で、違法外国人労働者の売人である、父・ロジェの仕事も手伝わなければならない。
ある日、労働監査官が査察に来て、逃げようとした外国人労働者・アミドゥが足場から落ちてしまう。出血がひどいアミドゥは動くこともできず、イゴールに妻・アシタと子供のことを頼み、イゴールは面倒をみると約束する。ロジェは警察沙汰になることを恐れてアミドゥを病院へ連れて行かず、傷の手当ができなかったアミドゥはついに死んでしまう。セメントで死体を埋めたロジェとイゴールは、妻・アシタにも嘘をつく。しかし、イゴールにとって、アミドゥとの「約束」を果たすべく、アシタに話さねばならない時が近づいていた…。
![]()
ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌは、ベルギー生まれの兄弟。1974年からビデオによるドキュメンタリーの制作・演出を始め、本作は長編2作目にあたる。「僕たちは、二つの体に分けられた一人の人間」と自ら語るように、今日まで実に30年以上にわたって二人で共同演出を行ってきた。
1996年カンヌ国際映画祭監督週間。『イゴールの約束』は、上映終了と共に満場の拍手に包まれ、国際芸術映画評論連盟賞を受賞した。ニューヨーク、モントリオール、ロンドン、トロント、メルボルンなど世界中の映画祭で絶賛され、“ケン・ローチのように登場人物からセンチメンタリズムを排する”“イタリアン・ネモリアリズモの再来”と高く評価された。アルノ―・デプレシャン(『クリスマス・ストーリー』)は、「96年に観た映画の中で、『奇跡の海』と『イゴールの約束』がベストだ」と語る。名実共にいまや他の追随を許さない、21世紀を代表する世界の名匠となったダルデンヌ兄弟は、この作品で世界の第一線に躍り出たのである。

少年と自転車
LE GAMIN AU VELO
 (2011年 ベルギー/フランス/イタリア 87分 ビスタ/SRD)
(2011年 ベルギー/フランス/イタリア 87分 ビスタ/SRD)
2012年9月22日から9月28日まで上映
■監督・製作・脚本 ジャン=ピエール・ダルデンヌ/リュック・ダルデンヌ
■製作 ドニ・フロイド
■撮影 アラン・マルコアン
■美術 イゴール・ガブリエル
■編集 マリ=エレーヌ・ドゾ
■出演 セシル・ドゥ・フランス/トマ・ドレ/ジェレミー・レニエ/ファブリツィオ・ロンジョーネ/エゴン・ディ・マテオ/オリヴィエ・グルメ
■カンヌ国際映画祭審査員特別グランプリ受賞・パルム・ドールノミネート/ゴールデン・グローブ外国語映画賞ノミネート/ヨーロッパ映画賞脚本賞受賞・作品賞・監督賞・女優賞ノミネート/インディペンデント・スピリット賞外国映画賞ノミネート/セザール賞外国映画賞ノミネート
![]()
 もうすぐ12歳になる少年シリル。彼の願いは、自分をホーム(児童養護施設)へ預けた父親を見つけ出し、再び一緒に暮らすこと。かつて父と暮らした団地へ向かったシリルは、追いかけてきた先生から走って逃げ、知らない女性にしがみついた。「パパが買ってくれた自転車があるはずだ!」しかし、部屋をあけてもそこはもぬけの殻だった。後日、ある女性がシリルを訪ねてくる。先日の騒動の際にシリルがしがみついた女性、サマンサだった。
もうすぐ12歳になる少年シリル。彼の願いは、自分をホーム(児童養護施設)へ預けた父親を見つけ出し、再び一緒に暮らすこと。かつて父と暮らした団地へ向かったシリルは、追いかけてきた先生から走って逃げ、知らない女性にしがみついた。「パパが買ってくれた自転車があるはずだ!」しかし、部屋をあけてもそこはもぬけの殻だった。後日、ある女性がシリルを訪ねてくる。先日の騒動の際にシリルがしがみついた女性、サマンサだった。
美容院を営むサマンサに週末だけ里親になることを頼みこみ、彼女と週末を過ごしながら、父親の住所を探し出したシリル。再会を果たし、つかの間の父との時間を味わうシリルだったが、父親の言葉は残酷だった。「もう会いに来るな」「電話くれるよね」「わからない…しない」そして、扉はバタンと閉められた。
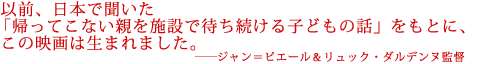
 カンヌ国際映画祭で、2度のパルムドール大賞(『ロゼッタ』『ある子供』)、主演男優賞(『息子のまなざし』)、脚本賞(『ロルナの祈り』)、そして本作でグランプリを獲得し、5作品連続でカンヌの主要賞受賞という史上初の快挙を成し遂げたダルデンヌ兄弟。
カンヌ国際映画祭で、2度のパルムドール大賞(『ロゼッタ』『ある子供』)、主演男優賞(『息子のまなざし』)、脚本賞(『ロルナの祈り』)、そして本作でグランプリを獲得し、5作品連続でカンヌの主要賞受賞という史上初の快挙を成し遂げたダルデンヌ兄弟。
親に見捨てられた少年シリルが、初めて信頼できる大人であるサマンサに出会うことで、心をひらき、人を信じ、善悪を学び、成長していく。サマンサもまたシリルに愛情を与えることで、自分の内にある母性に気づき、人を守ることの責任と喜びを知っていく。どんなに厳しい境遇におかれても、人は誰かとつながることで一筋の光を見出せる――。ダルデンヌ監督は、シリルとサマンサの小さな感情の機微を丁寧にすくいあげ、「彼ら(ダルデンヌ監督)の作品の中で最も優しい映画」(メトロ)と評されるように普遍的な珠玉の作品に仕上げている。
「裏切られ、助けを得る無垢な少年の物語によって、 ダルデンヌ兄弟にしかできない映画形式に立ち戻る。 『ケス』以来、いや、『自転車泥棒』以来の最良の子ども映画といっても文句はないだろう。」 (――スクリーン・デイリー)
