
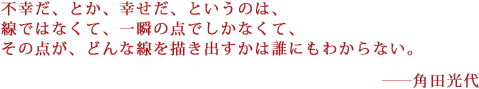
『八日目の蝉』原作者の角田光代は
「母性というものをあまりにも当たり前に女性に押しつけているのではないか、
そのことが女性たちを苦しめているのではないか。」と問い、
この作品を通して「母性とは何なのかを考えたかった。」と語っている。
幼い頃、台所にいる母に向かって「わたし本当はこの家の子じゃないでしょ?」という質問をしたことがあり、
「そうだよ。」と言われたらどうしよう…とドキドキしながら返答を待っていると、
母はあきれた顔で「あんたとお父さんの指の形そっくりだから大丈夫よ。」と言われ、確認しに父の元へ走った記憶がある。
ある日突然大好きだった母と引き離され、見知らぬ人から「私達が本当の家族なのよ。」と言われ、
聞き覚えのない名前で呼ばれる感覚とは一体どんなものなのだろうか。
監督・脚本家・出演者全員が原作のファンという環境の中で、
丁寧に紡がれていくストーリー展開は観ていてとても心地がいい。
八日目を生き延びてしまった蝉にしか見えない景色、
その運命から目を背けるのではなく、前に進むために必要なものが何なのかを、
観る者の「母性」または「父性」に優しく訴えかけてくれる。
一方『マイ・バック・ページ』に出てくる若者達は、
目には見えない何かを信じながら根拠なく突き進んでいく。
舞台は1970年前後の日本。街や人はエネルギーに満ち溢れており、
映画・音楽・サブカルチャーと同じくらい、若者が政治に興味を持っていた時代だ。
大学に進んだ者の多くが“世界の未来は自らの行動で変えていくんだ”という使命感に燃えながら、
反政府を謳い学生運動に励んでいた。
次第にのめり込み、空回りしていく自分から離れていく者の背中さえも目に入らなくなった時、
後戻りできない事件を犯してしまうことになる。
本物に近づくために振りかざす中身のない権力や、
熱くなりすぎて周りが見えなくなっていく様は痛々しいが、
それが間違いだと気づき、点が線になる瞬間は素晴らしい。
何かのせいにして生きていた自分から解き放たれ、
自らの存在意義を導き出した彼らの姿に、あなたは何を思うだろうか。
(ぐり)
マイ・バック・ページ
(2011年 日本 141分 ビスタ/SRD)
 2011年10月8日から10月14日まで上映
■監督 山下敦弘
2011年10月8日から10月14日まで上映
■監督 山下敦弘
■脚本 向井康介
■原作 川本三郎『マイ・バック・ページ』(平凡社刊)
■撮影 近藤龍人
■音楽 ミト(from クラムボン)、きだしゅんすけ
■出演 妻夫木聡/松山ケンイチ/忽那汐里/石橋杏奈/韓英恵/中村蒼/長塚圭史/山内圭哉/古舘寛治/あがた森魚/三浦友和
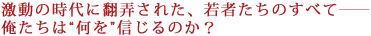
1969年。暴力で世界を変えられると信じた若者たちがいた時代。東大安田講堂事件を契機に、全共闘運動が急激に失速していった時代。東都新聞社で「週刊東都」の記者として働く沢田雅巳は、激動する“今”と葛藤しながら、日々活動家たちを追いかけていた。それから2年後、もはや崩壊の一途をたどり、大衆の支持を失った一部の活動家は、より直接的な武力闘争へと突き進み始めていた。そんな中、取材を続ける沢田は、先輩記者の中平とともに、梅山と名乗る男からの接触を受ける。
「銃を奪取し武器を揃えて、われわれは4月に行動を起こす。」意気揚々とそう語る梅山を、中平は“偽物”だと断じる。しかし沢田は、「宮沢賢治論」を読み、傍らのギターを手にCCRの「雨を見たかい」を口ずさむ梅山に、同時代の親近感を覚え、魅かれていく。そして、事件は起きた。“駐屯地で自衛官殺害”のニュースが沢田のもとに届くのだった――。
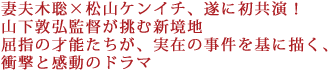
昨年公開された『悪人』で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞の栄冠を手にした妻夫木聡。『GANTZ』『ノルウェイの森』など様々な話題作で多彩な魅力を披露し続ける松山ケンイチ。この二大スターが、満を持して初共演を果たしたのが『マイ・バック・ページ』である。監督は05年『リンダリンダリンダ』を大ヒットに導き、08年『天然コケッコー』では第32回報知映画賞最優秀監督賞を受賞するなど、今最も注目を集める若き奇才・山下敦弘。文芸・映画評論など広く活躍する川本三郎のノンフィクションの原作を基に、4年ぶりに渾身の想いでメガホンをとった。
1960年代後半―今の日本が失った“社会の熱”が渦巻いていた時代。海の向こうにはヴェトナム戦争が、国内では反戦運動や全共闘運動が起きていた。そんな激動の時代の中で、二人の若者の運命的な出会いによって引き起こされた衝撃の事件を描く本作だが、作品の根底にあるのは、激動する「現実」と身を焦がす「理想」の狭間で思い悩む、若者たちの姿である。そこにはない“何か”を求めるが故の葛藤と挫折。彼らはいったい“何を”信じたのか?時代を越えた感動のドラマが、私たちの魂を揺さぶる。


八日目の蝉
(2011年 日本 147分 ビスタ/SRD)
 2011年10月8日から10月14日まで上映
■監督 成島出
2011年10月8日から10月14日まで上映
■監督 成島出
■原作 角田光代『八日目の蝉』(中公文庫刊)
■脚本 奥寺佐渡子
■撮影 藤澤順一
■音楽 安川午朗
■出演 井上真央/永作博美/小池栄子/森口瑶子/田中哲史/余貴美子/平田満/風吹ジュン/劇団ひとり/田中泯
![]()
 21年前、秋山丈博と美津子夫婦の間に生まれた生後4カ月の恵理菜を誘拐した野々宮希和子。会社の上司であった秋山を愛し、子供を身ごもったが、それは叶わぬ願いだった。子を諦めた絶望の中で、希和子は秋山と妻の間に生まれた赤ん坊を発作的に連れ去る。新聞やニュースに怯えながら各地を転々とする希和子。流れ着いた小豆島でひと時の安らぎを得るが、捜査の手はすぐそこまで迫っていた。そして福田港のフェリー乗り場で、4年に及ぶ逃避行は終わる。
21年前、秋山丈博と美津子夫婦の間に生まれた生後4カ月の恵理菜を誘拐した野々宮希和子。会社の上司であった秋山を愛し、子供を身ごもったが、それは叶わぬ願いだった。子を諦めた絶望の中で、希和子は秋山と妻の間に生まれた赤ん坊を発作的に連れ去る。新聞やニュースに怯えながら各地を転々とする希和子。流れ着いた小豆島でひと時の安らぎを得るが、捜査の手はすぐそこまで迫っていた。そして福田港のフェリー乗り場で、4年に及ぶ逃避行は終わる。
 秋山恵理菜は21歳の大学生になっていた。4歳で初めて実の両親に会い、私たちが正真正銘の家族だと言われても、実感が持てなかった。本当の家族の元に戻っても、「ふつう」の生活は望めず、心を閉ざしたまま成長した恵理菜は、ある日自分が妊娠していることに気づく。相手は、希和子と同じ、家庭をもつ男だった。過去と向き合い、かつて希和子と暮らした小豆島へと向かった恵理菜が見つけた真実。そして、恵理菜の下した決断とは…?
秋山恵理菜は21歳の大学生になっていた。4歳で初めて実の両親に会い、私たちが正真正銘の家族だと言われても、実感が持てなかった。本当の家族の元に戻っても、「ふつう」の生活は望めず、心を閉ざしたまま成長した恵理菜は、ある日自分が妊娠していることに気づく。相手は、希和子と同じ、家庭をもつ男だった。過去と向き合い、かつて希和子と暮らした小豆島へと向かった恵理菜が見つけた真実。そして、恵理菜の下した決断とは…?
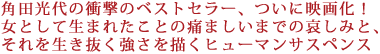
 希代のストーリーテラー、角田光代の最高傑作との呼び声高い「八日目の蝉」。各メディアから絶賛されたベストセラー小説を、『孤高のメス』で日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞した成島出がメガホンを取り、遂にスクリーンに登場する。主人公の恵理菜を演じるのは、現在上映中の朝の連続テレビ小説『おひさま』など、老若男女から人気を得ている井上真央。今までのイメージを覆す難役で新境地を開拓した。対する希和子を演じるのは、『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』で助演女優賞を総なめにした永作博美。脇役にも名だたる俳優陣が名を連ね、数々のスクリーンを彩った。
希代のストーリーテラー、角田光代の最高傑作との呼び声高い「八日目の蝉」。各メディアから絶賛されたベストセラー小説を、『孤高のメス』で日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞した成島出がメガホンを取り、遂にスクリーンに登場する。主人公の恵理菜を演じるのは、現在上映中の朝の連続テレビ小説『おひさま』など、老若男女から人気を得ている井上真央。今までのイメージを覆す難役で新境地を開拓した。対する希和子を演じるのは、『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』で助演女優賞を総なめにした永作博美。脇役にも名だたる俳優陣が名を連ね、数々のスクリーンを彩った。
蝉は、何年も土の中にいて、地上に出て七日間で死ぬという。でももし、八日目まで生きた蝉がいたとしたら、その蝉は幸せなのだろうか?何もかも失い自分は「からっぽ」だと、まるで他の人が知る筈もない“八日目”を生きているようなものなのだと思っていた女たちが、哀しみや孤独を乗り越え、自分の足で一歩踏み出していく姿に、あなたは心を打たれるに違いない。
