

1932年、モスクワ生まれ。父親は詩人のアルセーニイ・タルコフスキー。音楽、絵画の勉強を経て、落ちこぼれの不良少年ながらも(父の尽力もあり)奇跡的に名門校、国立映画大学へ。在学中は後にソ連を代表する映画監督となるアンドレイ・コンチャロフスキーと親交を結ぶ。
1962年、『僕の村は戦場だった』で長編デビュー、ヴェネチア映画祭でグランプリを受賞。
現実や人間を見つめる芸術家の真摯な姿勢は、その作品の真価をめぐって映画行政との対立が絶えなかったが、映像作家としての輝かしい才能は、寡作ながらも映画史に残る名作を生み出し続けた。1986年12月28日、パリで肺がんのため夭逝。

・ローラーとバイオリン(1960)
・僕の村は戦場だった(1962)
・特攻大戦略(1968)*未公開/脚本のみ
・アンドレイ・ルブリョフ 動乱そして沈黙/試練そして復活(1969)
・惑星ソラリス(1972)
・鏡(1974)
・ストーカー(1979)
・ノスタルジア(1983)
・サクリファイス(1986)
今週の早稲田松竹はアンドレイ・タルコフスキー特集。珠玉の作品群から、タルコフスキーの名を世界に知らしめたSF映画の金字塔『惑星ソラリス』と監督の自伝的作品『鏡』を上映いたします。
アンドレイ・タルコフスキー(1932〜1986)は、人の“救済”を描いた映画作家。流麗な長回しが綾なすタルコフスキーの作品には一切の妥協がなく、表現の自由を求めて母国ソ連を亡命するなど、文字通り、映画に生涯を捧げた。
木立を抜ける風のそよぎにも人間の心象を映し出して見せる
私はタルコフスキーの映画を観ていると、どうしても懐かしさを感じてしまう。子供のころに仰ぎ見た力強い父や美しく優しい母の姿、自然が文明を覆いつくした廃墟、生命の根源である水と火。
一体、“懐かしさ”とは何だろう。人はいつだって過去に思いを馳せてきた。だが懐かしさは絶えず喪失の痛みをも伴っているものだ(あの頃はよかった…。けれど大人である私は子供の頃には二度と戻れない)。
“何かが失われてしまった”
形あるものを永遠に失うこと。例えば誰かと死別すること、あるいは恋人や夫婦が今生に別れてしまうこと。様々なレベルはあれ、決して修復できない、取り戻すことのできない、そのような喪失。そうした喪失を一貫して描いてきたのがタルコフスキーという人だった(例えば、祖国ソ連を亡命して製作された『ノスタルジア』が監督の故郷へのエレジーであったように)。
『惑星ソラリス』では巨大な脳のように思考力を持った海が、クリスの意識下を読み取り、亡き妻ハリーの幻を現前させる。幻影であるハリーを振り払おうとするクリスを他所に、ハリーは何度も何度も甦り彼の前に立ち現れる。そこに、クリスの深層に隠されていたシコリが海に浮かぶ島のようにポツンと浮かび上がる。
監督自身の記憶が作品となっている『鏡』では幼いときに別れた父、アルセーニイ・タルコフスキーの詩が、息子である監督アンドレイによって朗誦される。“私”は記憶の欠片から父や母、別れた妻子との関係を、輝かしかった日々を、モノローグでポツポツと物語る。過去と現在が乖離していることの、その言い知れぬ悲しみ。
両作品は決して失われてしまったものを称揚しているのではない。そうではなく、失われてなお留まり続けるもの(それは幻影となって現在に回帰する亡霊のようなものかもしれない)と対峙すること、失われてなお、残照のように照らす、人の心象にこそ問題を提起している。
忘却の彼方に妻の死を追いやったクリスが、“ソラリスの海”によって彼の中に住まう妻と対面した時に、クリスの内に湧き上がったきたもの。
“私”の、過去と現在の交差、親子の、妻子との関係の変化から呼び起こされるもの。
それは一体何なのだろうか?
過去と対面したことで甦るもの。
忘却した(はずだった)ことを思い出した時、凝った感情が氷解して、激しく揺れ動きはじめる。「喪失を乗り越えた再生」と「喪失を内面に所有して、なお堅固に生き続けること」。どちらかが正しいのかではなく、タルコフスキーはこのアンビバレンスこそを終生のテーマとしていた。
人は何かを忘れることが出来る。
そして忘れ得ぬものがあることも、又然り。
いずれにしても、喪失からいかに人間が再び立ち上がるのか。タルコフスキーが描く、その激しく揺り動くエモーショナルで劇的な過程は何度も観ても私たちを驚かせるだろう。
(ミスター)
鏡
ЗЕРКАЛО
(1975年 ソ連 110分 SD/MONO)
 2011年10月29日から11月4日まで上映
2011年10月29日から11月4日まで上映
■監督・脚本 アンドレイ・タルコフスキー
■脚本 アレクサンドル・ミシャーリン
■撮影 ゲオルギー・レルベルグ
■音楽 エドゥアルド・アルテミエフ
■挿入詩 アルセーニイ・タルコフスキー
■出演 マルガリータ・テレホワ/オレーグ・ヤンコフスキー/イグナト・ダニルツェフ/フィリップ・ヤンコフスキー
★本編はカラーです。
★プリントの経年劣化のため、本編上映中お見苦しい箇所・お聞き苦しい箇所がございます。ご了承の上、ご鑑賞いただきますようお願いいたします。
![]()
 うっそうと茂る立木に囲まれた家の中で、母は、たらいに水を入れ髪を洗っている。鏡に映った、水にしたたる母の長い髪が揺れている。あれは1935年、田舎の干し草置き場で火事のあった日のこと。その年から父は家からいなくなった…。…両親と同様、私も妻ナタリアと別れた。妻は、私が自信過剰で人と折り合いが悪いと非難し、息子イグナートも渡さないと頑張っている。
うっそうと茂る立木に囲まれた家の中で、母は、たらいに水を入れ髪を洗っている。鏡に映った、水にしたたる母の長い髪が揺れている。あれは1935年、田舎の干し草置き場で火事のあった日のこと。その年から父は家からいなくなった…。…両親と同様、私も妻ナタリアと別れた。妻は、私が自信過剰で人と折り合いが悪いと非難し、息子イグナートも渡さないと頑張っている。
ふと私は、息子と同じ年頃の時代の事を思い出した。赤毛の、唇がいつも乾いて荒れていた初恋の女の子のこと。同級生達と受けた軍事教練のこと。そして、大戦中、疎開先のユリヴェツにいた時、母に連れられて遠方の祖父の知人を訪ねて、宝石を売りに行ったこと…。そして哀れだった母のことが、少年時代の記憶が、同じ境遇をたどっているイグナートのことが私を苦しめる…。
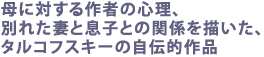
 『鏡』は、主人公が母親や別れた妻子との関係を詩的モノローグのスタイルで物語る、タルコフスキーの自伝的作品である。これまでの叙事詩的な世界から、一気に非常に私的なテーマにとりくんだ。“私”(作者)の、母と家族に対する様々な思いが、監督独自の“火”や“水”の自然現象の映像化を伴なって、美しい幻想的なイメージのなかに繊細かつ鮮明に語られる。意識下の過去を現実と交錯させながら作者の深層心理を浮き彫りにしていく映像表現は特に見事である。
『鏡』は、主人公が母親や別れた妻子との関係を詩的モノローグのスタイルで物語る、タルコフスキーの自伝的作品である。これまでの叙事詩的な世界から、一気に非常に私的なテーマにとりくんだ。“私”(作者)の、母と家族に対する様々な思いが、監督独自の“火”や“水”の自然現象の映像化を伴なって、美しい幻想的なイメージのなかに繊細かつ鮮明に語られる。意識下の過去を現実と交錯させながら作者の深層心理を浮き彫りにしていく映像表現は特に見事である。
 くわえて、1934年ソ連成層圏飛行、スペイン戦争、第二次世界大戦など、数多くの記録フィルムの断片が挿入され、歴史的現実が人々にもたらさずにはいない種々な影響を暗示している。撮影はゲオルギー・レルベルグ。ロシアの自然を象徴的に捉え、非常に印象的なカットを生んだ。主演はマルガリータ・テレホワと『ノスタルジア』のオレーグ・ヤンコフスキー。監督自らも著名な詩人である父アルセーニイ・タルコフスキーの詩を朗読している。
くわえて、1934年ソ連成層圏飛行、スペイン戦争、第二次世界大戦など、数多くの記録フィルムの断片が挿入され、歴史的現実が人々にもたらさずにはいない種々な影響を暗示している。撮影はゲオルギー・レルベルグ。ロシアの自然を象徴的に捉え、非常に印象的なカットを生んだ。主演はマルガリータ・テレホワと『ノスタルジア』のオレーグ・ヤンコフスキー。監督自らも著名な詩人である父アルセーニイ・タルコフスキーの詩を朗読している。


惑星ソラリス
СОЛЯРИС
(1972年 ソ連 165分 シネスコ/MONO)
 2011年10月29日から11月4日まで上映
2011年10月29日から11月4日まで上映
開映時間 13:30 / 18:45
■監督・脚本 アンドレイ・タルコフスキー
■原作 スタニスワフ・レム『ソラリスの陽のもとに』(早川書房刊)
■脚本 フリードリヒ・ガレンシュテイン
■撮影 ワジーム・ユーソフ
■音楽 エドゥアルド・アルテミエフ
■出演 ナタリア・ボンダルチュク/ドナタス・バニオニス/ユーリー・ヤルヴェト/ウラジスラフ・ドヴォルジェツキ
■1972年カンヌ国際映画祭審査員特別賞・国際エヴァンジェリー映画センター賞
★プリントの経年劣化のため、本編上映中お見苦しい箇所・お聞き苦しい箇所がございます。ご了承の上、ご鑑賞いただきますようお願いいたします。

 惑星ソラリス、それは宇宙のかなたの謎の星で、生物は存在は確認されないが、理性を持った有機体と推測されるプラズマ状の"海"によって被われていた。世界中の科学者達の注目が集まり、"海"と接触しようとする試みが幾度か繰り返されたが、いずれも失敗に終った。そして、ソラリスの軌道上にある観測ステーションは原因不明の混乱に陥ってしまっていた。
惑星ソラリス、それは宇宙のかなたの謎の星で、生物は存在は確認されないが、理性を持った有機体と推測されるプラズマ状の"海"によって被われていた。世界中の科学者達の注目が集まり、"海"と接触しようとする試みが幾度か繰り返されたが、いずれも失敗に終った。そして、ソラリスの軌道上にある観測ステーションは原因不明の混乱に陥ってしまっていた。
 心理学者クリスが原因究明と打開のために送られることになった。美しい緑に囲まれた我が家を後に宇宙ステーションヘと飛び立つクリス…。しかし彼を待っていたのは異常な静寂と恐しい程の荒廃だった。物理学者ギバリャンは謎の自殺を遂げ、残った二人の科学者も何者かに怯えている。そんなある日、突然クリスの前に、すでに10年前に自殺した妻ハリーが現われた。彼女はソラリスの"海"が送ってよこした幻だった。"海"は人間の潜在意識を探り出してそれを実体化していたのである。妻の自殺に悔恨の思いを抱いていたクリスは、遂には幻のハリーを愛するようになるが、科学者としての使命感と個人的な良心との相剋に悩まされる…
心理学者クリスが原因究明と打開のために送られることになった。美しい緑に囲まれた我が家を後に宇宙ステーションヘと飛び立つクリス…。しかし彼を待っていたのは異常な静寂と恐しい程の荒廃だった。物理学者ギバリャンは謎の自殺を遂げ、残った二人の科学者も何者かに怯えている。そんなある日、突然クリスの前に、すでに10年前に自殺した妻ハリーが現われた。彼女はソラリスの"海"が送ってよこした幻だった。"海"は人間の潜在意識を探り出してそれを実体化していたのである。妻の自殺に悔恨の思いを抱いていたクリスは、遂には幻のハリーを愛するようになるが、科学者としての使命感と個人的な良心との相剋に悩まされる…

 本作は、スタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』(1968年)と比肩されるSF映画の傑作と称され、アンドレ・タルコフスキーの名を不朽のものにした。原作はスタニスラム・レムの「ソラリスの陽のもとに」であるが、"未知なるもの"と遭遇して極限状況に置かれた人間の内面に光をあて、「愛」と「良心」をめぐる道徳・哲学的な問題を提起。深い洞察と独得の映画表現によって、映像による思弁ともいうべきタルコフスキーの世界を構築している。これまでのSF映画に見られない新たな地平を拓いた画期的作品として、多くのファンを今なお魅了し続けている作品である。
本作は、スタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』(1968年)と比肩されるSF映画の傑作と称され、アンドレ・タルコフスキーの名を不朽のものにした。原作はスタニスラム・レムの「ソラリスの陽のもとに」であるが、"未知なるもの"と遭遇して極限状況に置かれた人間の内面に光をあて、「愛」と「良心」をめぐる道徳・哲学的な問題を提起。深い洞察と独得の映画表現によって、映像による思弁ともいうべきタルコフスキーの世界を構築している。これまでのSF映画に見られない新たな地平を拓いた画期的作品として、多くのファンを今なお魅了し続けている作品である。
なお、原作にはない"地上のプロローグ"の未来都市のシーンは東京で撮影され、1972年夏、タルコフスキー監督はロケ撮影のため来日した。東洋哲学わけても日本の中世思想に共感を示したタルコフスキーだが、この来日が最初にして最後となってしまった。
