
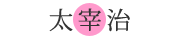
太宰治(だざい・おさむ)
1909年6月19日〜1948年6月13日。
日本の近代文学を代表する作家。青森県北津軽郡金木村(現・五所川原市金木町)に生まれる。本名は津島修治(つしま・しゅうじ)。東大仏文科に在学中に、非合法運動に関わるが脱落。酒場の女性と鎌倉の小動崎で心中をはかり、ひとり助かる。
1935年「逆行」が第一回芥川賞の次席となり、翌年、第一回創作集「晩年」を刊行。この頃、パビナール中毒に悩む。「晩年」以降、話術に長けた文体で短・長篇を発表し若い読者の心をとらえる。
1939年、石原美知子と結婚。平穏な生活を得て「富嶽百景」を発表。同年9月、三鷹村(現・三鷹市)へ転居。「走れメロス」「きりぎりす」など多くの佳作を執筆。戦後、「斜陽」などの発表により、織田作之助、坂口安吾らと共に無頼派として注目され、ベストセラー作家となる。「ヴィヨンの妻」「桜桃」など三鷹での生活を素材とした作品も継続して残した。
1948年、「グッド・バイ」連載中の6月13日に山崎富栄と玉川上水で入水し、没。生涯で自殺未遂、心中未遂を繰り返し五度目で死に至った太宰の遺体が発見されたは、奇しくも39歳の誕生日にあたる6月19日であった。この日は「桜桃忌」として知られ、太宰の墓のある三鷹の禅林寺には多くの愛好家が訪れる。
<作品一覧>
晩年/虚構の彷徨、ダス・ゲマイネ/ 二十世紀旗手 愛と美について/ 女生徒/ 皮膚と心/ 思ひ出/ 走れメロス/ 女の決闘/ 東京八景/新ハムレット/千代女/ 駆込み訴へ/ 風の便り/老ハイデルベルヒ/ 正義と微笑/ 女性/ 富嶽百景/ 右大臣実朝/ 佳日/ 津軽/新釈諸国噺/惜別/お伽草紙/パンドラの匣/薄明/冬の花火/ヴィヨンの妻/斜陽/人間失格/桜桃
進入学のみなさま。新社会人のみなさま。おめでとうございます!!
4月です。春です。桜はもう満開です。
新年度がスタートして、みなさまの生活にもいろんな変化があったのじゃないかなと思います。出会いと別れ。新しく何かを始めることになったり、あるいは何かを終えた方も。そんなみなさまの新しい生活の始まりに、今週は太宰治特集をお届け致します。
お届けするのはこちらの2本。太宰治の生誕100周年であった昨年秋、同日公開となった『パンドラの匣』と『ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜』。太宰治といえば、死の間際に書き上げた『人間失格』のように自虐的かつ退廃的な作品や、入水自殺でその短い生涯を閉じたことなどが非常に有名です。おそらく、「春に太宰」と聞いてもピンとこない方が多いのではないでしょうか。
でも、この2本はちょいと毛色が違います。『パンドラの匣』の監督・冨永昌敬は、この原作の持つ世界観を“太宰治の描くハードボイルド版『うる星やつら』的学園ドラマ”と表現しました。また、モントリオール世界映画祭の創設者セルジュ・ロジーク氏は、『ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜』を“日本特有の男女関係を描いたように見えるが、実際は普遍的なもの”と絶賛。これらは太宰ならではの「かるみ」で描かれた青春と、ある夫婦の生き様を丁寧に描いた愛の物語なのです。
ちなみにこの2本、同じ作家を原作としながらもその布陣は対照的。かたや、大学の卒業制作から脚光を浴び、瞬く間に時代の寵児となった若き鬼才・冨永昌敬チーム。フレッシュな顔ぶれを大胆に起用し、映画界にどでかい風穴を空けるような観たことの無い文芸映画を作りあげました。対するはロマンポルノからの叩き上げ、日本映画界きってのいぶし銀監督・根岸吉太郎チーム。脚本家・田中洋造を相棒に、老舗の超高級料亭のように贅沢な役者とスタッフを結集させて、まだまだ若手には譲らねーぞ!と生粋の映画職人魂を見せつけています。
『パンドラの匣』の主人公・ひばりは新しい時代の新しい男に生まれ変わろうとします。新しい生活になんだか胸騒ぎするようなこの季節、みなさまも「今日から俺は…」とそれぞれの決意を秘め、初心を持たれているんじゃないかなと思います。そんな季節とそんなあなたにビッタリの2本立て、「観る」太宰治の世界です。
パンドラの匣
(2009年 日本 94分 ビスタ/SRD) 2010年4月3日から4月9日まで上映
■監督・脚本・編集 冨永昌敬
2010年4月3日から4月9日まで上映
■監督・脚本・編集 冨永昌敬
■原作 太宰治 『パンドラの匣』
■撮影 小林基己
■音楽 菊地成孔
■出演 染谷将太/川上未映子/仲里依紗/窪塚洋介/ふかわりょう/洞口依子/ミッキー・カーチス
![]()
ギリシャ神話の美女パンドラは、開けてはならない匣(はこ)に好奇心を募らせ、ふたに手を掛けた。すると、病苦、悲哀、嫉妬、貪慾、猜疑、陰険、飢餓、憎悪など、あらゆる不吉の虫が這い出し、空を覆ってぶんぶん飛び廻り、それ以来人間は永遠に不幸に悶えなければならなくなった。しかし、その匣の隅にはけし粒ほどの小さい光る石が残っていた。その石には幽かに「希望」という字が書かれていたという――。主人公ひばりの信じるギリシア神話。そのポジティブな世界観。
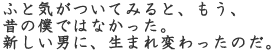
 舞台は、当時死病と呼ばれた結核患者を集めた“健康道場”という風変りな療養所。ここでは、院長は場長、お医者は指導員、看護婦さんは助手、入院患者は塾生と呼ばれている。「やっとるか」「やっとるぞ」「がんばれよ」「よしきた」…すれちがった時などには、必ずこの挨拶を交すのが決まりだ。ひばりは、戦争が終わったのを機に“新しい男”になることを決め、ここにやってきた。個性的な仲間に囲まれながら過ごすひばりに、やがて訪れたのは…。
舞台は、当時死病と呼ばれた結核患者を集めた“健康道場”という風変りな療養所。ここでは、院長は場長、お医者は指導員、看護婦さんは助手、入院患者は塾生と呼ばれている。「やっとるか」「やっとるぞ」「がんばれよ」「よしきた」…すれちがった時などには、必ずこの挨拶を交すのが決まりだ。ひばりは、戦争が終わったのを機に“新しい男”になることを決め、ここにやってきた。個性的な仲間に囲まれながら過ごすひばりに、やがて訪れたのは…。
主人公の“新しい男”ひばりを演じるのは、オーディションで選ばれた期待の16歳(!)染谷将太。助手長・竹さん役には芥川賞作家の川上未映子。もう一人のヒロイン、舌っ足らずで小悪魔的な新人助手マア坊役には、アニメ『時をかける少女』で主演声優を務めた仲里依紗。そして、ひばりの親友で詩人のつくし役に窪塚洋介、ひばりの母親役に洞口依子、インテリ学生固パン役にふかわりょう、場長にミッキー・カーチスと、個性的な面々が揃った。それぞれ思い切った配役ながら、お見事としか言い様の無い完璧なはまりっぷり。
それを盛り立てるのが、『パビリオン山椒魚』以来の共演となる、ジャズミュージシャン菊池成孔の音楽。不思議な劇中歌「オルレアンの少女」はいつまでも耳に残って離れない。ひばりからつくしに宛てた手紙形式で進行していく本作、昭和期の文芸映画さながらにオール・アフレコで録音されたセリフとあいまって、なんとも心地よいオペレッタのような味わいに。
今後の日本映画界を牽引していくであろう若き鬼才・富永に導かれ、異質な才能がグワッと一堂に会した様はまさに学園ドラマ的ワクワク感。ダークサイドの作家太宰によって描かれた「かるみ」の味わい、どうぞ御堪能下さい。
「今から60数年前、健康道場は実在した。取材のためにお会いした本物の“マア坊”は、私の祖父母と同世代であった。そうであるからには、意地っ張りで可愛らしいこの映画の主人公たちに、私たちと同世代の孫がいたとして何の不思議もない。そう思うと妙に嬉しくなってきた。なにしろ、たった64年前の出来事なのだから」――冨永昌敬(監督)


ヴィヨンの妻 〜桜桃とタンポポ〜
(2009年 日本 114分 ![]() ビスタ/SRD)
ビスタ/SRD)
 2010年4月3日から4月9日まで上映
■監督 根岸吉太郎
2010年4月3日から4月9日まで上映
■監督 根岸吉太郎
■原作 太宰治『ヴィヨンの妻』
■脚本 田中陽造
■撮影 柴主高秀
■音楽 吉松隆
■出演 松たか子/浅野忠信/室井滋/伊武雅刀/広末涼子/妻夫木聡/堤真一/光石研/山本未來/鈴木卓爾/小林麻子/信太昌之/新井浩文
■第33回モントリオール世界映画祭最優秀監督賞
![]()
 戦後、混乱期の東京。作家の大谷は、文才に溢れながらも酒に溺れて借金を重ね、妻以外の女にも次から次へと手を出してしまう破滅的な男。そんな夫の放蕩を知りながらも許す誠実で美しい妻・佐知は、ひょんなことから夫の借金を返すために飲み屋・椿屋で働き始める。あっという間にお店の人気者となり、日に日に輝きを増していく佐知に嫉妬する大谷は、書くことをそして生きることを苦悩し、遂に愛人と心中未遂を起こしてしまう。それを知った佐知は…。
戦後、混乱期の東京。作家の大谷は、文才に溢れながらも酒に溺れて借金を重ね、妻以外の女にも次から次へと手を出してしまう破滅的な男。そんな夫の放蕩を知りながらも許す誠実で美しい妻・佐知は、ひょんなことから夫の借金を返すために飲み屋・椿屋で働き始める。あっという間にお店の人気者となり、日に日に輝きを増していく佐知に嫉妬する大谷は、書くことをそして生きることを苦悩し、遂に愛人と心中未遂を起こしてしまう。それを知った佐知は…。
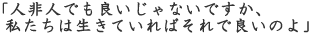
タイトルの“ヴィヨン”とは、高い学識を持ちながらも強盗・殺人などの罪を犯し、逃亡・入獄・放浪の生活を送った近代詩の先駆者フランソワ・ヴィヨンのこと。放蕩の果てに飲み屋の金まで奪って逃げた主人公・大谷のように、フランスではダメ男の例えとして使われるんだとか。
 太宰自身のイメージをそのまま投影したような作家・大谷。実際の太宰はこんな男だったのではないかと思わせるナイーブで繊細、誠実なのに身勝手で破滅的な作家像を、浅野忠信が見事に演じきった。大谷の妻・佐知を演じたのは、意外にも主演は初となる松たか子。脚本を手掛けたのは、鈴木清順『ツィゴイネルワイゼン』、相米慎二『セーラー服と機関銃』などで知られる田中陽造。太宰の著作『ヴィヨンの妻』を中心に、『思ひ出』『灯籠』『姥捨』『きりぎりす』『桜桃』『二十世紀旗手』を組み合わせ、当初から松たか子による佐知を想定して執筆したという。
太宰自身のイメージをそのまま投影したような作家・大谷。実際の太宰はこんな男だったのではないかと思わせるナイーブで繊細、誠実なのに身勝手で破滅的な作家像を、浅野忠信が見事に演じきった。大谷の妻・佐知を演じたのは、意外にも主演は初となる松たか子。脚本を手掛けたのは、鈴木清順『ツィゴイネルワイゼン』、相米慎二『セーラー服と機関銃』などで知られる田中陽造。太宰の著作『ヴィヨンの妻』を中心に、『思ひ出』『灯籠』『姥捨』『きりぎりす』『桜桃』『二十世紀旗手』を組み合わせ、当初から松たか子による佐知を想定して執筆したという。
さらに、室井滋、伊武雅刀、広末涼子、妻夫木聡、堤真一、鈴木卓爾、新井浩文と、錚々たる面々が顔を揃えた。衣装デザインは黒澤明の娘、黒澤和子。フードスタイリストは、『かもめ食堂』の飯島奈美。『THE 有頂天ホテル』『フラガール』『空気人形』を手がけた美術監督・種田陽平は、舞台の中野駅や吉祥寺へ向かう街の佇まいを見事に再現(中央線在住の人は特に注目!)。オールスターで結成されたこのチーム、率いた根岸監督にはモントリオール世界映画祭にて最優秀監督賞が贈られた。
「人間の一生は地獄でございまして、寸善尺魔とは、まったく本当の事でございますね。一寸の仕合せには一尺の魔物が必ずくっついてまいります。人間三百六十五日、何の心配も無い日が、一日、いや半日あったら、 それは仕合せな人間です。」――太宰治「ヴィヨンの妻」より
