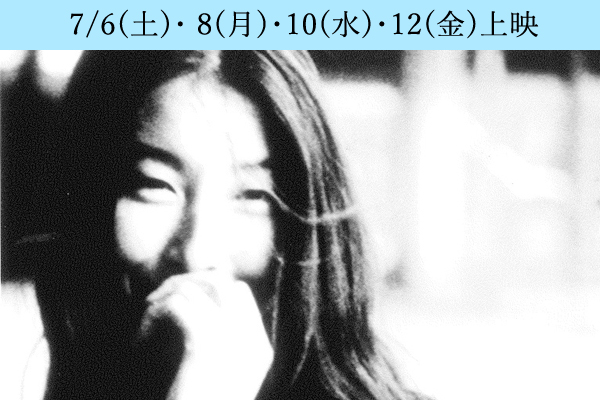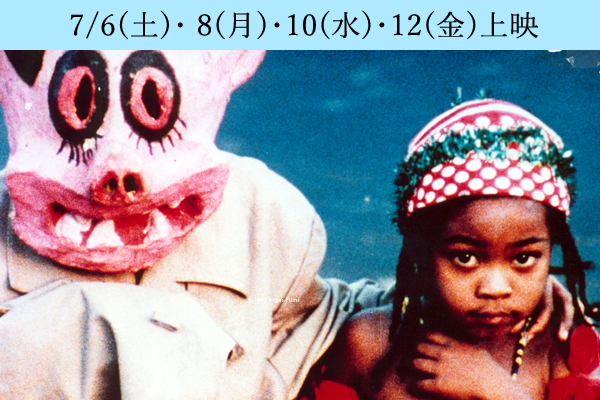パズー
数年前、あるショッピングセンターの広告の「運命を狂わすほどの恋を、女は忘れられる」というキャッチコピーに衝撃を受けた。女だけかどうかは置いておいて、人の記憶ってけっこう、意識的であれ無意識であれ自分のなかでコントロールしているんじゃないかと思う。あの日のこと、あの人のことは絶対に忘れられないとかよく言うけど、ほんとうは「忘れられない」んじゃなくて、「忘れたくない」から「忘れないようにしてる」ことのが多いんじゃないか。良い思い出、良い記憶にしたいから。忘れちゃったらどうでもいいことになっちゃうから。
記憶というのはとても曖昧なものだと思う。ほんとうは鮮明に覚えていることでも、誰かに伝える時には主観を入れたり話を盛ったりしてしまいがちだし、そのうちにそっちのほうがほんとうの記憶になってしまったりする。自分の体験、他人の体験、さらには社会的な事柄が混ざってきたり。3.11のことを思い出すときなんてまさにそうで、自分のことと友達のこと、それからニュースまでぐちゃぐちゃにして、全部が3.11の記憶になっている。でも記憶ってそもそもそういうもので、個人のものだけじゃない。
SNSによって、他人の体験や記憶を簡単に、しかもリアルタイムで共有できるようになったことは、かなりいろいろな価値観を変えてしまった。たとえば有名人が死んだとき、その人が昨日まで更新していたSNSは途端に過去のものになる。いたはずの人が今はもういないという感覚が、本人に会ったこともないのにネットを通じて世界中の人がいっせいに感じる。SNSは不思議な遺品のようなものになる。誰かの個人史をリアルタイムで知れるというのは、ちょっとタブウのような、怖い感じがする。だけど、この感覚を知ってしまった私たちは、それをやめられない気がする。
全然まとまってないけれど、とにかく、懐古主義のわたしにとって「人の記憶」はすごく興味深いものなのだ。それから切っても切れない記憶とメディアとの関係も、面白いなぁ不思議だなぁと思う。
そういう感覚を映像にしているのが、クリス・マルケルという人の映画だ。SNSが生まれるずっと前から、記憶の共有についてテーマにしてきた。常に新しい見方、新しい手法、まだ見ぬ世界を探し続けて映像に刻んできた。超クールだし、センス抜群でスタイリッシュ。だけど映す対象についてとても親密で優しい映画でもある。近すぎず、遠すぎないマルケルの作品を観ていると、なんだかすごく心地良い気分になる。
難しいと捉われがちだけれど、マルケルの映画はわからないことはわからないままでもいいと思う。観たまま感じたものを留めておけばいい。きっと、日常を過ごしているときにふと、マルケルの映画のワンシーンが頭をよぎるはずだ。その時に急に映画のことを理解できるかもしれない。そう思わせてくれる、軽やかで斬新なマルケルの映画が大好きだ。
シベリアからの手紙
Lettre de Sibérie
■監督 クリス・マルケル
■撮影 サッシャ・ヴィエルニ/クリス・マルケル
■録音 ルネ・ルージュ/ルネ・ルノー/ロベール・アマール
■特殊効果・アニメーション エキップ・アルカディ
■朗読 ジョルジュ・ルーキエ
■1958年ルイ・リュミエール賞
©1957 Argos Films
【2019年7/6(土)・8(月)・10(水)・12(金)上映】
開発途上のシベリアの街と大地、そこに生きる人々の風景が、随所に挿入されるアニメーションやアーカイヴ映像によって重層的にとらえられる作品。アンドレ・バザンが「エッセイ映画」として本作を紹介し、マルケルの編集を「水平的なモンタージュ」と評するなど、マルケルが独自のスタイルを持った映画作家として注目を集める契機となった。仏ソ協会によって発注され、シベリアへの旅は仏ソ協会会長アンドレ・ピエラール、劇作家アルマン・ガッティ、カメラマンのサッシャ・ヴィエルニと共に行われた。
不思議なクミコ
Le mystère Koumiko
■監督・撮影・編集 クリス・マルケル
■助監督 柴田駿/山田宏一/ミシェル・メスニル/クリスティーヌ・ルクヴェット
■音楽 武満徹
■出演 村岡久美子/クリス・マルケル(ナレーション)
■1966年オーバーハウゼン国際短編映画祭グランプリ(ドキュメンタリー部門)
© La Sofra
【2019年7/6(土)・8(月)・10(水)・12(金)上映】
1964年東京オリンピックを取材する目的で来日したマルケルが、偶然出会ったフランス語を話す美しい日本人女性クミコを被写体にし、彼女を取り巻く東京の風景を切り取った作品。19世紀の漫画「フヌイヤール一家」の抜粋やジャック・ドゥミ『シェルブールの雨傘』への参照など、マルケルらしい間テキスト的な手法を随所に見ることが出来る。マルケルが日本と深い関わりを持つ契機となった記念碑的作品。
サン・ソレイユ
Sans soleil
■監督・撮影・編集 クリス・マルケル
■音楽 モデスト・ムソルグスキー/ミシェル・クラスナ
■歌 アリエル・ドンバル
■特殊効果 山猫駿雄
■1983年ベルリン国際映画祭OCIC特別賞・ロンドン映画祭国際批評家賞、BFI賞(W受賞)
© 1983 Argos Films
【2019年7/6(土)・8(月)・10(水)・12(金)上映】
世界中を旅するカメラマンのサンドール・クラスナから届いた手紙を朗読する女性。その声に合わせてクラスナが「生の存続の二極地」と呼ぶ、日本とアフリカを中心とした映像がつながっていく。マルケルが書いたプレスリリースによれば「反復する主題、対位法、鏡のようなフーガといった作曲の手法」で様々な素材を寄せ集めることで「虚構の記憶が生み出された」という。時間と場所、記憶と歴史、表象の問題について深い考察がなされたマルケルの代表作。日本語版のテキストの朗読は『ベルサイユのばら』の作者として知られる池田理代子が担当している。
北京の日曜日
Dimanche à Pekin
■監督・撮影 クリス・マルケル
■編集 フランシーヌ・グリュベール
■音楽 ピエール・バルボー(作曲)/ジョルジュ・ドルリュー(演奏)
■特殊効果 エキップ・アルカディ
■朗読 ジル・ケアン
■1956年トゥール国際短編映画祭グランプリ
© 1956 Argos Films
【2019年7/7(日)・9(火)・11(木)上映】
1955年、のちに『SHOAH ショア』を発表するクロード・ランズマンら文化人たちと共に友好使節団として中国へ行ったマルケル。彼自身によって撮影された本作は、革命後の希望に満ちた北京の人々と風景がみずみずしく映し出されている。パリのエッフェル塔と北京の旅の思い出の品々がつなげられる冒頭のシーンでは、マルケルの生涯のテーマになった「記憶」の問題がすでに表されており、「中国学についてのアドバイザー」としてアニエス・ヴァルダが紹介されるなど興味深い内容になっている。
ある闘いの記述
Description d'un combat
■監督 クリス・マルケル
■撮影 ギスラン・クロケ
■編集 エヴァ・ゾラ
■音楽 ララン
■朗読 ジャン・ヴィラール
■1961年ベルリン国際映画祭短編映画部門金熊賞
© 1961 Van Leer Productions et S.O.F.A.C
© 2014 Argos Films – Cinémathèque de Jérusalem
【2019年7/7(日)・9(火)・11(木)上映】
1948年の建国以来12年目を迎えたイスラエルの複雑な現実を描いた作品。この映画がベルリン国際映画祭の短編映画部門で金熊賞を受賞したことについて「ドイツでは中国人についてもシベリアの人々についても、おそらくキューバ人についても語ることが出来ないが、少なくともユダヤ人について語ることができることがわかり安堵した」とマルケルは書いている。しかし第三次中東戦争以後、マルケルはこの映画を配給会社から回収し、上映することを一時的に禁じた。
レベル5
Level Five
■監督・撮影・編集 クリス・マルケル
■撮影 ジェラール・ド・バティスタ/イブ・アンゲロ
■音楽 ミシェル・クラスナ
■出演 カトリーヌ・ベルコジャ
© 1996 Argos Films
【2019年7/7(日)・9(火)・11(木)上映】
マルケルは『サン・ソレイユ』以降沖縄に魅せられ、何度か現地に足を運んだ。その経験から生まれた本作では、ローラという女性が亡くなった恋人の代わりに沖縄についてのコンピューター・ゲームを完成させようとする姿が描かれており、コンピューターの空間に現れる記録映像と日本によって植民地化された沖縄の歴史、集団自決についての証言によって現実と仮想空間、歴史の「真実」と嘘、記憶と忘却といった問題が扱われる。映画史的記憶に満ちた内容である一方、非常に複雑なメディア性を持った作品。