

監督・脚本■ルイ・マル
1932年10月30日、フランス・テュムリー生まれ。父親はフランスでも有数の実業家で、裕福ではあったが厳格なカトリック家庭で育つ。
戦争の混乱期に少年時代を送り、14歳の頃から映画に傾倒。1950年に映画高等学院(IDHEC イデック)に入学。その後、1953年海洋学者ジャック=イヴ・クストーにカメラオペレーターとして雇われ3年にわたってカリプソ号に乗り組む。クストーはすぐに彼を格上げし、二人の共同監督作品『沈黙の世界』(56)はカンヌ国際映画祭パルム・ドール、米アカデミー賞最優秀長編ドキュメンタリー賞を受賞した。
弱冠25歳で完成させた初長編映画『死刑台のエレベーター』(57)は、マルの才気迸るサスペンス作品。舞台女優だったジャンヌ・モローを一躍国際的な映画スターにのしあげ、またマイルス・デイビスのオリジナル・スコアも伝説的だ。続く『恋人たち』(58)では再びJ・モローを起用し、映画のエロス表現のタブーを破り物議をかもし、世界的にも大ヒット。マル本人が個人的な映画と語り、最高傑作とも評される『鬼火』(63)は社会との断絶感を抱える青年の自殺に至る48時間を描き、ヴェネツィア映画祭審査員賞・イタリア批評家賞を受賞。ゲシュタポの手先となった17歳の少年を描いた『ルシアンの青春』(73)では英国アカデミー賞作品賞を受賞。
その後、米国にわたり、少女娼婦とカメラマンの愛を描き、美少女ブルック・シールズの名を轟かせた『プリティ・ベビー』(78)を監督。ヴェネツィア映画祭金獅子賞受賞『アトランティック・シティ』(80)では、スーザン・サランドンにアカデミー賞初ノミネーションをもたらした。
大2次世界大戦中、ドイツ軍のフランス占領当時、12歳のマルはカトリックの寄宿学校に在籍していた。その校長である神父がユダヤ人を校内にかくまっていると密告され、神父は逮捕。ユダヤ人少年らは強制収容所へ送られた。この体験を元に、10年ぶりにフランスに戻ったマルは1987年『さよなら子供たち』を発表。同作はヴェネツィア映画祭金獅子賞を受賞した。最期の作品は『42丁目のワーニャ』(94)。チェーホフの「ワーニャ伯父さん」のリハーサルを行う劇団員の姿を通して、人生と芸術の虚実皮膜を描き出した。
1995年がんのため死去。63歳だった。2度の離婚を経て女優・キャディス・バーゲンと結婚、生涯を共にした。ほかの主な作品に『私生活』『ビバ!マリア』『カルカッタ』『好奇心』『ブラック・ムーン』『五月のミル』など。また、デビュー以来、ドキュメンタリー制作を愛したマルは、最も誇りに思う作品としてドキュメンタリーシリーズ『インド幻想』を挙げている。
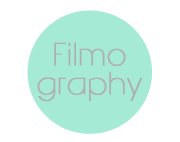
・沈黙の世界(56)監督
・死刑台のエレベーター(57)監督/脚本
・恋人たち(58)監督/脚本
・地下鉄のザジ(60)監督/脚本
・私生活(62)監督/脚本
・鬼火 (63)監督/脚本
・ビバ!マリア(65)監督/脚本/製作
・パリの大泥棒(66)監督/脚本
・テルレスの青春(66)製作
・世にも怪奇な物語(67)監督/脚本
・カルカッタ(69)<未>ナレーション/監督
・好奇心(71)監督/脚本
・ルシアンの青春(73)監督/脚本
・ブラック・ムーン(75)監督/脚本
・プリティ・ベビー(78)監督/原案/製作
・アトランティック・シティ(80)監督
・クラッカーズ/警報システムを突破せよ!(84)<未>監督
・アラモベイ(85)監督/製作
・しあわせを求めて(86)<TVM>監督
・さよなら子供たち(87)監督/脚本/製作
・五月のミル (89)監督/脚本
・ラヴィ・ド・ボエーム(92)出演
・ダメージ(92)(監督/製作)
・42丁目のワーニャ(94)監督
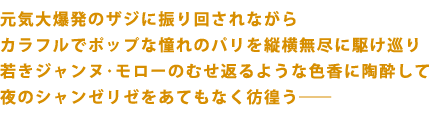
皆さまこんにちは、スタッフのザジです。
入社当時ザジ風ヘアーだった(恥)ことからこのあだ名がついて以来、いつか皆様にご紹介したいと心待ちにしていた作品が、ついに早稲田松竹に登場します。
そうです、今週はルイ・マル監督特集。
アバンギャルドな子ども映画の代表格『地下鉄のザジ』と、濃厚な大人のムード漂うサスペンス映画の金字塔『死刑台のエレベーター』の2本立てです。まったく異色な取り合わせですが、その幅広さもマルならでは。弱冠25歳で長編劇映画デビューを果たし、瞬く間に映画界で注目される存在となった才気煥発ぶりを感じていただけるはずです。もちろん、どちらも近年リバイバルした際の完全修復ニュープリント版でお届けいたします。時代を越えて人々に愛される名作を、是非スクリーンでご堪能ください。
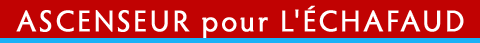
死刑台のエレベーター
(1957年 フランス 92分 ビスタ/MONO)
 2011年10月22日から10月28日まで上映
2011年10月22日から10月28日まで上映
■監督・脚本 ルイ・マル
■原作 ノエル・カレフ
■脚本 ロジェ・ニミエ
■撮影 アンリ・ドカエ
■音楽 マイルス・デイヴィス
■出演 モーリス・ロネ/ジャンヌ・モロー/ジョルジュ・プージュリイ/リノ・ヴァンチュラ/ヨリ・ベルタン/ジャン=クロード・ブリアリ/シャルル・デネ
![]()
 大企業で働くジュリアン(モーリス・ロネ)は、社長夫人のフロランス(ジャンヌ・モロー)と不倫関係にあった。2人は自殺に見せかけて社長の殺害を画策し、ジュリアンはついに実行に移す。完全犯罪を成し遂げたかに思えたが、証拠隠滅のため再び犯行現場に戻る途中のエレベーターに運悪く閉じ込められてしまう。一方、ジュリアンの車を盗んで街に繰り出した若いカップルも殺人を犯してしまい…。
大企業で働くジュリアン(モーリス・ロネ)は、社長夫人のフロランス(ジャンヌ・モロー)と不倫関係にあった。2人は自殺に見せかけて社長の殺害を画策し、ジュリアンはついに実行に移す。完全犯罪を成し遂げたかに思えたが、証拠隠滅のため再び犯行現場に戻る途中のエレベーターに運悪く閉じ込められてしまう。一方、ジュリアンの車を盗んで街に繰り出した若いカップルも殺人を犯してしまい…。
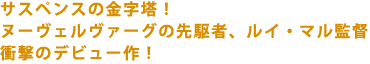
 「ジュ・テーム」…モノクロームに揺らめくフロランスの顔のアップから始まる『死刑台のエレベーター』。本作で大女優への道を切り開いたジャンヌ・モローの甘く狂おしい愛の囁き、スクリーンに堂々と映える美貌にいきなり目が釘付けになってしまいます。制作当時、ルイ・マルは25歳。長編単独監督デビュー作でありながら批評家から絶賛され、その年の最も優れたフランス映画に贈られるルイ・デリュック賞を受賞。文字通り衝撃的なデビューを飾りました。
「ジュ・テーム」…モノクロームに揺らめくフロランスの顔のアップから始まる『死刑台のエレベーター』。本作で大女優への道を切り開いたジャンヌ・モローの甘く狂おしい愛の囁き、スクリーンに堂々と映える美貌にいきなり目が釘付けになってしまいます。制作当時、ルイ・マルは25歳。長編単独監督デビュー作でありながら批評家から絶賛され、その年の最も優れたフランス映画に贈られるルイ・デリュック賞を受賞。文字通り衝撃的なデビューを飾りました。
エレベーターという閉鎖空間に閉じ込められたジュリアンの、焦燥感と恐怖に押しつぶされそうな孤独で長い長い夜。待ち合わせの時間になっても現れないジュリアンを想い、途方に暮れて夜のパリを雨に濡れて彷徨い歩くフロランスの淀んだ夜。ジュリアンの車を盗み、やがて予期せぬ殺人を犯してしまう若きカップルの暴走する夜。三つの夜がやがて一つに繋がる時、事件は冷たい美しさを湛えたまま終焉を迎えます。
 原作はノエル・カレフのサスペンス小説。撮影は『大人は判ってくれない』『太陽がいっぱい』のアンリ・ドカエ。そして忘れてはならないのが、“モダンジャズの帝王”と称されるマイルス・デイビスによる音楽。ラッシュ(編集前のフィルム)を流しながら即興セッションで仕上げた演奏は、まるでパリの夜に絡みつくようにして、作品に一層の深淵さと鋭さを与えています。IMDb(インターネット・ムービー・データベース)によると、この録音にはマルとモローも同席し、シャンパンを啜りながら行われたそう。劇中、フロランスが若いカップルを「本当に子供ね!」と叱責するシーンがありますが、そんな子供とたいして歳の違わなかったマル。作品のみならず舞台裏までムードたっぷりだったとは、なんと空恐ろしい25歳だったのでしょう(25歳というと私と同い年なのですが、あまりに洗練された大人っぽさに(勝手に)完敗した気分です)。
原作はノエル・カレフのサスペンス小説。撮影は『大人は判ってくれない』『太陽がいっぱい』のアンリ・ドカエ。そして忘れてはならないのが、“モダンジャズの帝王”と称されるマイルス・デイビスによる音楽。ラッシュ(編集前のフィルム)を流しながら即興セッションで仕上げた演奏は、まるでパリの夜に絡みつくようにして、作品に一層の深淵さと鋭さを与えています。IMDb(インターネット・ムービー・データベース)によると、この録音にはマルとモローも同席し、シャンパンを啜りながら行われたそう。劇中、フロランスが若いカップルを「本当に子供ね!」と叱責するシーンがありますが、そんな子供とたいして歳の違わなかったマル。作品のみならず舞台裏までムードたっぷりだったとは、なんと空恐ろしい25歳だったのでしょう(25歳というと私と同い年なのですが、あまりに洗練された大人っぽさに(勝手に)完敗した気分です)。

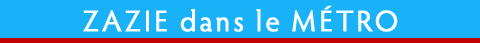
地下鉄のザジ
(1960年 フランス 93分 スタンダード/MONO)
 2011年10月22日から10月28日まで上映
2011年10月22日から10月28日まで上映
■監督・脚本 ルイ・マル
■原作 レイモン・クノー
■脚本 ジャン=ポール・ラプノー
■撮影 アンリ・レイシ
■美術顧問 ウィリアム・クライン
■音楽 フィオレンツォ・カルピ
■出演 カトリーヌ・ドモンジョ/フィリップ・ノワレ/カルラ・マルリエ/ユベール・デシャン/ヴィットリオ・カプリオーリ
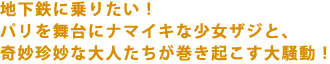
 PARIS! 凱旋門に、エッフェル塔。カフェオレに、クロワッサン…。お愉しみはいろいろあれど、田舎からやってきた少女ザジ(カトリーヌ・ドモンジョ)の一番の目的はMETRO!地下鉄に乗ること。しかし残念なことに、地下鉄はストの真っ最中。仕方なくパリ見学に出かけたザジの行く先々では、奇妙珍妙な大人たちが現れて、ハチャメチャな騒動が巻き起こる。やがて夜になり、疲れ切ったザジが居眠りをしている間にストが解除され、地下鉄が動き出すが…。
PARIS! 凱旋門に、エッフェル塔。カフェオレに、クロワッサン…。お愉しみはいろいろあれど、田舎からやってきた少女ザジ(カトリーヌ・ドモンジョ)の一番の目的はMETRO!地下鉄に乗ること。しかし残念なことに、地下鉄はストの真っ最中。仕方なくパリ見学に出かけたザジの行く先々では、奇妙珍妙な大人たちが現れて、ハチャメチャな騒動が巻き起こる。やがて夜になり、疲れ切ったザジが居眠りをしている間にストが解除され、地下鉄が動き出すが…。
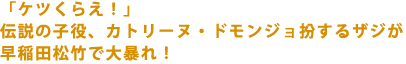
 『死刑台のエレベーター』から3年後、ルイ・マルは今もなおカルト的人気を誇るスラップスティック・コメディ『地下鉄のザジ』を監督しました。「この3年で一体何があったんだ!」とあるスタッフが言っていましたが(笑)、確かにその通りで、初めてご覧になる方はびっくりしてしまうかも。それくらい『死刑台のエレベーター』とは正反対で、少しもじっとしていないやんちゃな子供そのもの、のような映画なんです。
『死刑台のエレベーター』から3年後、ルイ・マルは今もなおカルト的人気を誇るスラップスティック・コメディ『地下鉄のザジ』を監督しました。「この3年で一体何があったんだ!」とあるスタッフが言っていましたが(笑)、確かにその通りで、初めてご覧になる方はびっくりしてしまうかも。それくらい『死刑台のエレベーター』とは正反対で、少しもじっとしていないやんちゃな子供そのもの、のような映画なんです。
原作は、当時ベストセラーだったレーモン・クノーの同名小説。言葉遊びと文学的技巧に富み、映像化不可能といわれたこの小説は、マルの小粋な(かつこれでもか!というくらいの)演出によって見事なトランスフォームを遂げています。ホームに滑りこんだ列車から飛びだし、恋人の腕に抱かれクルクルとまわる母親、いつまでもまわる母親、クルクルクルクル…まだまわるんかい!と思わずツッコミたくなるくらい、冒頭からパワー全開。
通常1秒24コマであるところを1秒8コマないし12コマで撮影したカクカク映像に、1カットごとに立ち位置の変わる登場人物、さっきまでパジャマだったのに次の瞬間服を着ているザジ…など、マルが随所に仕掛けた映像のトリックがなだれ込むように観客を巻き込んでいきます。もちろん、原作の醍醐味である言葉遊びにも要注目。ナンセンスでおかしみの利いた会話は機関銃のごとく止まるところを知りません。
同時代の映画監督フランソワ・トリュフォーは、本作を絶賛しマルに長い手紙を書いたといいます。とんでもなく強烈なのに、なんだか病みつきになる。気づいた時にはもう…大好き!そんな不思議な魅力を、是非劇場で確かめてみてください。
それでは皆さま、早稲田松竹でお会いしましょう!
(デザイン・文 ザジ)
