
カトリックの児童養護施設で里親に引き取られていく『冬の小鳥』の9歳のジニや他の少女たちの姿は、
彼女たち一人一人の人生というよりは、むしろよく口ずさまれて、世界中で聴かれる悲しい唄のよう。
悲嘆にくれて絶望して、なお裏切られていく彼女たちは声も出さずに尋ねている。
「なぜ、わたしはここにいるのか」「どうして誰も迎えに来てくれないのか」
薬物中毒によるメタドン治療をうけている『ソフィアの夜明け』の38歳のイツォにとっては、
残された人生はもはや期待のかけられるものではなかったかもしれない。
この映画が始まったときには、すでに彼は人生の終局を迎えた老人のようだ。
17歳の弟・イオルギがスキンヘッドで彼の前に現れたときに彼は驚いた。
アーティスト(木工技師)としての自分に憧れて、弟が自分と同じように人生を投げやりにするなんて。
しかし今、自分は一体どこにいるのだろう?治療に苦しむ肉体を引きずりながら、イツォは自問する。
そんなイツォに、弟が襲ったトルコ人の家族の娘ウシュルは若者らしい興奮をもってこう言う。
「今、世界は揺れ動き、すべては暴走してる」
これらの映画で描かれる人間の純粋で孤独な姿が強度を増していくごとに、
一方では反抗的なたくましさを育てていく姿が、
あるいはあの「大人は判ってくれない」のアントワーヌ・ドワネルや、「ポネット」の少女と同じように胸を打つのは、なぜだろう?
忘れ難い少年少女時代、不可解な現実に触れた最初の記憶を、皆が胸の奥に抱えているからだろうか。
それとも、もうすでに私たちがその柔軟な抵抗の感触を忘れてしまったからだろうか?
ジニが待ち続けた父が迎えに来ないことを知った後、死んだ小鳥を埋めた庭の片隅を掘り返したとき、そこにはもう何もなかった。
それを見た時に彼女は何を想像したのだろうか?
イツォが、夜明け頃のブルガリアの首都ソフィアの街を彷徨いながら見た、老人や赤子の姿は?
そういうものに触れたときに、私はゾクゾクしてしまう。その悲しさのあまりなのか、過酷さのためなのかはわからない。
それでも、ジニがキリスト教のパブテスマ(洗礼)のように土の下に潜り(この小庭は彼女の墓地であると同時に誕生の地でもある!)、
幾世代、幾人の感情が複雑に絡まった人種差別問題や自らの過去の病が、イツォの肉体を縛りつけて苦しめても、
なお彼らが再び動き始めたのは、新しい感情に出会ったからではなかったのか。
映画を観終わったとき、この旅がまだ終わらないことを私たちは知っている。
しかしそれを苦しいと思うだろうか?それとも、映画を見たあとにはこう思うのだろうか。
「また、出発だ。」
(ぽっけ)
ソフィアの夜明け
EASTERN PLAYS
(2009年 ブルガリア 89分 ビスタ/SRD)
 2011年5月14日から5月20日まで上映
■監督・製作・脚本・編集 カメン・カレフ
2011年5月14日から5月20日まで上映
■監督・製作・脚本・編集 カメン・カレフ
■撮影 ユリアン・アタナソフ
■音楽 ジャン=ポール・ウォール
■出演 フリスト・フリストフ/オヴァネス・ドゥロシャン/サーデット・ウシュル・アクソイ/ニコリナ・ヤンチェヴァ/ハティジェ・アスラン
■東京国際映画祭東京サクラグランプリ・最優秀監督賞・最優秀男優賞
![]()
ゲオルギは17歳。絶えず両親ともめていた。もっと男らしく見られたいと彼はスキンヘッドのギャングに加わる。彼は兄イツォとしばらく会っていなかった。
 兄イツォは38歳。職業は木工技師だ。彼はドラッグ中毒でメタドンの治療を受けていた。ヘロイン中毒のせいで生きることに投げやりな彼はアルコールに頼る日々を送っていた。
兄イツォは38歳。職業は木工技師だ。彼はドラッグ中毒でメタドンの治療を受けていた。ヘロイン中毒のせいで生きることに投げやりな彼はアルコールに頼る日々を送っていた。
ウシュルは20代の女性でイスタンブール出身のトルコ人。ウシュルと両親は彼女の兄を訪ねベルリンに向かう途中だ。ブルガリアを横断する長いドライブの後、一家は途中休憩し、ソフィアで一夜を過ごすことになる。だが、その夜は悪夢となった。一家はゲオルギを含むスキンヘッドのギャングによる暴行の犠牲となる。偶然現場に居合わせたイツォは、トルコ人一家を守ろうとするが…。
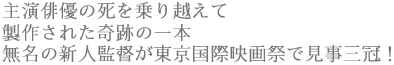
一昨年の東京国際映画祭で審査委員長のアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ(『アモーレス・ペロス』監督)が激賞、無名の新人監督が大旋風を巻き起こし、満場一致でグランプリを含むトリプル受賞という快挙を成し遂げた。
年間製作本数わずか7・8本と言われるブルガリアから登場したカメン・カレフ監督は、東欧映画期待の新鋭。フランスの国立映画学校を卒業後、久しぶりに出会った幼友達フリスト(主演・イツォ役)との交流を通し、彼の破天荒な生き方を主人公のモデルにした本作の製作に取り掛かった。
現代のブルガリアを舞台に、孤独に生きる芸術家イツォが、ある事件をきっかけに希望を掴み取ろうとする物語は私たちに生きる意味を問いかけ、叙情的で美しい映像は見る者の魂を覚醒させる。センセーショナルな俳優デビューを飾ったフリスト・フリストフが撮影終了間際に不慮の事故で他界するという悲劇を乗り越えて完成した本作。格差社会の底辺で必死に生きる人間たちの憤りや焦りをリアルでビターな味わいで描いた、青春映画の傑作!


冬の小鳥
A BRAND NEW LIFE
(2009年 韓国/フランス 92分  ビスタ/SRD)
ビスタ/SRD)
 2011年5月14日から5月20日まで上映
■監督 ウニー・ルコント
2011年5月14日から5月20日まで上映
■監督 ウニー・ルコント
■製作 イ・チャンドン/ロラン・ラヴォレ/イ・ジュンドン
■出演 キム・セロン/パク・ドヨン/コ・アソン/パク・ミョンシン/ソル・ギョング/ムン・ソングン
■東京国際映画祭アジアの風部門最優秀アジア映画賞/ソウル国際女性映画祭第1回アジア女性映画祭ネットワーク賞
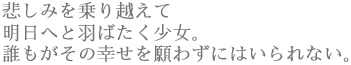
 1975年。新調してもらったよそ行きの洋服を着て、9歳のジニは大好きな父に連れられソウル郊外にやってくる。高い鉄格子の門の中では、庭で幼い子供たちが遊んでいる。ジニは父親と離され子供たちがいる部屋に通されるが、状況が分からず思わず外に飛び出してしまう。目に入ってきたのは、門のむこうに去る父の背中。そこは、孤児が集まるカトリックの児童養護施設だった。
1975年。新調してもらったよそ行きの洋服を着て、9歳のジニは大好きな父に連れられソウル郊外にやってくる。高い鉄格子の門の中では、庭で幼い子供たちが遊んでいる。ジニは父親と離され子供たちがいる部屋に通されるが、状況が分からず思わず外に飛び出してしまう。目に入ってきたのは、門のむこうに去る父の背中。そこは、孤児が集まるカトリックの児童養護施設だった。
自分は孤児ではないと主張するジニは、父に連絡を取るよう院長に頼む。出された食事にも手をつけず、反発を繰り返すジニ。ついには脱走を試みるが、門の外へ足を踏み出しても途方にくれてしまうのだった。
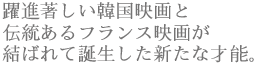
 実際に韓国から養子としてフランスに渡ったウニー・ルコント監督の実体験から生まれた本作。バタークリームのケーキ、おかっぱ頭にアップリケのついたセーター、1975年の生活描写は、昭和の風景にも似て懐かしい。「ほとんどの部分は創作だが、9歳だったときの心のままに書いた」と監督が語る通り、ジニをとおしてスクリーンに焼き付ける感情は、嘘偽りのないものだ。だからこそ映画は強烈な説得力をもって、観る者を深く感動させる。
実際に韓国から養子としてフランスに渡ったウニー・ルコント監督の実体験から生まれた本作。バタークリームのケーキ、おかっぱ頭にアップリケのついたセーター、1975年の生活描写は、昭和の風景にも似て懐かしい。「ほとんどの部分は創作だが、9歳だったときの心のままに書いた」と監督が語る通り、ジニをとおしてスクリーンに焼き付ける感情は、嘘偽りのないものだ。だからこそ映画は強烈な説得力をもって、観る者を深く感動させる。
脚本を読んだイ・チャンドン(『オアシス』監督)は、"シンプルだが沢山の要素が詰まっている"と評し、本作のプロデュースを買って出る。そして、2006年にフランスと韓国で結ばれた<映画共同製作協定>の第1号作品として本作は完成した。映画誌カイエ・デュ・シネマでは、ポン・ジュノ(『母なる証明』監督)が本作を2000年代最高の映画の1本に選出。2009年東京国際映画祭ではアジアの風部門最優秀アジア映画賞を、2010年ソウル国際女性映画祭では第1回アジア女性映画祭ネットワーク賞を受賞した。ウニー・ルコント監督は、今後が期待される監督のひとりである。
