
テロリストから英雄になった南アフリカ共和国大統領ネルソン・マンデラ。
そして、英雄兼独裁者になったドイツ労働者党首相アドルフ・ヒトラー。
アパルトヘイト/ユダヤ人迫害
国民に熱狂的に支持されていたこの二人が
なぜ差別を無くそうとする政治家と、差別を促進する政治家だったのでしょうか?
残された人物伝なんかは、装飾がはりついてなんかウソっぽい。
その人間のまわりにもっとスポットライトを当ててみましょう。
彼らを取り巻く環境。
受けた教育。
友人。
恋人。
その中の誰か一人欠けたら、彼らは歴史に名を現していなかったかもしれない。
英雄でも独裁者でも、我々と同じ。影響しあって存在する。
今週は政治家と、それを見つめて支える友人の「ふたりぼっち」映画2本立てです。

マンデラの名もなき看守
GOODBYE BAFANA
(2007年 フランス・ドイツ・ベルギー・イタリア・南アフリカ 117分 シネスコ・SRD)
 2009年5月23日から5月29日まで上映
2009年5月23日から5月29日まで上映
■監督・脚本 ビレ・アウグスト
■脚本 グレッグ・ラッター
■出演 ジョセフ・ファインズ/デニス・ヘイスバート/ダイアン・クルーガー/パトリック・リスター
■オフィシャルサイト http://mandela.gyao.jp/
![]()
1968年―─パリ、五月革命。チェコスロヴァキア、プラハの春。日本、東大闘争。世界が不透明な欺瞞の包囲網から抜け出そうと革命闘争を繰り広げている頃。南アフリカもまた長い夜の夜明けを待っているところだった。
アパルトヘイト政策下―─黒人を下等な人間とみなすことはまだ当たり前の時。 人種差別主義者であったジェームス・グレゴリー(ジョセフ・ファインズ)は、国内一の刑務所と名高いロベン島に赴任し、最悪のテロリスト、反政府運動の首謀者と言われるネルソン・マンデラ (デニス・ヘイバート)の担当となる。マンデラの生まれ故郷の近くで育ったグレゴリーは、彼らの 言葉であるコーサ語が分かるというので、秘密の会話をスパイしろと言うのだ。
 任務に忠実であったグレゴリーだが、塀の中でも深い人間愛と知性を持ち、信念を貫く
マンデラという人物に魅了され、彼の描く平等な世界に憧れを抱いていく・・・
任務に忠実であったグレゴリーだが、塀の中でも深い人間愛と知性を持ち、信念を貫く
マンデラという人物に魅了され、彼の描く平等な世界に憧れを抱いていく・・・
「こんな汚れた現実に従うことはできない」
しかしそんな想いが周囲に知られれば、自分の立場も妻子の安全さえも脅かされる。国家、家族、理想、現実、良心。数々の想いに裂かれながら、グレゴリーの選ぶ道とは?
![]()
 監督は「ペレ」「愛の風景」のそれぞれでカンヌのパルムドールを二度も受賞したビレ・アウグスト。07年カンヌ60周年記念「それぞれのシネマ」でも監督(作品「最後のデート・ショウ」)に選ばれた彼は、常に徹底して自由と差別の問題についての作品を撮り続ける。「映画の境界線を越える力」と「人間は変わることができる」という可能性に賭け続ける彼の作品は今回ネルソン・マンデラの題材を得てさらに強く輝くこと間違いなし。
監督は「ペレ」「愛の風景」のそれぞれでカンヌのパルムドールを二度も受賞したビレ・アウグスト。07年カンヌ60周年記念「それぞれのシネマ」でも監督(作品「最後のデート・ショウ」)に選ばれた彼は、常に徹底して自由と差別の問題についての作品を撮り続ける。「映画の境界線を越える力」と「人間は変わることができる」という可能性に賭け続ける彼の作品は今回ネルソン・マンデラの題材を得てさらに強く輝くこと間違いなし。
ネルソン・マンデラは良い人過ぎる、と監督は言う。いい人過ぎては映画の題材にならない、とも。ネルソン・マンデラは不屈の精神で人間を信じて、そこから一歩も動かない。彼には迷いがないのだ。でも、今回のように看守の側からネルソン・マンデラを描くことによって監督は映画になる確信を得たという。グレゴリーは白人で、マンデラは黒人。看守と囚人。この対立構造はまさにアパルトヘイト政策下の白人と黒人の立場。グレゴリーとマンデラの間にあるのは一つ檻という見えない境界線なのだ。
グレゴリーの葛藤は、「なぜ自分には境界線が見えるのだろうか」という悩み。肌の色の違いは目に見える。しかし、この当時の状況下の白人に「差別」は見えるものではなかった。それが「見えてしまう」という葛藤。これがビレ・アウグストが、グレゴリーを映画の題材に選ぶ理由だと思う。
 「肌の色や生まれ育ち、宗教などを理由に生まれつき他者を憎むものなどいない。人は憎しみを学ぶのだ。」著書『自由への道のり』でネルソン・マンデラはこう語る。
「肌の色や生まれ育ち、宗教などを理由に生まれつき他者を憎むものなどいない。人は憎しみを学ぶのだ。」著書『自由への道のり』でネルソン・マンデラはこう語る。
身についたことを忘れることは容易ではない。だからこそ生まれる負の連鎖を断ち切ろう。
まず忍耐強く牢屋の中に座るマンデラの姿を、グレゴリーと一緒に檻の外から眺めましょう。いつしか、檻に入っているのはわれわれなのかもしれないと思い始める。なにしろ私たちの間には鉄格子が1つ。


わが教え子、ヒトラー
MEIN FUHRER
(2007年 ドイツ 95分 ビスタ・SRD)
 2009年5月23日から5月29日まで上映
2009年5月23日から5月29日まで上映
■監督・脚本 ダニー・レヴィ
■出演 ウルリッヒ・ミューエ/ヘルゲ・シュナイダー/ジルヴェスター・グロート/アドリアーナ・アルタラス/シュテファン・クルト/ウルリッヒ・ナーテン
■2007年サンフランシスコ・ユダヤ映画祭表現の自由賞/2008年ドイツ批評家協会賞最優秀男優賞(ウルリッヒ・ネーテン)
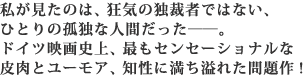
1944年12月25日第二次世界大戦終戦も近づいた頃、ナチス・ドイツは連合国との戦いに相次いで敗れ、完全な劣勢に陥っていた。ここで打開案として、宣伝大臣ゲッベルスは1945年1月1日ベルリンにて100万人の市民を前にヒトラー総統(ヘルゲ・シュナイダー)の雄々しいスピーチを撮影し、それをプロバガンダ映画に仕立て国民の戦意を高揚させる計画を立てる。
しかし、肝心のヒトラーは心身を病んで自信喪失。スピーチなどできる状態ではない。そこで5日間でヒトラーを再生させるための教師として選ばれたのが、世界的ユダヤ人俳優「演説の天才」と称されるアドルフ・グリュンバウム(ウルリッヒ・ミューエ)だった。ヒトラーと同じ「アドルフ」の名前を持ち、ユダヤ人であるグリュンバウムは収容所に残された家族と一緒に暮らせることを条件にこの任務を引き受けるが、これは多くの同胞の命を奪ったヒトラーを暗殺するのに絶好の機会である。しかし、演説指導をするうちにグリュンバウムはヒトラーの孤独な一面に触れて、手を出すのをためらい始める。
 ヒトラーもまた、グリュンバウムのユーモラスな演説指導に触れて、心を開きはじめる。そして二人の間にはいつしか友情にも似た感情が芽生え始めたのだった。同胞ユダヤの仇を討つべきか、愛する家族を収容所から救い出して生き残るべきか。葛藤するグリュンバウムは演説当日ヒトラーでさえも思いもよらない行動に出る。
ヒトラーもまた、グリュンバウムのユーモラスな演説指導に触れて、心を開きはじめる。そして二人の間にはいつしか友情にも似た感情が芽生え始めたのだった。同胞ユダヤの仇を討つべきか、愛する家族を収容所から救い出して生き残るべきか。葛藤するグリュンバウムは演説当日ヒトラーでさえも思いもよらない行動に出る。
![]()
アドルフ・ヒトラーについての映画は非常に多い。ヒトラーが映画をプロパガンダに有効利用した点も、もしかしたら関係あるかもしれない。しかも何故だろう。チャップリンの「独裁者」の影響なのか、彼はコメディの題材でよく使われる。モンティ・パイソンしかり今回の「我が教え子、ヒトラー」でも、ヒトラーを演じるのは有名なコメディアンのヘルゲ・シュナイダーだ。面白い。ヒトラーを笑え、と?
 ヒトラーという人物を映画で使うことについて、アレクサンドル・ソクーロフが「モレク神」を撮った時に言ったのは「ヒトラーを徹底的に“ひとりの男”に引きずり降ろさなければ、歴史の悪循環は断ち切れない」という言葉。もしかしたらこの作品もその意志を継いでいるのかもしれない。
ヒトラーという人物を映画で使うことについて、アレクサンドル・ソクーロフが「モレク神」を撮った時に言ったのは「ヒトラーを徹底的に“ひとりの男”に引きずり降ろさなければ、歴史の悪循環は断ち切れない」という言葉。もしかしたらこの作品もその意志を継いでいるのかもしれない。
ヒトラーをただ憎み人類の歴史から抹殺するならばそれもいいだろうと思う。悪夢をいつまでも反芻する必要はない。しかし、憎しみで恐怖を抹殺することができただろうか?消えるのは肉体だけで、恐怖は消えない。
例えば、「ヒトラーはまだ生きている」という噂が流れるたびにスターリンが裏庭に埋めたヒトラーの骨を掘り出して安心していたなんていうジョークまである。
ヒトラーは怪物ではない。我々と同じ人間で、同じように考えることができるはずなのに虐殺が起きるから恐ろしいのだ。
さて、この作品の内容はもちろんフィクションです。これは監督のダニー・レヴィも公言している。史実に基づいたフィクションではなく、フィクションを礎に人間的な真実を描こうという試み。だから、「ハイル、ヒトラー」がこんなに滑稽に響く映画は他にはないし、ヒトラーがこんなに繊細に見える映画も他にはない。嘘とホントがひっくり返ったのか、それともこれがホントなのか。
私にはわかりません。それを判断するのはあなた自身!!
最後に。本作が遺作となった『善き人のためのソナタ』のウルリッヒ・ミューエの冥福を祈ります。彼の静かに燃える知性が今この作品を何段階も深く、味のあるものにしています。ぜひご覧下さい。
(ぽっけ)
