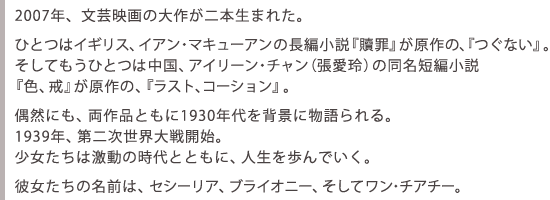つぐない
ATONEMENT
(2007年 イギリス 123分)![]()
2008年9月27日から10月3日まで上映
■監督 ジョー・ライト
■原作 イアン・マキューアン『贖罪』
■脚本 クリストファー・ハンプトン
■出演 キーラ・ナイトレイ/ジェームズ・マカヴォイ/シアーシャ・ローナン/ロモーラ・ガライ/ヴァネッサ・レッドグレーヴ/ブレンダ・ブレシン/アンソニー・ミンゲラ
1935年、戦火が忍び寄るイギリス。夏のある日、政府官僚の長女に生まれたセシーリアは、兄弟のように育てられた使用人の息子、ロビーを愛しているのだと気付く。しかし生まれたばかりの二人の愛は、小説家を目指す妹、ブライオニーのついた哀しい嘘によって引き裂かれることになる。
4年後、ロビーは戦場の最前線に送り出される。彼の帰りをひさすら待ち、手紙をしたため続けるセシーリア。ブライオニーは自分が犯した罪の重さを思い知らされる。
セシーリアとロビーは再び会うことができるのか。
ブライオニーが罪を贖える日はやっていくるのか。
原作は、イギリス本国のみならず現代文学を代表するブッカー賞作家イアン・マキューアンの『贖罪』(新潮社刊)。2002年に出版され、イギリス本国では150万部の大ベストセラーとなった。脚本化するにあたり、13万語におよぶ大作を2万語に脚色し直したという。監督のジョー・ライトはデビュー作『プライドと偏見』のスタッフを再び集結させ、綿密な準備を経て完璧な作品を作り上げた。
セシーリアを演じたキーラ・ナイトレイの美しさもさることながら、ブライオニーの少女時代を演じたシアーシャ・ローナンの持つ魅力は唯一無二のもの。少女の持つ、残酷なまでの無垢さ。しかしそれが事件を引き起こすもととなってしまう…
『つぐない』は、ブライオニーの物語。彼女の苦悩、驚きや歓び、哀しみ。

ラスト、コーション
色┃戒 / LUST, CAUTION
(2007年 アメリカ/中国/台湾/香港 158分) ![]()
 2008年9月27日から10月3日まで上映
■監督 アン・リー
2008年9月27日から10月3日まで上映
■監督 アン・リー
■脚本 ワン・フイリン/ジェームズ・シェイマス
■出演 トニー・レオン/タン・ウェイ/ワン・リーホン/ジョアン・チェン/トゥオ・ツォンホァ
「中国語で“Lust”は仏教用語の“欲情”を意味し
“Caution”は“戒め”を意味する。
“色”は“人生”そのもの。
人間が生きていく上で不可欠な“感情”を著しています。
また、“戒”は指輪のことを中国語で“指戒”と表現するように、
“誓い”の意味があるのです。」
―――アン・リー
1938年、中国。女子学生のワン・チアチーは、日本軍による侵攻から逃れ、本土から香港に集団移住して来た。香港大学に転入したワンは、親友に誘われて演劇部に入部する。そこで出会った、レジスタンス派の学生で強い信念と志を持つクァン・ユイミンに、ワンは淡い思慕を寄せる。演劇部の看板女優となったワンは、クァンに導かれるまま愛国思想に傾倒していく。
 4年後の1942年、日本占領下の上海。抗日運動に身を投じる女スパイになったワンは、敵対する特殊機関の顔役、イーを暗殺するため彼に近付き機会を狙っていた。
4年後の1942年、日本占領下の上海。抗日運動に身を投じる女スパイになったワンは、敵対する特殊機関の顔役、イーを暗殺するため彼に近付き機会を狙っていた。
危険な逢瀬を重ねるうちに、ワンはいつしかイーに惹かれ始める。そしてイーもまた、ワンの不思議な魅力の前に素顔を見せるようになる。
痛々しいほど、暴力的なまでに激しくお互いを求め合うふたり。自分以外を信じることができないふたりが心を通い合わせることのできる方法は、言葉ではなかった。逢瀬を重ねれば重ねるほど、想いは高みへ上っていく。そして、イーを暗殺する使命を持ったワンが選んだ結末は…
原作はアイリーン・チャン(張愛玲)の同名短編小説(原題「色、戒」)。中国では「張迷」という言葉があり、張愛玲の熱烈なファンのことをそう呼ぶという。
 ワン・チアチーは実在した女スパイ、鄭蘋如(テイ・ピンルー)がモデルとされており、イーもまた実在した人物である丁黙邨(テイ・モクソン)がモデルとされている。
ワン・チアチーは実在した女スパイ、鄭蘋如(テイ・ピンルー)がモデルとされており、イーもまた実在した人物である丁黙邨(テイ・モクソン)がモデルとされている。
過激なセックスシーンが話題となった本作。ポルノ映画のようだという声も聞こえなくは無い。
だけれど、私は疑問に思う。なぜ映画では、セックスシーンが省かれてしまうのか。ことの始まりや終わりで済ますのか。セックスというものはあまりにもプライヴェートなもので、そんな“恥ずかしい”ことをスクリーンにさらすのは慎みに欠けるとでも言うのだろうか。
もちろん、セックスが愛の全てではない。その場面を用いずとも、素晴らしい映画はたくさん存在している。でも。指と指の隙間からこぼれ落ちてしまう時間の一片を、フレームから外されてしまう感情の波を、セックスのなかにだけある対話を、汲み取って欲しいと思うのだ。そういう意味で、『ラスト、コーション』は今まで省かれていた感情の対話を映し出していると言える。
(sone)