
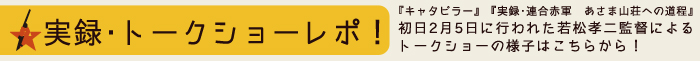

監督■若松孝二
1936年、宮城県生まれ。
高校時代、停学処分を3回受け、54年に退学。家出して上京し、お菓子屋の小僧や日雇い労働などの職を転々とし、ヤクザの世界へ。この極道時代に新宿で映画の撮影現場の用心棒をしたことがきっかけで、半年間の拘留所暮らしの後、足を洗って映像の世界へ。
63年、『甘い罠』で監督デビュー。低予算ながらも圧倒的な迫力のある映像でピンク映画としては異例の集客力をみせた。その後も、「ピンク映画の黒澤明」などと形容されヒット作を量産。
65年に若松プロを設立し、『壁の中の秘事』がベルリン国際映画祭に出品され、国辱映画として騒がれる。71年、パレスチナゲリラの闘争を描いた『赤軍―PFLP 世界戦争宣言』を発表。『胎児が密猟するとき』『天使の恍惚』『水のないプール』『17歳の風景』などの話題作を次々世に送り出す。『戒厳令の夜』『愛のコリーダ』などプロデュース作品も多い。
『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』は、第58回ベルリン国際映画祭最優秀アジア映画賞(NETPAC賞)、および同映画祭の国際芸術映画評論連盟賞(CICAE賞)を受賞。『キャタピラー』では第60回ベルリン国際映画祭銀熊賞(最優秀主演女優賞)を受賞した。
![]()
■主な監督作品
・甘い罠(1963)監督
・鉛の墓標(1964)監督
・情事の履歴書(1965)監督
・壁の中の秘事(1965)監督
・血は太陽よりも赤い(1966)演出/監督
・ひき裂かれた情事(1966)監督/企画/脚本
・胎児が密猟する時(1966)監督
・情欲の黒水仙(1967)監督
・犯された白衣(1967)監督/脚本
・性の放浪(1967)監督
・金瓶梅(1968)監督
・裸の銃弾(1969)監督/企画/製作
・新日本暴行暗黒史 復讐鬼(1969)監督
・狂走情死考(1969)監督
・処女ゲバゲバ(1969)監督
・ゆけゆけ二度目の処女(1969)監督
・現代好色伝 テロルの季節(1969)監督
・狂走情死考(1969)監督
・復讐鬼(1969)監督/企画/制作
・新宿マッド(1970)監督
・性賊 セックス・ジャック いろはにほてと(1970)監督
・性輪廻(セグラマグラ) 死にたい女(1971)監督
・秘花(1971)監督
・赤軍派-PFLP 世界戦争宣言(1971)監督
・天使の恍惚(1972)監督/企画/製作
・濡れた賽ノ目(1974)監督
・聖母観音大菩薩(1977)監督/企画
・餌食(1979)監督
・水のないプール(1982)監督/製作
・キスより簡単(1989)監督
・われに撃つ用意あり READY TO SHOOT (1990)監督/企画/製作
・エロティックな関係(1992)監督
・寝盗られ宗介(1992)プロデューサー/監督
・シンガポール・スリング(1993)監督/脚本
・Endress Waltz エンドレス・ワルツ(1995)監督/企画
・明日なき街角(1997)監督
・飛ぶは天国、もぐるが地獄(1999)監督
・完全なる飼育 赤い殺意(2004)監督
・17歳の風景 少年は何を見たのか(2005)監督
・実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(みち)(2007)監督/企画/脚本/製作
・キャタピラー(2010)監督
★プロデュース作品
・堕胎(足立正生監督/1966)制作
・裏切りの季節(大和屋竺監督/1966)製作
・毛の生えた拳銃(大和屋竺監督/1968)企画/製作
・愛のコリーダ(大島渚監督/1976)製作
・戒厳令の夜( 山下耕作監督/1980)製作
・赤い帽子の女(神代辰巳監督/1982)プロデューサー
ほか監督・出演作など多数
極私的若松孝二。
今から12年前、BOX東中野という映画館で『映画梁山泊 若松プロダクションの軌跡』という特集上映があった。当時、私は10代の終わりで学校に行けず満足に働くこともできず、時間だけは余っていたので、映画館でよく暇つぶしをしていた。そこに扇情的な言葉で埋められた真っ赤なチラシが置いてあった。それが若松孝二との出会いだ。
ひたすら内に秘めた怒りを爆発させたかのようなエネルギー溢れる映画群。それは私の知っている映画とは全く違うものだった。常識では忌避されるような過激な表現。その見てはいけない映像は、見事に私の心に抱えていた闇と結びついた。描かれているのはほとんどが社会から疎外された人間たち。暗闇のスクリーンから、刹那にしか生きられない彼らの命が鮮烈に浮かび上がった。私が初めて“詩”を意識したのは文学ではない。若松孝二の映画からだ。
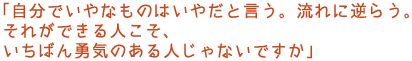
若松孝二の言葉は明瞭で核心を突いてくる不思議な魅力がある。連合赤軍の若者たちが使う言葉は、思想書の影響そのままに抽象的で分かり難い。実際のところ若者たちは、言葉と自らの未熟さとの乖離に苦しんでいたのではないだろうか。
![]()
若松孝二は豊富な人生経験から、理想だけではなく方法論まで明確に提示した。その肉体言語というべきものに、若者たちは敏感に反応したのだと思う。
“梁山泊”さながら、若松孝二の下に結集した才能あふれる若者たち。足立正生、大和屋竺、沖島勲、小水一男、曾根中生、荒井晴彦…。挙げればきりないが、映画界に大きな影響を与えている逸材ばかりだ。若松孝二は彼らに自らの作品の脚本を書かせたり、プロデュースして監督させたりもした。若き才能を活用しながら育てる映画作りは、今でも続いている。映画監督が映画館を経営するという世界的に前例のない「シネマスコーレ」。開館して29年経つ。いかに次代に映画を橋渡しするか、若松孝二の自覚と熱意が伝わってくる。
![]()
私の好きな言葉だ。若松孝二はヨルダンのジェラシ・マウンテンという場所で死にかけたことがある。彼を守ってくれたのはパレスチナの戦士だった。子孫のために自分の故郷を取り戻そうと闘う戦士たち。そんな自らの命を顧みないほど熱い志に触れ、彼は映画の本当の存在意義に気づく。めちゃくちゃに撮っていながらも、根底に流れる一筋の情熱。命に代えても伝えなければいけないものがある。その志を映画で体現してきたのが若松孝二だ。
インターネットが世界を動かす時代となった現在。今起きているエジプトの反政府運動もネットでの呼びかけが発端になったという。匿名性という武器がネットにはあるが、その反面肉体性が欠如してしまう。エジプトの運動も結局はデモとなり、肉体を全面に打ち出した闘いとなっている。今私たちが直面している息苦しい世界。そこに風穴を開けるにはどうしたらいいか。自分の名前を前面に出し、いたる所を駆け回って、危ない時は腹にさらしを巻く、若松孝二流の映画術。その無骨な闘いは、私たちの閉塞した世界を打ち壊すヒントを与えてくれる。
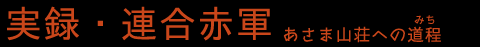
実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(みち)
 (2007年 日本 190分 ビスタ/SR)
(2007年 日本 190分 ビスタ/SR)
2011年2月5日から2月11日まで上映
■監督・製作・企画・脚本 若松孝二
■原作・脚本 掛川正幸
■撮影 辻智彦/戸田義久
■音楽 ジム・オルーク
■ナレーション 原田芳雄
■出演 坂井真紀/ARATA/並木愛枝/地曵豪/坂口拓/伴杏里/大西信満 ほか
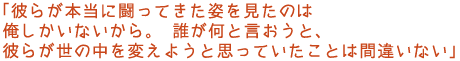
1972年2月28日、日本中を釘付けにした「あさま山荘事件」。それは日本で初めて“革命”の名の下に、銃で国家権力へ臨んだ闘いだった。なぜ彼らは勝利の展望もない国家権力との闘いに挑んだのか。ただの人殺し事件として抹殺された、若者たちの壮絶なる闘い。それを“実録”として甦らせ、もう一度世に問い直そうとしているのが『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』だ。
この映画は主に3つの段階で構成されている。
第一、連合赤軍が結成されるまで。
第二、総括と称しての同志粛清。
第三、あさま山荘での銃撃戦。
 連合赤軍結成までの過程は、遠山美枝子という女性を中心に描かれる。彼女は実際に若松プロの手伝いをしており、若松監督とは知己の間であった。働きながら夜は大学で勉強に励み、似た境遇を生きる重信房子とデモに参加する姿。当時の若者にとって革命を志すことは特別なことではなく、青春の在り処の一つであった。
連合赤軍結成までの過程は、遠山美枝子という女性を中心に描かれる。彼女は実際に若松プロの手伝いをしており、若松監督とは知己の間であった。働きながら夜は大学で勉強に励み、似た境遇を生きる重信房子とデモに参加する姿。当時の若者にとって革命を志すことは特別なことではなく、青春の在り処の一つであった。
“革命”の下に武装蜂起を始めた若者たち。彼らの大部分が当時の数少ない大学生であり、約束された将来と自分の全てを捨てて革命に挑んでいた。その答えが正しいかではなく、なぜ彼らはそこまで厳しい道を選んだのか。
「彼らが背負った凄惨さは何か?」
そんな若者たちを見つめ、彼らに支えられて映画を作ってきたからこそ、若松孝二は問い続けているのだ。
“総括”という名の同志粛清。
「わたしは、小嶋さんのようなりたくないです。死にたくないです。とにかく生きていたいんです…。でも本当にどう総括したらいいのか、わかんないんです」
遠山美枝子はそう訴えて、自らを殴ることに総括を要求され殺される。よりよい世界にするための革命のはずが、人間を最悪の行動に走らせてしまう悲劇。それは連合赤軍だけの特別なことなのであろうか。この描写の痛みは、今の社会そして私自身にも通じるものがあるからこそ、直截的に伝わってくるのだと思う。
 “銃口”がついに国家権力に向けられる「あさま山荘事件」。具体的に権力側は描かれず、あさま山荘の中で何が起こっていたのかに焦点が絞られる。残された連合赤軍兵士5名は悲壮な闘いの中で、革命の成功を口にし続ける。そんな中、若松孝二が自らの気持ちを託したという少年は何度も叫ぶ。
“銃口”がついに国家権力に向けられる「あさま山荘事件」。具体的に権力側は描かれず、あさま山荘の中で何が起こっていたのかに焦点が絞られる。残された連合赤軍兵士5名は悲壮な闘いの中で、革命の成功を口にし続ける。そんな中、若松孝二が自らの気持ちを託したという少年は何度も叫ぶ。
「みんな勇気がなかったんだよ!」
見えない敵に向けられた銃口。彼らは闘いの中で自らの、時代の、本当の総括をし始める。そんな若者たちの志を潰し、ひたすら歴史から消し去ろうとしてきた今の時代にこそ、若松孝二の銃口は向けられているのだ。

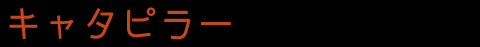
キャタピラー
 (2010年 日本 84分
(2010年 日本 84分  ビスタ/SR)
ビスタ/SR)
2011年2月5日から2月11日まで上映
■監督 若松孝二
■脚本 黒沢久子/出口出
■撮影 辻智彦/戸田義久
■主題歌 元ちとせ『死んだ女の子』
■出演 寺島しのぶ/大西信満/吉澤健/粕谷佳五/地曵豪/ARATA/篠原勝之
■2010年ベルリン国際映画祭銀熊賞(最優秀女優賞)寺島しのぶ
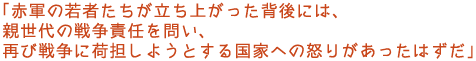
一銭五厘の赤紙1枚で召集される男たち。シゲ子(寺島しのぶ)の夫・久蔵(大西信満)も盛大に見送られ、勇ましく戦場へと出征していった。しかしシゲ子の元に帰ってきた久蔵は、顔面が焼けただれ、四肢を失った無残な姿であった。村中から奇異の眼を向けられながらも、多くの勲章を胸に、“生ける軍神”と祀り上げられる久蔵。
 彼のぼんやりとした視線の先にあるのは、かつての武功を讃えた新聞の記事と国からもらった勲章だった。 シゲ子は「銃後の妻の鑑」として、献身的に久蔵の世話をした。かつて自分をののしり、殴り、蹴り上げた、その声も手も足も失った夫の体を拭き、食事を食べさせた。四肢の自由を失った久蔵だが、性欲を失うことはなかった。勃起すればシゲ子を求め、シゲ子は黙ってその下半身にまたがった。シゲ子の胸に冷たい風が吹きぬけていく。そして、1945年8月15日。男と女に、敗戦の日が訪れた…。
彼のぼんやりとした視線の先にあるのは、かつての武功を讃えた新聞の記事と国からもらった勲章だった。 シゲ子は「銃後の妻の鑑」として、献身的に久蔵の世話をした。かつて自分をののしり、殴り、蹴り上げた、その声も手も足も失った夫の体を拭き、食事を食べさせた。四肢の自由を失った久蔵だが、性欲を失うことはなかった。勃起すればシゲ子を求め、シゲ子は黙ってその下半身にまたがった。シゲ子の胸に冷たい風が吹きぬけていく。そして、1945年8月15日。男と女に、敗戦の日が訪れた…。
若松孝二が最も得意としてきた“密室劇”。お金がかからず、落ち着いて演出ができる利点があるという。たった15人のスタッフと12日で撮影されたこの映画。資本家に縛られず自分の作りたい映画を作るために、彼は頭を使い自ら稼いで、インディペンデント映画の先駆けとなった。故にいわゆる大作映画とは違う、アナーキーで刺激的な作品が次々と生み出された。最小限の投資で最大限の効果を上げる映画術。長いフィルモグラフィーの中で培われたその方法には、これからの表現者の指針ともなるべき宝がたくさん潜んでいる。
 「食べて、寝て、食べて、寝て、食べて、寝て…」
「食べて、寝て、食べて、寝て、食べて、寝て…」
若松孝二は“本能”を描いてきた作家である。生々しさ、汚さ、いやらしさという負の側面から、包み隠さず人間を描こうとする。寝るということは生殖に限らず、相手の心を抱くという究極のコミュニケーションだ。シゲ子と久蔵の関係性は繰り返される本能によって暴露される。そしてたった二人の夫婦の関係性から、時代の移り変わりを描く見事さ。個人の内面と社会の在り方は全て関わりあっている。その密室を爆破して時代の心を表現してみせるのが若松孝二だ。
戦後、新たなる社会の変化を必要としていたのに、その本質は何も変わらない。大人たちへの若者たちの異議申し立ても力づくで潰される。波乱万丈なる戦後史と共に疾走し続けてきた若松孝二。でも彼は負けることなく、今でも新たなる時代の可能性を信じて、自らの方法で全身全霊思いの丈を映画にぶつけてくる。それは未来を創る若者たちに捧げられた、若松孝二のメッセージ。
![]()
(mako)


