
年を追うごとに正月が好きになる。
正月を理由に朝から酒を飲めるからだろうか、たまにしかないまとまった休みだからだろうか、もちろんそうだ。
しかしそれよりも、賑やかさや人の出入りの慌ただしさも気にならない、底の抜けた爽やかさが好きだ。
普段の、騒ぎながら皆で飲む酒。雰囲気のあるバーで飲む上等な酒。
それもいいが、正月に気の置けない人と酌む酒にはやはり格別なものがある。
酒の話ばかりだけれど、酒の良さも難儀のないその雰囲気があればこそだ。
小津安二郎の映画を正月に観る。これは何かそんな正月に飲む酒に似て、格別なものではなかろうか。
妙に騒がしく驚かせることもなく、気忙しくハラハラもさせない。
いつもと同じように笠智衆は座しているし、原節子や女たちの心配事も、幾度も繰り返してきたこと。
我々と同じように、去年から持ち越した心配事なぞ表沙汰にはせずに一献、また一献と杯を傾け、時は進むのだ。
しかし、今年に限っては、年を越して旨い酒が飲めるのかどうか心配になっている自分がいる。
それはやっぱりあの震災からはどこか心が落ち着かずにいて、さらに歳末の気忙しさも相俟って、
いつもと同じ年越しというわけにはいかないのだろうなと、弱気になってしまうのだ。
東京はいま、おおきなプラットホームだ。
自衛隊に入隊したのだろうか、制服姿の青年と、彼を見送る女子高生との東京駅での別れを見た。
ボランティアへ向かう人々が支援物資を持ち寄って、一台の車に乗り込む姿を見た。
テレビのニュースで見た、親元を離れて東京で暮らしている福島の子供たち。
震災の直後から、吸い込まれるように東京から東北へ人が動き、吐きだした息のように人が散らばっていく。
多くの人が移動したこの年の正月。東京という曲がり角を曲がって全国へ散らばってしまった被災者の方々や、
東北へ向かった彼らも、今日はどこかで卓を囲み、親しい人との久方ぶりの再会を楽しんでいるかもしれない。
わたし自身、家族と実家ではなく東京の街で会う機会が増えた。
わずかな時の合間の、即席の食卓を囲んでの食事と会話。
「大変だね」「そうだね。まぁでも頑張るしかないよ」
しかし、こんな会話を思い出すたびに私はどこか腹が立つ。
あぁ小津の映画を観たときみたいだ。なんかしなくちゃ。
不甲斐なく日々に溺れていってしまうのが怖いのだ。
今、彼の映画を観てみるといいのかもしれない。自分の心の中の微振動を感じながら。
関係の中に潜む有事の影、生活の変化を想像せずにはいられない。
不安定で、出鱈目で、流動的なわたしたちの生活と向き合った映画。
あの正月の爽やかさのように、無情に、間断なく空気を入れかえていく映画。
小津安二郎の映画。
あぁ勉強したい、働きたいと思う。また、そうしながら小津の映画をみていきたい。
高校生のときに初めてみた小津の映画。
大学生のときに、社会人になってからみた小津の映画。
結婚したら、子供が産まれたら、親が亡くなったら小津の映画をみるのだと思う。
2011年という年の終わり、2012年という年の始まり。
時間が進んで行くのが、どこか少しサビシイ気もするのですが、
皆さま、今後もどうぞよろしくお願いいたします。
(ぽっけ)
東京暮色
(1957年 日本 140分 スタンダード/MONO)
 2011年12月31日から2012年1月6日まで上映
2011年12月31日から2012年1月6日まで上映
■監督・脚本 小津安二郎
■脚本 野田高梧
■撮影 厚田雄春
■美術 浜田辰雄
■音楽 斎藤高順
■出演 原節子/有馬稲子/笠智衆/山田五十鈴/高橋貞二/田浦正巳/杉村春子/山村聡/信欣三/藤原釜足/菅原通済
★製作から長い年月がたっているため、本編上映中お見苦しい箇所・お聞き苦しい箇所がございます。ご了承の上、ご鑑賞いただきますようお願いいたします。
![]()
杉山周吉は銀行の監査役をつとめ、雑司ヶ谷の一角で、次女の明子とふたりで静かに暮らしている。ところが最近は、長女の孝子は夫との折り合いが悪いらしく、子供を連れてたびたび実家に帰ってくる。その上、明子はだらしのない恋人の子を身ごもり、密かに堕胎までしていた。
その頃、五反田のとある麻雀屋の女主人喜久子が明子のことを尋ねまわっていることを聞き、明子はその女性が死んだと思っていた実母であることを知る。喜久子は、周吉が京城に赴任していた時の部下と深い仲になり、周吉と幼い娘達を残して、出奔していた過去があったのだった…。
![]()
『早春』に続いて野田高梧と共に執筆された本作は、小津にとって最後の白黒映画であるが、その内容の暗さからしばしば二人の間で意見が対立し、野田は完成した作品に対しても終始否定的であったという。小津は一貫して、母のいない家族や子供を亡くした家族など、なにかが足りない家族像を描いてきた。しかし家族に欠員のある事情に就いて、作中で深く詮索することはなかった。そのような作品系譜の中で「事情」そのものを主題に据えたこの映画は、特に異例の作品だといえる。
話のモチーフは、当時流行していたジェームズ・ディーン主演の『エデンの東』だとされるが、あまりに救いのない陰鬱とした内容に、小津の自信と執着にもかかわらず、世評は『東京暮色』を失敗作だとみなした。しかしながら、小津に潜むある種の葛藤を暗喩しているかのような、生々しい登場人物の内面描写を描いた本作は、東京に生きる人間の孤独や悲哀に満ち溢れており、公開から50年以上が経った今、観る者に忘れ難い余韻と詩情を残している。


東京物語
(1953年 日本 136分 スタンダード/MONO)
 2011年12月31日から2012年1月6日まで上映
2011年12月31日から2012年1月6日まで上映
■監督・脚本 小津安二郎
■脚本 野田高梧
■撮影 厚田雄春
■美術 浜田辰雄
■音楽 斎藤高順
■出演 笠智衆/東山千栄子/原節子/杉村春子/山村聡/三宅邦子/香川京子/東野英治郎/中村伸郎/大坂志郎
★製作から長い年月がたっているため、本編上映中お見苦しい箇所・お聞き苦しい箇所がございます。ご了承の上、ご鑑賞いただきますようお願いいたします。
![]()
 尾道に住む、周吉ととみの老夫婦は、老後の思い出にと東京に暮らす子供たちを訪ねることにした。周吉は20数年ぶり、とみとっては初めての上京であるこの旅を、とても楽しみにしていた二人だったが、いざ東京に来てみると、子供たちは両親を歓待することはどこか二の次で、それぞれの生活に精一杯であった。唯一、戦死した次男の嫁紀子だけが、二人の来訪を心から喜び迎えてくれた。
尾道に住む、周吉ととみの老夫婦は、老後の思い出にと東京に暮らす子供たちを訪ねることにした。周吉は20数年ぶり、とみとっては初めての上京であるこの旅を、とても楽しみにしていた二人だったが、いざ東京に来てみると、子供たちは両親を歓待することはどこか二の次で、それぞれの生活に精一杯であった。唯一、戦死した次男の嫁紀子だけが、二人の来訪を心から喜び迎えてくれた。
面倒を見てやれないのも悪いと、子供たちは両親を熱海旅行へと行かせる。一応はみな親切だが、どこか親身な温かさに欠けた子供たちに、周吉ととみは何かさびしく、物足りなかった。熱海へやってきた二人は、早く田舎へ帰ろうと話し合うのだった。
ハハキトク――尾道にいる末娘からの電報が東京のみなを驚かしたのは、夫婦が東京から帰っていったまもなくのことであった…。
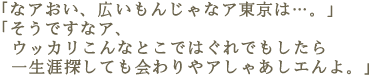
小津の映画には東京を舞台にした作品がとても多い。それらはほぼすべてオリジナルストーリーであり、他の監督には見られない、小津の東京への執着を証明している。そしてその「小津の東京」のなかでも集大成であり、彼の代表作として不朽の輝きをはなっているのがこの『東京物語』である。
『晩春』や『お茶漬けの味』で名コンビとなった野田高梧との共同脚本により、構想、執筆、推敲と、実に7ヶ月の日数を費やして完成した本作。年老いた夫婦の東京旅行を通して、戦後変わりつつある家族の関係をテーマに、人間の生と死までをも見つめている。 家でひとり侘しくたたずむ笠智衆を捉えたショットは映画史上に残る名ラスト・シーンだろう。国際的にも非常に有名な日本映画のひとつであり、ヴィム・ヴェンダースやホウ・シャオシェン、ジュゼッペ・トルナトーレ等名だたる監督によりオマージュを捧げた作品が製作されている。

