
永遠に語り継がれる偉大な喜劇王、チャールズ・チャップリンとジャック・タチ。
彼らを敬愛してやまない監督たちが生み出したのは、
一方はバレエ、もう一方はアニメとまるで方向性が違っていながら、
どちらも心揺さぶられる「出会い」に満ちた、馴染み深くも全く新しい映画でした。
それが今週の上映作品、
『ダンシング・チャップリン』と『イリュージョニスト』の二本です。
『ダンシング・チャップリン』の監督、周防正行は常に新しい世界との出会いを描いてきました。
『Shall we ダンス?』で突然社交ダンスに出会ってしまったり、
『しこふんじゃった。』で急に相撲部に入部することになったり、
痴漢に間違えられて人生が一転するようなものさえあります。
自分の人生を急激に変えてしまうような出会い。
今作では、それはバレエダンサーである妻・草刈民代との出会いであり、
彼女の住む「バレエ」という世界との出会いなのではないでしょうか。
新しい世界に飛び込むということ、それは周防監督のどの作品にも共通しているように思えます。
そして『イリュージョニスト』ではマジシャン・タチシェフのもとに一人の少女が飛び込んできます。
彼女は少なからずタチシェフの生活に影響を与え始め、彼の日常は少しずつ変化していくのです。
新たな訪問者に対する、困惑と喜び。
タチシェフは彼女のために、最後の最後まで自分の手品にタネがあるようなそぶりを見せないのでした。
『ダンシング・チャップリン』は新しい世界に足を踏み入れた訪問者の視点、
『イリュージョニスト』はある世界の住人として訪問者を受け入れる視点から語られています。
一つの複雑なイベントである出会いを真逆の立場からみつめあったもの。
まるで出会いという塊をちょうど半分に割った二つのかけらみたいなものが、
『ダンシング・チャップリン』と『イリュージョニスト』なのかもしれません。
だからこそ、それぞれの映画におけるアプローチとは逆の視点が浮き彫りにされていきます。
周防監督がバレエの世界へと飛び込んでいくのと同時に、バレエダンサー達は周防監督を受け入れていきました。
それは『イリュージョニスト』のタチシェフが当然飛び込んできた少女を受け入れたのと同じです。
また一方で、手品に魅了された少女がタチシェフのあとを追ってくるということと、
周防監督がバレエの映画を撮るということは同じ事なのかもしれません。
「出会い」を経験した時、私たちは主観的な側面からしかそれを眺めることはできません。
しかし『ダンシング・チャップリン』と『イリュージョニスト』はどちらも逆のアプローチでありながら、
お互いの視点が至るところに含まれています。
私たちが過去を思い返して想像するしかない出会いの向こう側の視点を、
この二本の映画は丸ごと詰め込むことに成功したに違いありません。
(ジャック)
イリュージョニスト
L'ILLUSIONNISTE
(2010年 イギリス/フランス 80分 ビスタ/SRD)
 2011年11月12日から11月18日まで上映
2011年11月12日から11月18日まで上映
■監督・脚色・キャラクターデザイン・作曲 シルヴァン・ショメ
■オリジナル脚本 ジャック・タチ
■製作 ボブ・ラスト/サリー・ショメ
■声の出演 ジャン=クロード・ドンダ/エイリー・ランキン
■アカデミー賞長編アニメ賞ノミネート/セザール賞アニメーション賞受賞/ベルリン国際映画祭正式出品/ニューヨーク批評家協会賞最優秀アニメーション映画賞受賞、ほか受賞・ノミネート多数
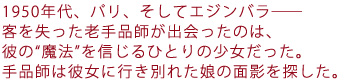
 ロックンロールが世界を席捲し、時代が古きを追い落とすように進む1950年代のパリ。昔ながらのマジックを披露する初老の手品師タチシェフは、かつての人気をすっかり失い、三流の劇場や場末のバーでドサ回りの日々。ある日スコットランドの離島に流れ着いた彼は、やっと電気が開通したばかりの片田舎のバーで、貧しい少女アリスと会う。
ロックンロールが世界を席捲し、時代が古きを追い落とすように進む1950年代のパリ。昔ながらのマジックを披露する初老の手品師タチシェフは、かつての人気をすっかり失い、三流の劇場や場末のバーでドサ回りの日々。ある日スコットランドの離島に流れ着いた彼は、やっと電気が開通したばかりの片田舎のバーで、貧しい少女アリスと会う。
手品師のことを何でも願いを叶えてくれる“魔法使い”と信じ、島を離れるタチシェフを追うアリス。落ちぶれた自分を尊敬し、甲斐甲斐しく世話を焼き時に甘えるアリスに、行き別れた娘の面影を見るタチシェフ。やがてふたりは言葉が通じないながらも、エジンバラの片隅で一緒に暮らし始めるが…。
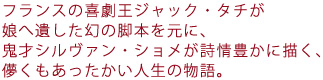
 『ぼくの伯父さん』をはじめ、生涯にわずか6作品を監督し、今なお世界中で愛され続けているジャック・タチ。彼は「FILM TATI No.4」という娘に捧げた1本の脚本を残していた。半世紀にわたりフランス国立映画センターで眠り続けていたこの幻の脚本に息吹を与えたのは、長編デビュー作『ベルヴィル・ランデブー』で一躍脚光を浴びたシルヴァン・ショメ監督。本国フランスで100万人以上を動員する大ヒットを記録し、世界33ヶ国以上で公開され、各国の映画賞を総なめにした前作に続き彼が挑んだのは、前作とは正反対の、シンプルにして、しかし豊潤な、ある時代遅れの手品師の美しい物語だ。
『ぼくの伯父さん』をはじめ、生涯にわずか6作品を監督し、今なお世界中で愛され続けているジャック・タチ。彼は「FILM TATI No.4」という娘に捧げた1本の脚本を残していた。半世紀にわたりフランス国立映画センターで眠り続けていたこの幻の脚本に息吹を与えたのは、長編デビュー作『ベルヴィル・ランデブー』で一躍脚光を浴びたシルヴァン・ショメ監督。本国フランスで100万人以上を動員する大ヒットを記録し、世界33ヶ国以上で公開され、各国の映画賞を総なめにした前作に続き彼が挑んだのは、前作とは正反対の、シンプルにして、しかし豊潤な、ある時代遅れの手品師の美しい物語だ。
タチのエスプリ、そしてショメが創造したノスタルジックで美しい映像世界が見事に融合し、永遠に心に刻まれる物語がここに誕生した。


ダンシング・チャップリン
(2010年 日本 136分 ビスタ/SR)
 2011年11月12日から11月18日まで上映
2011年11月12日から11月18日まで上映
■監督・構成・エグゼクティブ・プロデューサー 周防正行
■原作・振付 ローラン・プティ
■製作 亀山千広
■音楽 チャールズ・チャップリン/フィオレンツォ・カルピ/周防義和
■出演 ルイジ・ボニーノ/草刈民代/ジャン=シャルル・ヴェルシェール/リエンツ・チャン/ナタリエル・マリー/マルタン・アルアーグ/グレゴワール・ランシエ
★上映途中に約5分間の幕間がございます。
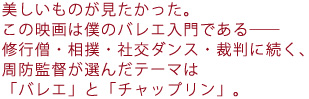
 2009年7月、都内の撮影所で、ある作品がクランクインした。監督は『Shall we ダンス?』や『それでもボクはやってない』などの話題作で、常に独自の視点で国内だけでなく海外でも注目を集めてきた周防正行。彼が新作に選んだ題材は「バレエ」と「チャップリン」。撮影所の中に組まれたセットは床、壁ともに真っ黒。台本は、なし。周防の掛け声が響き、音楽とともに登場したのは軽やかに舞うチャップリン?“美しいバレエの映画にする”ために新しい試みが始まった。
2009年7月、都内の撮影所で、ある作品がクランクインした。監督は『Shall we ダンス?』や『それでもボクはやってない』などの話題作で、常に独自の視点で国内だけでなく海外でも注目を集めてきた周防正行。彼が新作に選んだ題材は「バレエ」と「チャップリン」。撮影所の中に組まれたセットは床、壁ともに真っ黒。台本は、なし。周防の掛け声が響き、音楽とともに登場したのは軽やかに舞うチャップリン?“美しいバレエの映画にする”ために新しい試みが始まった。
監督が選んだのは、フランスの巨匠振付家ローラン・プティの、チャップリンの数々の名作を題材にしたバレエ作品<ダンシング・チャップリン>。1991年の初演からチャップリンを踊り続けるダンサー、ルイジ・ボニーノのために振り付けられた作品であり、彼は世界で唯一この作品のチャップリンを踊ることができるバレエダンサーである。しかしルイジも還暦になり、肉体的に限界を迎えつつある。このままでは幻の作品になってしまう!と危機感を抱いた監督の強い思いからこの企画がスタートした。
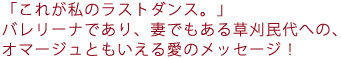
監督が映画化を計画したもうひとつの理由は、2009年にバレリーナを引退し女優へと転身した、自身の妻である草刈民代の存在だった。バレエのために鍛え上げられてきた身体で踊った彼女の“最後の踊り”を、夫として、映画監督としてフィルムに焼き付けたいという思いが、ルイジへの思いと重なった。彼女は本作で、『街の灯』の盲目の花売り娘をはじめ、コミカルな表情で楽しませる『キッド』のキッド役まで、女優としての才能も発揮して全7役をこなし、まさに彼女の36年のバレエ人生の集大成ともいえるラストダンスとなった。
また本作は、監督が映画化するに至るまでの姿を追った60日間の舞台裏を第一幕、東宝スタジオで撮影されたバレエを第二幕、という二幕で構成された全く新しいタイプの映画である。バレリーナの夫として15年、バレエの世界に魅了されてきた周防監督がフィルムに残したかったもの。それは振付家、衣装デザイナー、バレエダンサーそれぞれが美を追求する姿、そして完成された美しい舞いである。第一幕ではバレエと映画製作の舞台裏を知り、第二幕ではその知識をベースに最高に美しいバレエを鑑賞することができる、極上のエンターテインメント映画が完成した。
