
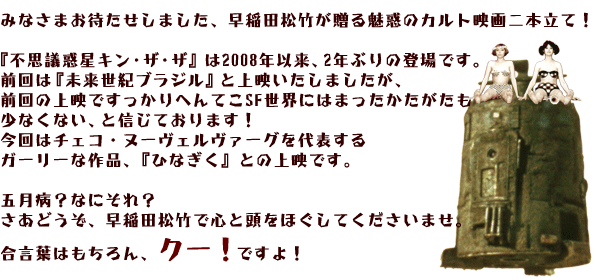
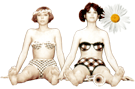 ひなぎく
ひなぎく
SEDMIKRASKY
(1966年 チェコスロヴァキア 75分 SD/MONO )
 2010年5月8日から5月14日まで上映
2010年5月8日から5月14日まで上映
■監督・原案・脚本 ヴェラ・ヒティロヴァー
■原案 パーウェル・ユラーチェク
■脚本 エステル・クルンバホヴァ
■撮影 ヤロスラフ・クチェラ
■音楽 イジィ・シュスト/イジィ・シュルトル
■出演 イヴァナ・カルバノヴァー/イトカ・チェルホヴァー
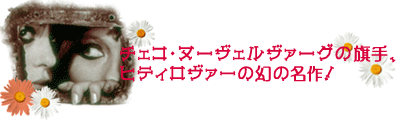
好き勝手に生きる女の子2人のおはなしです。おしゃれして出かけては男をだまして食事をおごらせ、たらふく食べた後に嘘泣きして逃げていく。2人は共にマリエと名乗る。もしくはイェツィンカ。ヤルミラのときもある。本当の名前はわからない。姉妹かどうかもよくわからない。
牛乳を沸かしてミルク風呂にはいる。部屋中の紙を燃やしてソーセージをあぶる。雑誌を切り抜いてるうちに互いの体をちょんぎり始めて、しまいには画面まで切ってしまう。細切れになった画面はみるみるうちに元に戻り、ふたりは何事もなかったようにまた出かけていく。
「死ね、死ね、死ね、死ね!」
「わたしたち生きてるのよ。生きてる!生きてる!」
つまらないことは嫌い。すぐに飽きる。おもしろくなければやりたくない。食べることに貪欲で、人のことは気にしない。無軌道に無計画に、やりたい放題。意味のあることなんて何もしない。そもそも意味ってなーに?
一見そんなふうにしか見えないが、彼女たちは、自分たちが生きている世界へ向けてせいいっぱい反乱しているのだ。
中身があるんだかないんだかわからない“雰囲気映画”は今の時代もたくさんあるけど、この映画が作られた60年代のチェコは、社会主義が唱えられ自由が抑圧されていた時代だった。 そんな時代に、よくもまあこんな映画を作ったなと感心してしまう。社会も国も秩序もまるで関係ないと言わんばかりに、自由を謳歌する映画を。
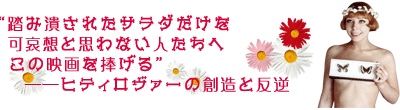
ストーリーなんてまるでない(ように思われる)のは、監督のヒティロヴァーにとって、この映画自体が自分の意思を表現する手段だったからだろう。それが結果として「前衛的」で「実験的」となった。ヒティロヴァーはこの作品のおかげで、共産主義国家から反体制的とみなされ、76年まで活動を停止させられる。
ヒティロヴァーは後にこう語っている。「危険をおかさず探求もしない人は、失敗しないかわりに発見への希望も見出せません」と。
私は昔から、ものをつくっている人が好きだ。好きというか、憧れに近い。外からのどんな風にも負けずに、自分の内側を形として外側へ変換できる人。
ふたりが着る洋服(色や柄が違っても、ふたりはいつもまったく同じ型のワンピースを着続ける)や、部屋のインテリアなど、もちろん全てが素敵に可愛い。色ズレ、カラーリング、光学処理、唐突な場面展開など、あらゆる映画的手法もおもしろい。
おしゃれなカルト映画?女の子映画の決定版?話わかんないけどとにかくかわいい?それでもけっこう。それも映画の価値だから。でも、この映画が作られた時代へ、少し思いをめぐらせてみてほしい。
映画にはいろんな観方がある。私にとっては、「やりたいことはなんでもやっていいんだよ」と背中をそっと押してくれる、いつもそんな存在の映画だった。


不思議惑星キン・ザ・ザ
KIN-DZA-DZA!
(1986年 ソ連 134分 SD/MONO )
 2010年5月8日から5月14日まで上映
2010年5月8日から5月14日まで上映
■監督・脚本 ゲオルギー・ダネリア
■脚本 レヴァス・カブリアゼ
■出演 スタニスラフ・リュブシン/エフゲニー・レオーノフ
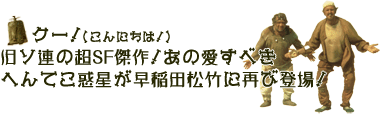
凍てつく冬のモスクワ。真面目なソ連市民であるマシコフは、妻に頼まれて買い物に出ると、そこに青年がやってきて「あの人がヘンなこと言ってます」と助けを求めて来た。
「裸足だし…」と青年が指すその怪しい男は、自分は他の星からやって来たのだと訴えていた。だが、常識あるマシコフは戯言と思って信じず、男の手の中の「空間移動装置」を押してしまう。瞬間、マシコフと青年は砂漠のど真ん中にワープしていた!
呆然としながらも、マシコフは年長者の威厳を失うまいと「ここはソ連国内の砂漠だ」と断言。街を目指して歩いてみるが、灼熱の太陽が2人を襲い、酢はあっても水はない。とうとう疲れ果て砂の中に座り込んだ2人の前に現れたのは、釣鐘型の奇妙な宇宙船だった…!
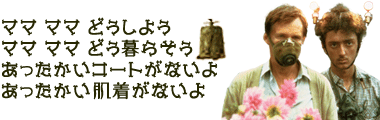
数多くの優れたSFが、今も昔もたくさん存在する。例えばキューブリックの『2001年宇宙の旅』は、宇宙船や重力の描き方などが非常に正確であることで有名だ。
 でも、この『不思議惑星キン・ザ・ザ』は、科学を小気味よく無視した映画である。ご覧頂きたい、この釣鐘型の奇妙な宇宙船を!
でも、この『不思議惑星キン・ザ・ザ』は、科学を小気味よく無視した映画である。ご覧頂きたい、この釣鐘型の奇妙な宇宙船を!
こんなもの、どうやったって飛ぶわけがない(でも、飛ぶんです)。「クー」で大半が済まされるあの宇宙語も、通用するわけがない(でも、通用します)。
そんなキン・ザ・ザの“途方もなさ”は、ある意味最大のチャームポントとなって人々を中毒にしてきた。公開当時は批評家から散々コケにされたものの、ソ連全土で1520万人という驚異的な動員数を記録。その後も世界中でカルト的人気を博した。
私たちを魅了して止まないのは、純粋に面白いことの正しさを、この作品が証明してくれるからかもしれない。キン・ザ・ザに敷かれる理不尽な身分制度やマッチの驚くべき価値は、もちろん旧ソ連の社会主義や、西側資本主義への風刺が込められているだろう。
だが、その強烈なアイロニーは巧みにSFへと昇華され、私たちを心地よく包み込んでくれる。キン・ザ・ザにあるのは、計算されてこその上質な笑いなのだ。
ローテクでやぼったいという一種の“センスの良さ”と“賢さ”が織りなす『不思議惑星キン・ザ・ザ』。「クー!」…この魅力はある種の“粋”なのではないだろうか。
