

1941年ポーランド生まれ。70年代を通じ、優れたドキュメンタリー作品を多数発表。ポーランドの現実を独自の視点でとらえ、差し迫った社会危機をはっきりと指摘した最初の映画作家であった。
1976年に長編劇映画デビュー。愛と運命に導かれる人々の心の内奥を見つめ続け、類まれな傑作、名作を次々と発表、世界中に多くのファンを獲得した。
“トリコロール”三部作を完成後、監督を廃業。ダンテの『神曲』に基づいた『天国編』『地獄編』『煉獄編』三部作の脚本に取りかかっていたが、その最中、96年に突然の心臓発作により54歳の生涯を終えた。
2002年、三部作の脚本完成部分『天国編』がトム・ティクヴァ監督により『ヘヴン』として映画化された。2005年、『地獄編』がダニス・タノヴィッチによって『美しき運命の傷痕』として映画化された。

・初恋(1974)
・スタッフ(1975)
・ある党員の履歴書(1975)
・平穏(1976)
・傷跡(1976)
・アマチュア(1979)
・偶然(1982)
・終わりなし(1984)
・殺人に関する短いフィルム(1987)
・愛に関する短いフィルム(1988)
・デカローグ(1988)
・ふたりのベロニカ(1991)
・トリコロール/青の愛(1993)
・トリコロール/白の愛(1994)
・トリコロール/赤の愛(1994)
・ヘヴン(2002)*脚本(トム・ティクヴァ監督作品)
・美しき運命の傷痕(2005)*原案/ダニス・ダノヴィッチ監督作品
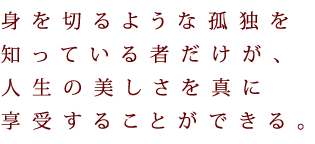
あなたにとって人生とは?──こんな問いのはるか彼方、日常の中では沈んでいってしまうような大切な記憶や想いをみんな連れて観に来てほしい作品があります。“トリコロール”三部作と『ふたりのベロニカ』。5月10日より、2週にわたってクシシュトフ・キェシロフスキ監督作品を特集します。
知り合うはずのなかった誰か。
私とは似ても似つかないはずの誰か。
起こらないはずの事件。
変わらないはずの日常。
何かが起こったあとでは、「はず」という言葉にどんな力を持たせることもできない。それが「運命」。 その壁にうつる神の姿を見つける人もいるかもしれない。 しかし、そこに人間の愛と美の孤高の姿を描いたのがキェシロフスキでした。
フォトジェニックな映像とその手触り、温度。 キェシロフスキの映画は、観ているだけだとは思えないほどにやわらかく観客を包み込み、そして拒む。 そのみずみずしく繊細な世界は多くの人々に愛されています。
ポーランドで生まれ、ドキュメンタリー作家としてキャリアをスタートしたキェシロフスキは、長編劇映画デビュー後も並行してドキュメンタリーを製作していました。 たとえば、日本においては戦後からさかんにドキュメンタリー映画と劇映画が並行して撮られるようになったように、またヌーヴェルヴァーグでいう右岸派・左岸派のように映像は常に社会の現実と虚構の両面を映してきました。 両方を一手に製作している映像作家も多く、クシシュトフ・キェシロフスキもその代表的な人物と言えるかもしれません。
一体彼はポーランドで何をその目に捕らえ、ドラマを描くようになったのでしょうか。
![]()
キェシロフスキ作品の中で描かれるのは人生のわずかな期間、しかも生涯を左右する、ある局面です。 逃れ難い運命の力を目前にした人物たちの、(時には孤独や絶望を招く選択を下すことになる)運命との格闘。それこそが、人を本当に美しく輝かせる──その姿をキェシロフスキは描いたのでした。
彼はドキュメンタリー作品を製作するうちに、人の生活への真の意味での「触れられなさ」を目撃し、 ドキュメンタリーでは捕らえられない“秘密の姿”をドラマで描いたのだと私は思います。 だからこそ彼の作中人物ののっぴきならなさと、孤独な美しさが観客の胸に届き、人生の豊かさが湧き上がってくるのです。
立ち入ることが許されないはずの硬質な個人の領域に、真実という愛を見つけた。 キェシロフスキはとても現代的に、重要かつ普遍的なテーマを描いた作家です。 日頃では触れがたい、人間の人生の豊かさに、あなたも触れてみてはいかがでしょうか。 是非一度足を運んでみて下さい。


 (1993年 フランス 99分 ビスタ/SR )
(1993年 フランス 99分 ビスタ/SR )
■監督・製作・脚本 クシシュトフ・キェシロフスキ
■撮影 スワヴォミール・イジャック
■音楽 ズビグニエフ・プレイスネル
■出演 ジュリエット・ビノシュ/ブノワ・レジャン/エレーヌ・ヴァンサン/フローレンス・ペルネル/シャルロット・ヴェリ/エマニュエル・リヴァ
■ヴェネチア国際映画祭金獅子賞・女優賞・撮影賞/LA批評家協会賞音楽賞/セザール賞主演女優賞/音響賞/編集賞
フランス国旗で“自由”を象徴する「青」。青いファイル、青いプール、青い窓、青のモビール。たびたび主人公を照らし物語を運命的に結び付けていく青の光。作品には暗示的に青のイメージが散りばめられている。
そして青が示す感情を瞳の奥に照射させて、この映画でひときわ輝くジュリエット・ビノシュ。彼女のフィルモグラフィの中でも特にこの作品は印象的です。
夫と子どもを一度に失い自らも死を選ぶか、思い出とともに生きるか、それともまったく違った人生を始めるか、彼女は苦悩する。劇中で「いい人で、寛大で、理想の、頼れる女性」と亡き夫の愛人に言われるまでのプロセス、そして彼女の選択の一つ一つに与えられた憂鬱な絶対感は、強烈な共感と嫉妬を引き起こす。
 “自由”についての映画が数多く撮られている中で、この作品ほど現代女性の潜在的なメンタリティに深く根ざした“自由”を描ききった作品を私は他に知りません。(あったら観たいです)
“自由”についての映画が数多く撮られている中で、この作品ほど現代女性の潜在的なメンタリティに深く根ざした“自由”を描ききった作品を私は他に知りません。(あったら観たいです)
静寂と孤独の中で、青い光とともに彼女の中に響く音楽。「欧米統合祭のための協奏曲」亡き夫と共同で作曲した未完のこの曲の音色は、彼女以外の何者かの力を強く感じさせる。しかし孤独か、幸福か?自由か、不自由か?という問いは本当の自由を手に入れた彼女にはもう届かない。もし女性に生まれたならこのジュリエット・ビノシュになりたいと思うくらい憧れてしまう女性像だ。


 (1994年 フランス/ポーランド 92分 ビスタ/SR)
(1994年 フランス/ポーランド 92分 ビスタ/SR)
■監督・脚本 クシシュトフ・キェシロフスキ
■脚本 クシシュトフ・ピエシェヴィッチ
■撮影 エドワード・クロシンスキー
■音楽 ズビグニエフ・プレイスネル
■出演 ズビグニエフ・ザマホフスキー/ジュリー・デルピー/ヤヌシュ・ガヨス
■ベルリン国際映画祭監督賞
フランス国旗で“平等”を象徴する「白」。三部作中唯一男性が中心的に描かれ、少しコメディタッチな一面が前作『青』とは打ってかわった印象を与える。主人公カロル(ズビグニエフ・ザマホフスキー)の名はポーランド語で「チャーリー」(チャールズ・チャップリンの愛称)を意味するらしく、チャップリンの悲喜劇性をイメージしていることが、この作品の印象を三部作の中で際立てている理由かもしれない。
カロルと妻のドミニク(ジュリー・デルピー)のやり取りには男女の諍いの多くが凝縮されていて、観客には自己の体験の中から別れの予感、「もうどうしようもない」という感情が湧きあがってくる。
“平等”とはただ権利の話ではなく、この作品に垣間見られる“共有できない一線”に関係あるということがこの物語の見所だと思います。本来揺られ続け、固定されるはずのない人間の宿命と相反する純白─―ポーランドの冷たい雪、ドミニクの白い肌、石膏の胸像。もしかするとこの色には人を狂わせてなお、歩ませ続けていく力があるのかもしれない。


 (1994年 フランス/ポーランド/スイス 96分 ビスタ/SR )
(1994年 フランス/ポーランド/スイス 96分 ビスタ/SR )
■監督・脚本 クシシュトフ・キェシロフスキ
■脚本 クシシュトフ・ピエシェヴィッチ
■撮影 ピョートル・ソボチンスキー
■音楽 ズビグニエフ・プレイスネル
■出演 イレーヌ・ジャコブ/ジャン=ルイ・トランティニャン/フレデリック・フェデール/ジャン=ピエール・ロリ/サミュエル・ル・ビアン/マリオン・スタレンス
■全米批評家協会賞外国語映画賞/NY批評家協会賞外国映画賞/LA批評家協会賞外国映画賞/インディペンデント・スピリット賞外国映画賞/セザール賞音楽賞
フランス国旗で“博愛”を象徴する「赤」。三部作の最終章であり、キェシロフスキの遺作でもある本作は『ふたりのベロニカ』以来のミューズ、イレーヌ・ジャコブを女学生でモデルの主人公に、名優ジャン=ルイ・トランティニャンを退官した判事役に迎えて奏でる暖かみのある物語。シリーズのラストということもあって、トリコロール三部作だけでなく、『デカローグ』までも総括するような運命の悪戯と導きが、壮大なスケールを感じさせる。
「赤」とはすれ違うことを拒む色、存在のもつ無垢なエネルギーの色だ。誰もその色彩の輝きを無視することはできない。二つのカップルと一人の老人の過去と現在が響きあい、そのつながりが未来までも紡いでいくラストシーンは必見です。
 しかし一体トリコロール三部作とはなんだったのか。「自由」「平等」「博愛」がそれぞれ示し続けていたものが、時に物悲しい様相を見せながらエモーショナルに観客の心を動かしたかもしれない。それでもキェシロフスキがこの世を去ってからこの三人の女性の行方を知る人はいないのだ。
しかし一体トリコロール三部作とはなんだったのか。「自由」「平等」「博愛」がそれぞれ示し続けていたものが、時に物悲しい様相を見せながらエモーショナルに観客の心を動かしたかもしれない。それでもキェシロフスキがこの世を去ってからこの三人の女性の行方を知る人はいないのだ。
フランス革命以降、ヨーロッパから始まった旧世界との訣別。掲げられた3つの理念。少なからず発展を遂げて、自らの生き方を選び、お互いを尊重し、豊かな生活を求められる社会になってきたと言えるだろう。しかし大きな力の前に無力を感じている人が多いのではないだろうか?この映画たちは運命の前では無力だと教えてはいない。抗い、傷つきなお美しい人間たちの姿を目に焼きつけてほしい。


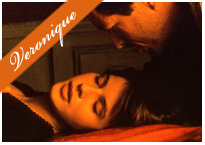 (1991年 フランス/ポーランド 92分 ビスタ/MONO)
(1991年 フランス/ポーランド 92分 ビスタ/MONO)
■監督・脚本 クシシュトフ・キェシロフスキ
■脚本 クシシュトフ・ピエシェヴィッチ
■撮影 スワヴォミール・イジャック
■音楽 ズビグニエフ・プレイスネル
■出演 イレーヌ・ジャコブ/フィリップ・ヴォルテール/サンドリーヌ・デュマ/ルイ・デュクルー
■カンヌ国際映画祭女優賞・FIPRESCI(国際映画批評家連盟)賞/全米批評家協会賞外国語映画賞/LA批評家協会賞音楽賞
■オフィシャルサイト http://www.bitters.co.jp/futari/
とても不思議なことだと思う。映画の中の人物に自分との共通点を見出すように、世界のどこかに自分と同じような誰かがいるかもしれない…という期待は絶えない。似たようなものを見つけたら、多少強引にでも自分の側に引き寄せてしまう─―この憧れにも似たかすかな期待と実際には出会えない寂しさの両方をこの映画は運んでいく。
パリとポーランドのふたりのベロニカはそれぞれの時間を越えて交信しあう。届くはずのない生きた証がメッセージとなって、ベロニカからベロニカへ。もしかしたらこのビー玉越しに見える世界はもうひとつの私の世界かもしれない、もしかしたら「私」はもうすでに一度生きたのかもしれない。
この「もしかしたら〜」の強い予感が、徐々に確信に変わっていく間に強くなるベロニカの新たな選択への意欲、そして犠牲としてのベロニカの人生の儚さに我々は自分の人生を省みることになるのだ。
 このふたりのベロニカに起きたことを偶然…と言えるだろうか?起きたこと、感じたことが開いた可能性はフィクションではない。私たちは感じたことを考えて現実に変えていくからこそ人間的なのだ。
このふたりのベロニカに起きたことを偶然…と言えるだろうか?起きたこと、感じたことが開いた可能性はフィクションではない。私たちは感じたことを考えて現実に変えていくからこそ人間的なのだ。
映画を観るという動作にも深くつながる、『ふたりのベロニカ』の鑑賞の体験はナンニ・モレッティ、エドワード・ヤン、マイケル・ウィンターボトム、日本では岩井俊二や行定勲など世界中の名だたる監督たちに影響を及ぼしている。
映像美もさることながらもうひとりのベロニカを感じさせるような複雑なカメラワーク、ズビグニェフ・プレイスネルによるポエティックな音楽、イレーヌ・ジャコブのみずみずしい魅力、様々な仕掛けがつくりだした幻想的で不可思議な世界は人間の感情の欠片をつぶさに拾い集め続けたキェシロフスキの結晶のような作品に仕上がっています。是非劇場でご鑑賞ください。

(ぽっけ)