
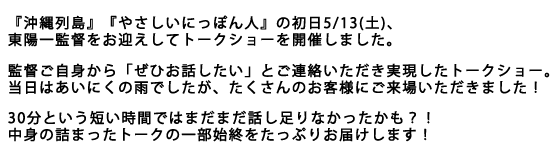
こんな大雨の日に、こんな古い映画を観に大勢の方に来ていただいてびっくりしております。今日が2017年の5月13日ですけど、あと2日経つと5月15日になりまして、いわゆる沖縄返還からちょうど45年という日を迎えるわけです。『沖縄列島』という映画は、作られたのがそれよりも4年ほど先の1968年だったものですから、来年は映画が出来てから半世紀ってことになるんです。とんでもない大昔の映画を今頃観ていただくというのは非常に複雑な気持ちで、嬉しいっていうのと恥ずかしいっていうのと、それから怖いなという、いろんな感情が混ざっているんですけど、観に来ていただいたお客様にご挨拶したいと思って喋らせていただくことになりました。
まず始めについ最近の話をしたいんですが、ドイツのテレビ局が制作したアンゲラ・メルケル首相についての40分くらいのテレビドキュメンタリーをたまたま観たんですね。メルケルという人は大変面白い人で、彼女は東ドイツに生まれて育ったんです。当時の東ドイツは、大体5人に1人が秘密警察「シュタージ」と関係のある人だといわれたくらい情報網が発達していた国でした。飲み屋で5人で一杯飲んでると、その5人に1人は確率上シュタージと知り合いであると言われるくらい。そういう時代に生きてこられた方なんですね。彼女がいうには、東ドイツという国は人間を個人としては絶対に見ないで、いかなる階層に属しているか、いかなる組織に属している人間なのか、あるいは単なる人数としてしか考えていなかったそうなんです。 東ドイツ政府はそのために倒れたと彼女は言います。
「人間を個人として扱う」ということは、どこの政治家でも口からは出ます。でもそれはそう言う必要があったからの話だというのは、世界中似たようなものだと私は認識しています。ところがメルケル首相が「個人」と言うときには、難民問題で沢山の人々を受け入れた実績のとおり、一人一人名前を持ってそれぞれの人生を生きているという認識を根本に持っているということがすぐわかるんですね。そのことに強い印象を受けたということもあるので、『沖縄列島』や『やさしいにっぽん人』に関して、今日は個人という観点からお話しできたらと思います。
『沖縄列島』という映画が出来る前にも、祖国復帰運動に関しての16ミリプリントで30、40分くらいの映画は東京でも沢山観ることができたんです。でもそれらは、偉そうな言い方にとられると困るんですが、復帰運動や社会問題としての基地問題の情報を伝えてはくれるのですが、どうも今まである程度知っていることのレポートだと感じることが多かった。やっぱり一人一人の人間を私は見たいという思いがありました。
それで、プロデューサーを中心とした友人たちと話して制作が決まりました。どこかから依頼されたという映画ではないので、経済的な裏話をすれば大変なことになるんですが。ともかく私は68年の春に、単身1ケ月くらい調査のために沖縄に行き、いろんな方にお会いして、いろんな所を見ました。当時はまだドル紙幣を持ってパスポートを取らなきゃならなかったんです。ドキュメンタリーははじめからストーリーとかを考えたりするのはとんでもない間違いだって頭の中にあったもんですから、ともかく調査で得たデータを持ち帰って整理し、それから撮影のために行って3カ月間で撮った映画です。
基地の問題にはいろんな問題が絡んでいるので、全てを一時間半とかそれくらいの映画で扱うわけにはいかないが、ともかくなるべく沢山の見たものや人を撮っていくっていうことを原則としました。一人一人を深く掘り下げられないにしても、印象強く残る形で個人を撮るというのを全体の根っこに据えたいと考えたんですね。例えばバスガイドをしながら演劇をやっている女性とか、カフェで働きながら理髪師になりたいと思っている女性とかですね。それから、アメリカの原子力潜水艦の一次排水に放射能が漏れ出たことがあって、それが漂っている海の下で船の底を掃除していた潜水士さん。彼は放射能汚染されている疑いがあるにも関わらず、ちゃんとした診療を受けられなかったんです。彼からは一言もインタビューはとっていませんが、お家までうかがって朝ごはんのところから撮らせていただきました。そういう形で、政治家にはインタビューしますが、一般の人々にはインタビューするというより、生活の一端を撮らせていただこうとしたんです。
『沖縄列島』で一番苦労した場面について、取材の根本的な態度の問題を含んでいるので申し上げます。石垣島に台湾の少女たちが出稼ぎに来ているというシーンがあります。その方たちが、収穫したパイナップルを工場で缶詰に出来るように不要な部分を切り取っていく作業,「芽取り」というんですが、そのシーンを撮らせてもらったんです。たくさんの若い女工さんたちが一斉に並んで立って仕事しているわけですね。そのシーン全体の集合ショットみたいなのを撮ったんですが、これではダメだと思いました。それで一人の女性に焦点を合わせて撮り始めたんですけど、なんだかそれだけでも納得できない。要するに、これだったらTVニュースとか新聞記事の報道に過ぎないじゃないかと思ったんです。報道を馬鹿にするわけじゃないけども、それはTVがやる仕事でしょう。俺はTVの仕事をすれば満足なのかと、自分への問いかけが出てくるわけです。
それでふと思いついて、テーブルの下にカメラマンと一緒にしゃがんで潜ったんですね。そしたら私が予期していたように、仕事をしている若い女性は片方の足に体重をのせて、もう片方の足を休ませるために膝をひらがなの「く」の字に曲げて立ってたんですね。映画ではそのカットが7秒くらい入っています。長い時間の立ち仕事をする女性は必ずそうやるのを、私は子どもの頃から見てきた訳です。例えば自分の母親が、台所に立って沢山のジャガイモの皮をむいてる時もそうでした。それを撮った時に、どういうわけか、これでこのシーンは出来たと思ったんですね。つまり、女工さんたちにインタビューしたりする必要はないんだと。働いている顔のアップとそういう形で足を曲げているところに、彼女個人の生身を強く感じたんですね。あとはどんどんどんどん流れてくる缶詰の缶の音と映像があればいいと思って、切り上げたんです。
映画が出来上がって、ある自主上映をした後に会場に残った人たちの中で、40〜50代くらいのご婦人が手を挙げてこう言われたんですね。今私がお話した7秒くらいのカットについて、「私はあの映像を見て〈もののあわれ〉を感じました」と。僕はびっくりしたんです。〈もののあわれ〉って言葉は複雑な意味を持っている言葉ですが、どの辞書にも必ず書いているひとつの意味は「人生の機微やはかなさなどに触れた時に感ずる、しみじみとした情趣や、心に湧き起こってくる切ないような感情の動き」というようなことですね。ご覧になった通り、映画の中では特に何の説明もしてないです。でも、その女性はそんなことを感じた。そのように言われた時に、やっぱりああいう撮り方をして良かったと思ったんですね。つまりここで台湾から女工さんたちがいっぱい来て、沖縄の人より安い賃金で働きながら頑張って稼いで故国に帰るんだ、というような言葉だけでは言い尽くせない個人の生命の躍動というか、生身の人間性みたいなものをそのご婦人が感じたんだと。「凄いことを言われた」という気持ちがいまだに続いているんです。それが一番大きな体験でした。

『やさしいにっぽん人』に話を移します。つい最近わたしの大学の同級生がこれを観て「無茶苦茶な映画だけど面白かった」ってメールをくれました。この作品もまったく個人的に作った映画ですね。前作と同じプロデューサー、同じスタッフで作った映画です。まあメチャクチャといえばメチャクチャですけど、あの時でなければ出来なかった映画だと思います。個人的な二つの話題があるのでそれをご報告します。
まず当時、私たちは劇映画の作り方を全く知らなかったんですね。私は岩波映画という記録映画の会社にいましたから。劇映画をどう作ったらいいかわからないし、キャスティングもどうしたらいいかわからなかったんです。主人公のユメっていう女性のイメージは脚本に書いたんだけど、女優さんの見当がつかなかったんですね。(主演の)河原崎長一郎さんとはこういう映画を作ろうと飲み屋で話し合っていました。「やさしいにっぽん人」という題名が初めに出来たんです。河原崎さんは決まっていたんですけど、ユメが決まってなかった。どこの俳優事務所に行けばいいかとかそういうことも知らないし、スクリーンで見て知っている女優さんの中で、この人にやってもらいたいっていう人も見つからなかった。それで助監督をやってくれた前田勝弘さんと街中で見つけようとしたんです。今考えると無茶苦茶ですね。
二人で新宿の繁華街に立って2、3日ボケ〜としてたんです。かなり不審な男たちだったと思いますけど。そしたらある日、目の前をすーっと通っていく女性がいたんです。その横顔から後姿を見た時に「あ、ユメが歩いて行く」と思って、一定の距離を保ちながら二人で後をつけたんですよ。ますます危ないですけど(笑)。やがて、彼女がある建物の階段をとんとんとんと上がって消えたんです。そこは実は「現代人劇場」という劇団の事務所だったんですね。それで事務所の人に、「今上がっていった人は誰ですか」って訊いたら、「知らないの? あの人は緑魔子だよ」と。その時はシナリオと名刺を置いて帰ってきたんです。そしたらそれから4、5日経った頃、ご本人から「会いたい」って電話がかかってきたんです。新宿のどこかの喫茶店の二階だったんですが、入ってきた彼女が挨拶して座っていきなり「私この映画に出ます」とおっしゃった。僕らは嬉しかったけどびっくりして、「それは大変嬉しいことですけど、まともなギャラのお払いは……」とまでしかこっちが言わないうちに、「そんなことは考えていません」と彼女は言ったんですね。「お金のために出るんじゃありませんから」って。キザに言えばすごく実験的なシナリオだったし、普通に言えば相当に無茶苦茶なシナリオだったと思うんですが、それを読んで出ますって自分の意志でおっしゃった。事務所がどうこうというのと関係なく、いきなりご本人が出てきて「私出ます」って言われたんです。そんな全く個人的な関係が始まりだったんです。で結局この作品だけでは満足できなくて、次に緑魔子さんを主役にしてもう一本『日本妖怪伝サトリ』っていう、これまたもっと不思議な映画を作っちゃったんですが(笑)。とはいえ、『やさしいにっぽん人』の時は、その人が俳優であるか素人であるか知らないところから始まったというお話です。
もう一つ。この映画には伊丹十三さんにも出ていただいています。作品が完成して最初にできたプリントを「ゼロ号」っていうんですね。その次にそれを修正した「初号」っていう完成作品になるんですが、当時の私たちには「ゼロ号」「初号」なんて二つプリントを焼いてる時間もお金もなかったんで「ゼロ号初号」というのがあったんですね。それでスタッフ全体と俳優さんたちも案内して一緒に観ていただいたわけです。そうしたらその後伊丹十三さんから電話がかかってきたんですね。「ちょっと話したいことがあるから、今銀座にいるんだけど出てこないか」って言うんです。雨が降ってましたけど、「今から行きます」って傘さして出かけて、東銀座の新橋演舞場の近くにあるホテルの二階で二人でコーヒーを飲んだんですね。お疲れさまでしたとか色々雑談を始めて、今だったら会えばすぐにビールからってなっちゃうと思うんですけど、その時は二人とも大真面目にコーヒーしか飲んでないんですね。それで彼と一時間くらい話したんですが、その時に一番私に決定的な印象を与えた、どうしても忘れられないで今まで記憶している言葉があります。彼はこうつぶやくようにこう言ったんですね。「あんな謎に満ちた映画を観られる今の若者は幸せだな」って。それは僕にとっては絶賛されたのと同じことだったんです。もちろん伊丹さんもそういう風に評価してくれたんだと思います。
緑魔子さんの「私出ます」の話も、伊丹さんの意見も、社交辞令でもなんでもない、その人個人から出てきた言葉ですね。 でも、「謎に満ちた映画が観られる今の若者は幸せだな」っていう言葉は、今の日本で通じるだろうかという気もするんです。謎に満ちた映画を観た若者は、そりゃ幸せな顔をする人もいるだろうけど、ほとんどそういう映画は弾き飛ばされるんじゃないかと。それが日本の現状だなっていう印象を僕は持っています。僕は自慢じゃないけど謎に満ちた映画ばかり撮ってきたと思うんです (笑)。昨年苦労して作って公開した『だれかの木琴』という映画があるんですけど、興行成績では『君の名は。』と『シン・ゴジラ』に完全に負けましてね(笑)。
今映画について考えると、伊丹さんに言われたさっきの言葉と全然畑の違うドイツの政治家から聞いた「個人」っていう言葉に結び付けて、物事をあんまりわかりやすく、誰が見てもわかりやすいように映画を作るってことは、少なくとも自分にはできないなあと思ったりするんです。個人個人と言いますけど、だいたい映画っていうのは個人が出てくるわけですよね。ですからそこで言われている個人っていかなる個人かという問題がまた出てくる訳です。ただ謎に満ちていればいいわけじゃない。これはややこしい問題になりますけど、一つだけ例をあげます。例えば今年公開された富田克也監督の『バンコクナイツ』っていう長い映画があります。その映画はものすごく登場人物が多いわけです。誰が主人公とか全然わからないっていう風に見えますが、段々絞り込んでいくんです。そのたくさん出てくる人物が本当にワンシーンしか出てこなくても、その人がそこに存在するっていう印象をはっきり残していくような、非常に優れた映画だと思います。だから、個人がたくさん出てきて、それで個人個人が描かれていますってなるわけではなくて、大勢の人間を描きながらそれぞれの目の向け方の有り様が違うという風に撮られているんですね。最近観た日本映画の中で一番優れていると思いました。
伊丹十三さんに言われたような謎に満ちた映画っていうのは、複雑な問題を扱っているんだけど、そういう映画こそエンターテイメントとして受け入れられるような世界が来てほしいと思っているし、稀にはそういうことが上手くいった場合もあるので、現在の日本映画に失望しているわけでもないんです。優れた若い才能たちはいますが、ただやっぱりお金がかかりますので、監督の好きなように作れる時代ではないと思いますが、映画っていうのはどうしてもなくなるわけにはいかない表現媒体だと思っています。新しい優れた監督は既に出ていますし、これからも出てくるだろうと期待はしてますが、誰にもわかる映画なんていうのを考えないで、好き勝手にメチャクチャやったらどうだろうか、というようなことを酒の席では言ってしまいそうになりますが、最近はそういう事を言うと嫌がられるんで、あんまり言わないようにしています。
そんなわけで大体時間が来てしまいました。あっと言う間ですね。あとこの倍くらい喋ると喋った気になるんですが。(場内笑い)喋り足りない分はまた友人たちと喋ることにして、これくらいにしておきたいと思います。どうもありがとうございました。
