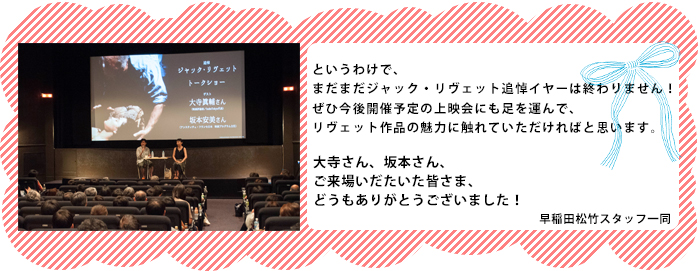大寺:皆さんこんにちは。本日は暑い中、ジャック・リヴェット追悼上映にお越しいただいてありがとうございます。本日はアンスティチュ・フランセで映画プログラムを担当している坂本安美さんと映画の話をしたいなと思います。実は坂本さんとは古い付き合いで、元々カイエ・ドゥ・シネマ・ジャポンという雑誌で初めて会いまして、もう30年近い付き合いかも知れないです。色々なことがあったんですけど、一つだけ言っておかなければいけないなと思うことがあります。僕はいま新文芸坐という所で映画の話をする仕事をよくしているんですが、こういうことをするようになったのは、13年前の秋くらいに当時の横浜日仏学院(現・アンスティチュ・フランセ横浜)でシネクラブをやってトークをしてくれないかと坂本さんから誘われたのがきっかけです。多分それが無かったら僕はこういう仕事をしていなかったと思うので、今日こうやって、人前で坂本さんと映画の話をするのは初めてなんですけれども、感謝の気持ちを皆さんの前で伝える良い機会になってよかったなと思っています。
ともあれ、ジャック・リヴェットと言うのは皆さんにとっても重要な映画作家だと思うんですけれども、「カイエ・ドゥ・シネマ・ジャポン」という雑誌をやっていた私たちにとっても非常に重要な映画作家であるジャック・リヴェット全般をお話しすると同時に、今回わざわざフランスから権利を取得して上映する、今ではなかなか上映することが出来なくなった『修道女』、それから『彼女たちの舞台』、『美しき諍い女』というジャック・リヴェットの代表作と言っていい3本を上映致しますので、それを中心に坂本さんとトークできればいいなと思っています。

大寺:まずは、坂本さんにジャック・リヴェット全般についてお話しいただければなと思うのですが。いかがでしょうか。
坂本:先ほどご紹介頂きました、アンスティチュ・フランセ東京という、元々は東京日仏学院という飯田橋にあるフランスの文化センターでプログラミングをしておりまして、現在は東京だけではなくて各地のそういった施設をベースに、特にフランス映画の上映をオーガナイズしている者です。
大寺さんと出会うきっかけにもなったのが、ジャック・リヴェットたちが創設に関わっていたフランスの映画雑誌の「カイエ・ドゥ・シネマ」の日本版の「カイエ・ドゥ・シネマ・ジャポン」です。そこで一緒に映画についてお話させて頂いたり、書いたりしていた時期があったんですけれども、それからはお互い違うところで映画の仕事を続けていました。 何年か前にジャック・リヴェット監督の『恋ごころ』('01)が公開された頃だったんですが、東京日仏学院で映画も、ドキュメンタリーも含めて彼の全作を上映しました。
そういう大きな特集を開催すると、その時は本当に毎日監督と一緒にいるような気持ちで準備をして、その監督に取り憑かれるのを待つような気持ちで仕事をするので、残念ながらリヴェットに直接会ったことはないんですけれども、その時はリヴェットと共に過ごしたような記憶があります。それが終わってしまった後に、リヴェットが行っちゃったみたいな、とても寂しい気持ちになりました。しばらく経ってリヴェットがあまり映画を撮れなくなっていると聞きました。だけどやはりリヴェットってずっといるような気持ちがしていたので、訃報を聞いた時は本当につらかったですね。ロメールの訃報を聞いた時も辛かったですけど、リヴェットは特に辛かったですね。
何人かリヴェットの映画に出ている知り合いの女優さんがいて、お話を直に聞く機会があったんですが、やはり彼女たちも病気になった事は知っていたけどリヴェットは自分たちとずっと一緒ににいてくれる気持ちがあったと言っていました。それほど女優さんたちといくら離れていても、いつもどこかで見守っていてくれる存在だったと言っていました。自分は女優じゃないですけれども、やっぱり女性を見る目っていうのが他のヌーヴェル・バーグの監督たちと違うというか、本当に女性の身になってくれるという感じですね。そういう監督って正直他にあまりいない。そういう意味で女性としてもリヴェットっていう男性がいなくなった事が痛いですね。

大寺:実はここに来る前に、坂本さんと今日のテーマは男性的なものと女性的なものかなって話をしていたんです。男性的・女性的なものって、すごく当たり前の話でシンプルな事の様だけど本当にこれって大事なんだなって思うんですね。当然、今は多様な性、複数の性があると言わないといけないんでしょうけれど、やはり世の中には男性的なものと女性的なものっていう大きな区別があると思うんですね。その中で物事を考えるというのは私たちにとって大きな問題じゃないかと思うんです。
なぜかというと、今ちょうど坂本さんからリヴェットと共にあったというお話があったんですが、たぶん坂本さん的な共にあり方と、僕たちにとってのリヴェットとの共にあり方とは違うんですよね。この違いというのが凄く重要でとっても面白い。今回上映する3作品を観直してきたんですけれど、その時今まで気づかなかった、それこそ坂本さんたちがおそらく最初から見ていたであろうリヴェットが、見えてきたような気がしました。
僕もリヴェットとは会ったことはありません。ただ、「カイエ・ドゥ・シネマ・ジャポン」が誕生した頃というのは1990年くらいですね。あの頃私たちにとってリヴェットというのはすごく大きな名前でした。 ヌーヴェルヴァーグにはゴダールとトリュフォーというスター監督がいたんですが、ただこの二人だと華やかでスターすぎると言いますか、もうちょっと自分たちにとって身近な存在っていうのを求める部分があったわけですよ。ロメールも紹介され始めた頃だったんですけど、ロメールはリア充というかお爺さんイケイケで凄すぎというか(笑) 割と華やかで、あれにはなれないという感じがありました。もちろん素晴らしい作家なんですけれども。
そうした時にリヴェットという人はまず当時呪われた作家と言われていたんですね。なぜかというとまず作品が日本公開されていない。今日上映された『彼女たちの舞台』が91年に日本で初公開されたリヴェット作品ですね。1980年代後半は全く公開されてなかった。しかも長大な作品や、実験的な作品ばかりを撮ってフランスでも全然ヒットしない。公開もしないしヒットもしないよく分からない人だと。難解な映画作家だという風に言われていました。なのでそういうイメージが非常に強かった。
でも同時に彼は映画批評家としても非常に高名でした。とっても素晴らしいものを書くんですね。彼はタイトルだけでこっちの心を鷲掴みにするんですよ。「ハワード・ホークス(★1)の天才」とか。なにそれって思うじゃないですか。リヴェットって最初の一文とかタイトルのつけ方とかが抜群に上手くて。どう人の心を掴むかっていうと、この前フランス映画祭で上映した『パリはわれらのもの』(61)もそうだと思うんですけれども、ある種の"男の子"性があると思うんですね。つまりリヴェットの映画は、謎、陰謀、秘密結社っていうのが常に出てきますよね。そういうのってある意味男の子的なんですよ。隠れ家作ったり、秘密結社とかフリーメイソンとか、世の中には陰謀があってとか。男の子ってそういう話が大好きなんです。そういう琴線にすごく触れてくるわけですね。彼の映画っていうのはまずそういうところから私たちの心に入ってくるんですよ。
で、1991年に公開された『彼女たちの舞台』から急速にリヴェットブームが日本で起きるんですね。そのあと『美しき諍い女』、『ジャンヌ』二部作('94)が連続公開されたり、特集も行われたりしました。90年代のミニシアタームーブメントの中心的人物の一人になったんですけれども、その時の彼っていうのは『セリーヌとジュリーは舟でゆく』('74)などの、ああいうイメージ。女の子が出て、ファッショナブルで、いわゆるガーリームービーみたいな文脈でとらえられていた。これって当時の男の子のシネフィルであった私たちにとっては、上手いことやったなって感じだったんですよ。つまり、秘密結社とかアジトとかが大好きなシネフィルの男の子っていうのは、そういう自分に不満があるわけですね。なんか自分は大人じゃないんじゃないかと。このままじゃ世界が分かってないんじゃないかと。それをなんとか越えなきゃいけないときに、主にふたつ道がありまして。ひとつは、悪くなること。もうひとつはチャラくなることなんですよ。イケイケになって女の子とチャラチャラして、楽しそうにやる。たぶんその当時のリヴェットっていうのは、私たちにはそう見えていた。もともとシネフィル出身で難しいこととか言ってたのに、ベルナデット・ラフォンとかアンナ・カリーナとか、可愛い女の子と一緒に映画撮ってて、すごくうまい具合に何かカジュアルになってウケたなと。ポップになって日本でもブームになったなと思ってたんですけども。
今回観直してそれってすごく浅い見方だったなと、リヴェットってそんなもんじゃなかったんだなと気づいたんです。たしかに今回の3本の中で『彼女たちの舞台』はそのレベルでもとらえられなくはないかもしれません。ある程度ゲーム性の強い映画なので、そういう風にも解釈できない事はないと思うですけれども、やっぱり『美しき諍い女』はそれじゃ絶対撮れない映画だと思いました。『美しき諍い女』って本当に女性を見る眼差しであったりとか、女性をいかに撮るか、すべての女性の中にある「美しき諍い女」をどうすくい出すか、どう見つめるか、どう自分の描線につなげるかと真剣に考えた映画で、これはシネフィルの男の子的なものでは到底到達できない作品だなと、今回しみじみ感じました。
坂本:すごく男の子目線から語っていただいて、なるほどと思うお話でした。リヴェット自身も、映画を作ることっていうのは、常にゲームの中に、遊戯の中に自分を置くようなことで、いわゆるアメリカとかヨーロッパでのインディアン遊びや西部劇ごっこみたいなことをずっとやっているようなものだ、みたいなことを言ってたりもしています。そういう意味でジャン・ルノワールが言っているような、いつも遊戯性の中に身を置いて映画を撮ることの大事さみたいなことをリヴェット自身も語っていたと思うんです。そういった男の子が好きそうな部分に反応したというのは、あ〜なるほどなって思って聞いていました。
私もやっぱり『彼女たちの舞台』が(リヴェット作品を観た)最初だったと思うんですけれども、観ていてウキウキして、女の子であることがすごく誇りに思えるような感じでした。これからご覧になる方もいるのであまり言えないんですけれども、ほとんど女の子の映画なんですよね。その中にも出てくる男性が重要な役ではあるんですけれども、女の子たちだけで世界を作ろうとしているかのようなところがあって。その女の子たちが一緒にいることで何か生まれてきたり、遊んだり、あるいはぶつかったりとかする。こんな映画なかったよな〜って思って、女の子であることがこんなにウキウキできるんだみたいな感じでした。
ところが、今回こちらでお話させていただくってこともありますし、亡くなったという追悼の意味も込めて観直してみると、映画が持ってる深みっていうか、見れてない部分があったなというのはわたしも感じました。特に『美しき諍い女』は、当時どうしても表面的な部分で、エマニュエル・ベアールがほぼ3時間以上、裸でモデルとしてポーズをとっていて、そういう部分にどうしても最初に目がいってました。今回観てもその面白さは感じたんですが、それ以上にリヴェットの映画の中に常にあるテーマである「死」のテーマですとか、終わりゆくものについてのテーマとかが、年齢がそういう年齢に達してきたのか、すごく痛いほど感じられましたね。
(★1)ハワード・ホークス…(1896‐1977)アメリカの映画監督。代表作『暗黒街の顔役』『三つ数えろ』『リオ・ブラボー』

大寺:今回の上映作品は年代順だと『修道女』、『彼女たちの舞台』、『美しき諍い女』っていう順なんですけれども、たぶん話し始めるのには坂本さんの方から触れていただいた『彼女たちの舞台』というのがリヴェットの入り口として良いかなと思います。日本で一番最初に公開された作品ですし、やっぱりこの作品はゲーム性みたいなものが強い方、遊戯的なタイプのリヴェットの作品だと思うので。
これが公開されたとき強い思い出がありまして、1991年だったと思うんですけれども、ほぼ同時期に公開されたドワイヨンの『恋する女』('87)っていう作品があって、それに『美しき諍い女』にも出ているマリアンヌ・ドニクールが主演していて、演劇学校の女の子たちをたくさん集めて撮っていて、すごく似ていると思ったんですよ。女の子たちを配してゲームのような、順列組合せ的なそれぞれの関係性で映画を紡ぎだしていくと。ドワイヨンとリヴェットって考えれば考えるほど似ているところがあるんですよ。まず演劇への興味。演劇と人生の関係性ですよね。今回観直して初めて気づいたんですけれども、『美しき諍い女』っていう作品は年老いたカップルと若いカップルの二組の世代の違うカップル、そこにもうひとり画商の人間の5人の関係なんですけれども、この関係ってジャック・ドワイヨンの『三人の結婚』('10)と全く一緒なんですよ。あの映画は演劇をテーマにしているので、『美しき諍い女』でいう画家のかわりに劇作家が出てくるんですけれども、彼の別荘のような大きな家でほぼ全編展開するってところもそっくりです、意識的か無意識か分かんないけれども。ドワイヨンとリヴェットって撮影監督もよくかぶりますし、とっても似たような作家であると思うんですよ。ただやっぱりだからこそ際立った個性がある。ドワイヨンにあってリヴェットにないもの。そういうものが比較から見えてくるんじゃないかと思うんですけども。
リヴェットの映画って女の子がいて、女の子であることが誇らしい、坂本さんなんかもそう見ると思うんですよ。だけど、僕ら男の子目線だと、そうじゃなくて女の子はなぜあんなチャラチャラ出来るんだろうと。映画の中で女の子がチャラチャラしているだけでは普通映画にならないわけですよ。それを映画として形式化しているものは何だろうと考えるのが貧しい男の子なんです。この映画ではあの四人組ですね。彼女たちがいろんな役割を交換しながら物語を紡ぎだしていけるのはなぜかというのを男の子は考える。まず、全体を支配しているビュル・オジェ演じるコンスタンスという演劇学校の先生がいることですよね。もう一方に謎の男トマがいると。この二人がいることによってこの映画が形式化されていく。これがすごく面白いなと思いますね。
坂本:リヴェット自身がインタビューで公開当時に言ってたことなんですけど、みんなで一緒に朝ご飯を食べたりとか、夜過ごしていたりだとかしているうちに、そこには常にみんなの心配事や悩みが出てくる。そんな女の子たちを見ているだけで楽しいんだけど、ただやっぱりそれだけでは映画は回っていかない。だから、一人一人になるシーンを必ず設定するんですね。その時に登場人物の頭の中が見えてくる。みんなで暮らしていながらも、それぞれの頭の中や背負っている覚悟、苦悩というのがもちろん違うっていうのが見えてくる。そのちょっとずつ違うその4人の個性をスバッと的確にとらえる力がやっぱり凄いですよね。
ポルトガル人の有名な女優マリア・デ・メディロスの妹のイネス・デ・メディロスが出てきますね。彼女なんかは「国で相当スキャンダルを起こしてきたのよ」というセリフなんかがあるんです。たぶん命を落したかもしれないようなこともあったと。あとアンナという黄色い服を着ている彼女なんかも、実は妹が行方不明で彼女の名前を偽名として使っているらしいことがわかる。
で、映画の最後に出てくるメッセージがあって、その瞬間ウッって思うというか。いかにこの映画がチャラチャラした女の子の映画だけではなくて、ある意味ものすごく政治的な映画であるかということがわかるんです。まぁそう考えると処女作からものすごく政治性を持っている。でもリヴェットはものすごく頭のいい人だし、ものすごく優美な人だからそういった政治性を表に出さない。先ほどドワイヨンのお話しをなさってましたけど、私は最近の日本の黒沢清さんに近い部分があるのかな、なんて思ったりしています。
大寺: その話も今日はしたいとわたしも思っていました。
坂本:あからさまに出さないんですよね。ものすごく政治的というか、つまり自分の生きているこの世界に対してものすごく意識して作っている。だからこの『彼女たちの舞台』の時代というのは、たぶん政治的にもまだ暗黒な部分があった時代だと思うんですよ。だからこの中に出てくる政治的な要素だとか、最後のメッセージっていうのはそこにつながっていく。
大寺:要するにリヴェットを語るときにさっきから言ってきた、形式性だとか遊戯性だとか、都市に陰謀があってとか、そういう映画史の文脈をいわゆるフリッツ・ラング(★2)的とよく言ったりするんですけど。それと同時にリヴェットにはルノワール的な部分、豊かさに開かれた部分というのと、やはり現実主義というのが間違いなくあると思うんです。リヴェットの映画を観るのは楽しい、しかし、この楽しさと現実はどう関係があるのだろうということを考えざるを得ないんですよ。それは明らかに意識して撮っていると思っていて。『彼女たちの舞台』の中ではよくわからない非人称的な列車の窓から撮った外のシーンが何回もインサートされますよね。あれよくわからないですよね。
坂本:そうですね。最初のころは通勤しているシーンくらいに思うんだけど、最後の方はリハーサルのシーンにパッとインサートされたりするんですよね。
大寺:あれはほんとにわからないですよね。だから、だた都市がいきなり侵入してきたような。たぶんそれってこの映画と現実との距離感も関係があると思うんですよ。 例えばオープニングのシーン。女の子が本を読んでいて、おそらく本の世界にいて無音なんですよ。で、本を閉じてコーヒーを飲み終えるとだんだん外の雑音が聞こえてくる。それで彼女がカフェを出て雑踏の中に入っていって、そのまま演劇スクールの建物に入っていきなり演技を始めると。そこでいきなり現実と虚構、あるいは物語の世界に入っている私たちと現実というのがほんとに見事に重ねられる。オープニングだけで傑作感がすごい。それとほぼ同じことを『美しき諍い女』でも繰り返していると思うんです。だから現実との距離感ってすごく大事だと思います。
『彼女たちの舞台』で楽しいシーンがありまして。色の違うコーヒーカップを頭にのせて裁判官の役を演じたりだとか、みんなで判事の役を演じたりだとか役割を交換していく。いわゆるゲームの様にくるくると役割を交換していく。そういう遊戯的な側面を許す女性だけの劇団、女性ばかりが住む共同住宅、いわゆる女の園があって、そういう場所っていうのはちょっと現実と離れているんですよ。ただそこに突然列車のインサートシーンが入ったり、抽象的な場所で、抽象的なゲームを撮っているかのように見えるんだけれども、その一枚裏には間違いなく現実がある。
坂本:そうですね。だからそういう現実を敢えてあからさまに見せるような事はしなくて、音で見せたり列車のシーンで見せたりだとか、ほんとに混沌とした世界が周囲に広がっているという事を少しづつ見せるくらいなんですね。
(★2)フリッツ・ラング…(1890−1976)オーストリア出身の映画監督。ハリウッドでも活躍した。代表作『メトロポリス』『M』『死刑執行人もまた死す』


坂本:そういった意味で長編二作目の『修道女』でお話しすると、これはリヴェット自身の持ち込んだ企画ではなくて、ゴダールの作品なんかも生み出しているプロデューサーのジョルジュ・ド・ボールガールの企画なんですが、今回見直して、以前よりも本当におもしろいな、すごい作品だなと思いましたね。この作品はほとんど外のシーンが無いんですけど、なんかものすごい風の音がするんですよね。
みなさんご存知かと思うんですけど、本作は公開されるまで本当に大変なことになって。ジャン・グリュオーという脚本家の言葉を借りると、いまなんかよりもっといい子ぶったやつらが多い世界だったから、カトリック系の学校の両親だとかが反対して結局公開が遅れてしまった、という作品です。この作品なんかも修道女という女の人たちだけのところにアンナ・カリーナ演じるスザンヌっていう、自分からその場所に入りたいと思っていなかった女性が入ってきて、特に何かものすごく政治的にマニフェストしようと思ったわけでなく単に正直にいようと思ったことで、外の世界をガッと入れちゃう。そうした、虚構の世界と現実との関係っていうのを既にこの作品でもリヴェットは意識してたのかと思います。
大寺:オープニングが誓願式のシーンで、修道女は一般の人と関わっちゃいけないんで、黒い格子に囲まれてる。黒い格子っていうのはすごいリヴェット的な視覚的モチーフだとぼくは思ってるんですけど。幽閉っていう主題はリヴェットにとってとっても大きいものですね。
『修道女』の原作はドニ・ディドロで、この人は『ブローニュの森の貴婦人たち』(★3)の原作も書いた小説家さんなんですけど、この作品もブレッソンを思わせるところがちょっとあると思います。ブレッソンも『罪の天使たち』とか、修道女たちを描いた作品があります。やっぱりブレッソンの作品とリヴェットの作品はまず似ているところがあって、それは、聖なるものというか、修道女といった囚われの女性を扱っているということ。それとあともう一つは、さっきもいったように風の音が凄かったりとか鳩の出す音が凄かったりとか、音響がかなり人工的ですよね。これはリヴェットの初期の特徴だと思います。これは『美しき諍い女』ぐらいまで続いていて、雷の音がいきなり鳴り響いたりとかします。ああいうのって、とても人工的だと思うんですよ。それがだんだん自然主義的になっていくんですが。
『美しき諍い女』で凄いのは、あれは特に吹かしたわけじゃないだろうに、物凄い風が吹いている。どうやって撮ったんだろうっていうぐらい、自然をわが物にしているというか、本当に起こったことを自分の力にしてしまえる。おそらくそういうことだと思うんですけども。けっして人工的にやってないんだけど、映画の中で非常に強い意味を持っている。 『修道女』あたりはまだそれをかなり人工的にやっている。それがブレッソンに近いところだと思います。ブレッソンだと『ブローニュの森の貴婦人たち』とか『ジャンヌ・ダルク裁判』(62)などは主人公が受難を受けている、パッションの映画ですよね。情熱=受難というゴダール的な意味合いでの「パッション」を描いている。
ただ、今回初公開以来初めて『修道女』を観直して凄く面白かったんです。初公開のときには、女性を主人公にした小説的な物語系のリヴェットかなと、それぐらいの印象だったんですが。まず面白かったのが、これも男の子的な、形式から入っているところがあるんですけど。このアンナ・カリーナ演じる主人公は何を考えているんだろうっていうのが最初わかんなかったんですよ。たしかに受難なんだろうと。お母さんに認めてもらえなくて、あれは不倫の子で、不倫って常にリヴェット的な主題ですよね。不倫の子として生まれて家族に疎まれて、修道院に入れられて、そこが好きじゃなくて出たいんだけどっていう、そういう話なんですけど。彼女は何を考えている人なんだろうと。純真な人で、こんな場所に居たくなかったって、それはわかるんだけど、個人的になにを考えているのかってことは初め観た時には全然わかんなかったんですが、今回観直して彼女はおそらく鏡なんだろうと思ったんですよ。つまり、彼女が何を考えているかじゃなくて、彼女がいることによってその周りが映し出される。
坂本:そうですね。
大寺:まずは家族が映しだされる。家族の非情さとかその絆の希薄さといった面。次は修道院に入って、最初はいい修道長さんがいたけど、その人がすぐ亡くなっちゃって、凄く厳しい人になっちゃうんですよね。そういう非常に戒律の厳しい修道院っていう共同体。そこで魔女扱いされたりして、いたたまれなくなってなんとか別の修道院に移るんですけど、そこは最初はいい修道長さんかなっと思ったら、今度は逆なんですよね。ある種の享楽主義みたいな感じで、同性愛的ニュアンスも入ってくるんですけど。彼女はここではチヤホヤされて逆にいたたまれないと。彼女はそんなふうに様々な悲劇に巻き込まれていくんだけど、彼女自身が何かしているわけじゃないんですよね。
坂本:そうなんですよ。ほとんど常に受け身で、自分から誓願して入ったわけじゃないから。自分の意志でやったことじゃないことは受け止められないってだけなんですよね。だから彼女がいることで、いろんな人たちが逆に見えてきちゃう。人間関係とか、ひいては当時の社会のシステムだとかが見えてくる。それを演じる素質を持っていたのが、アンナ・カリーナです。当時ゴダール夫人でまだ一作か二作に出てるぐらい、たぶん『女と男のいる舗道』('62)の後すぐくらいだったと思います。当時のリヴェットの言葉を借りると、「まるでグリフィス映画に出てくる女優のような優雅さを顔に湛えている女優」。
大寺:目がパッチリしてるからかな。
坂本:受難を受けてもみすぼらしくならないというか、常に品格をもっているというか。
大寺:『女と男のいる舗道』の有名なシーンで『裁かるゝジャンヌ』(★4)のファルコネッティを観ながら涙を流す素晴らしい場面がありますね。ファルコネッティを見ている彼女もまた古典的な美しさを湛えてますよね。
坂本:そういう古典的な美しさを持った女優をリヴェットは探してたんでしょうね。さっき、打ち合わせしている時に大寺さんとも話したんですけど、リヴェットは一度一緒に仕事をした女優さんには忠実ですよね。このあと29年後にもう一回アンナ・カリーナを出演させてるんですよね。『パリでかくれんぼ』('95)という作品で、ロランス・コートという『彼女たちの舞台』のクロードという男の子っぽい女の子を演じた女優の、お母さんかも知れない役を演じてるんです。そういう風に、女優さんとの関係を本当に大切にしてきた監督で、他のヌーヴェルバーグの監督だとロメールなんかも同じ女優さんを出してますけど、その女優さんの生きてきた人生とか、演じてきた役柄へのオマージュとかを持って出してる感じがするので、出てくる瞬間とても感動するんです。
大寺:さきほど、同じ女優を何度も使うという話をしていただきましたけど、『彼女たちの舞台』のロランス・コート、すごく良いですよね。
坂本:彼女の出演作でたぶん一番いいでしょうね。
大寺:特に裁判所ごっこをするシーンの彼女は、ほとんどサイレント映画の女優みたいですね。
坂本:それこそ劇中の彼女の部屋にはチャップリンのポスターが貼ってありましたね。先日ジャンヌ・バリバール(★5)という女優さんが来日されて、アンスティチュ・フランセでもこの映画をやったので一緒に観てたんですよ。そうしたら「ロランス・コートほんとにいいわねえ。女優ながらに惚れ惚れする。」って言ってました。「最近あんまり出てないからどうしたのかしら。」なんて言ってましたけど。『彼女たちの舞台』ではたぶんバイセクシャル的な役ですけど、途中で男に恋をしてしまうあの瞬間から非常に女の子っぽくてかわいらしくなるあたりがいいですよね。
大寺:そうですね。あとこの映画、ちらっとイレーヌ・ジャコブ(★6)が出てるんですよね。
坂本:そうですね。まだキシェロフスキ(★7)の作品に出る前ですよね。
大寺:まだぺエペエの頃ですよね。だけどいいんですよね。
坂本:ほとんど台詞はないんですよね。でも彼女がいるとつい見ちゃいますよね。
大寺:画面の中心がそこにいきますよね。「あ、イレーヌ・ジャコブだ」って気づきますよね。それはすごいなと思ったんですけど。
あと、『修道女』の話でヒロインは周りを映しだす鏡だって話をしましたけど、これって典型的なリヴェットのパターンの一つだと思うんです。ただ『修道女』で映しだされるのは周囲の女の園ですが、そういうものを描くのが楽しいってこの作品で気づいたのかなって気がしますね。
坂本:そうかもしれないですね。なんか本人は、自分の企画じゃなかったし、検閲の問題でものすごく騒ぎになってしまったこともあって、正直あまり楽しい映画じゃなかったって言っていますが。
で、この後に撮るのがジャン・ルノワールについてのドキュメンタリーで、当時アシスタントだったユスターシュ(★8)と二人で、映画を撮ることの楽しさをもう一度思い出したいっていう気持ちでずっと撮ってたっていってましたけれど。でもなんだかんだで『修道女』の中にもリヴェット的な要素ってすごいあるし、ものすごく面白い作品ですよね。
大寺:特に思ったのが、後半に出てくる方の院長さん。享楽主義的な。彼女は物語的には悪役なんですよね。悪役というか、堕落してる女性っていう役なんだけど、でもいいですよね。
坂本:そう! だって、アンナ・カリーナのことを本気で好きになって苦しんでいく。今考えれば同性愛っていうか、当時は罪ぐらいに扱われてますけど、そういうことを抜きにすれば、単に恋をして苦しんでいる女性がいるっていうか、その恋をしていく姿がずっと描かれているっていう。
大寺:と思うんですよ。だからあのシーンっていうのは多分撮ってて楽しかったんじゃないかなって気が正直するんですよね。
坂本:そうですよね。そう思います。
大寺:そのへんで、こういうの自分にむいてるって思ったのかな。そこで今までの形式的に、多分『修道女』って言ってみれば、発想的にはある種フーコー(★9)的というか、彼女を中心に鏡として映し出されたさまざまな共同体を撮るっていう形式にはなってると思うんですけど、そういう女の子が出てきて楽しそうにしてる、仲良さそうにしてるという。なんか関係性ですよね。つまり関係性の映画っていうのは男の子の発想の中にはないんですよ。
坂本:そうなんですか。
大寺:そう、ないんですよ。男の子って基本的に妄想なんですよ。ぼくが男の子を勝手に代表するのもあれですけど(笑)。
(★3)『ブローニュの森の貴婦人たち』…(1944/フランス)ロベール・ブレッソン監督作品。
(★4)『裁かるゝジャンヌ』…(1928/フランス)カール・ドライヤー監督作品。ルイーズ・ルネ・ファルコネッティ主演。
(★5)ジャンヌ・バリバール…(1968−)フランスの女優。リヴェット作品では『恋ごころ』『ランジェ公爵夫人』に主演している。
(★6)イレーヌ・ジャコブ…(1966−)フランスの女優。代表作『ふたりのベロニカ』『トリコロール赤の愛』
(★7)クシシュトフ・キェシロフスキ…(1941−1996)ポーランド出身の映画監督。代表作『デカローグ』シリーズ、『トリコロール』三部作
(★8)ジャン・ユスターシュ…(1938−1981)フランスの映画監督。代表作『ママと娼婦』『ぼくの小さな恋人たち』
(★9)ミシェル・フーコー…(1926−1984)フランスの哲学者。著作「言葉と物」「監獄の誕生」

大寺:すごく大事だと思うのは、『美しき諍い女』って妄想の映画って言うか、決して存在してはいけない傑作の映画だと思うんです。結局誰も見ていない、観た人間は死に呪われるっていうか、黒い十字架にかけられてしまう。この辺の話っていうのは以前、横浜日仏学院ってところでやった講義をまとめた「現代映画講義」って本を十年前ぐらいに出したんですけど、その中で批評家の佐々木敦さんとかなり詳しく話してまして。この映画は「美しき諍い女」っていう不可能の中心、キャッチ−な言葉を使えば否定神学的な、あってはいけない、ありえないもの、あるいはないことによって全てがありえるようなものを扱っていると。つまり、完全な傑作とか、完全な天才というのは世の中にはあってはいけない、あるいはありえない。だけど、あるということを信じることによって、みんなが努力したりとか様々な人がその周り集まってきたりとかする。そういう構造っていうのがあると思うんです。
そういうのってリヴェットの大きなモチーフだと思うんですよ。なにかあり得ないもの、負の中心って実は神の裏側なんですよ。神っていうものはポジティヴなもので、その周りに人が集まってくるものだとしたら、否定神学っていうのはなんにもないブラックホールみたいなものがある。だから『美しき諍い女』っていうのもそういう映画で、かつて存在しなかった、10年前に描こうとしたけど描けなかった絵をもう一回描こうとする。で、描いたんだけど最終的にそれを見た人間はモデルと、おそらくそれが何であるかわからない子どもしかいないと。だから結局、そういうものはありえない。映画の中でもスクリーンには映されない。そういうものをあることにして、この『美しき諍い女』っていう様々な人の物語が成り立つと。そのような形式の総決算としてリヴェットは撮ったのかなっていう気がするんですけど。
ただ、そういうのは男の子の発想な訳ですよ。つまり妄想。なにか決定的もの、神みたいな凄いものがあって、それによって世の中は成り立つんだという発想ですね。それって、さっきもチラッとお話ししましたけど、黒沢清監督もわりとそこに近いところがあると思うんですよ。まだ日本で公開されていない今度の新作の『ダゲレオタイプの女』(’16)っていうのもそうで、なにか写ってはいけないもの、それは黒沢清の場合は幽霊的なものと結びついてきますけど、そういう絶対的なものが世の中にはあるんだと。あるいはあると妄想する。それによって、あるかないかはともかく、それを信じた人たちの映画が出来ると。それがリヴェットの大きなモチーフだと思うんですね。たぶん僕が前に『美しき諍い女』を観た時そういう作品だと思ったと思うんですけど。今回観直してみて、ほんとにインパクトが強かったのは、「美しき諍い女」っていうものを画家が信じて、モデルから引き出そうとしている2人の女性。つまりリズとマリアンヌっていう。この2人の女性との関係性ですよね。これがものすごくリアルで生々しいなと。この生々しさっていうのはいわゆる男の子的な映画の発想からは出てこないと思うんですよ。
たとえば、黒沢清っていう人も似たような主題を選んでるんですけど、これは黒沢清への批判ではなく、リヴェットとの違いっていうことでいうと、黒沢監督はあくまで男の側の作家だと思うんですよ。『ダゲレオタイプの女』もある意味で妄想の映画です。それに対して、『美しき諍い女』っていうのは男性と明らかに女性がいるんですよね。
坂本:そうですね。全くの他者として屹立してますね。
大寺:特に後半になるにしたがって、モデルの彼女の存在感がどんどん大きくなっていく。
坂本:そうですね。ご存知のようにリヴェットは撮影が進むにしたがってシナリオを書いていくんです。本作でもアサスという南仏の館のある部屋で共同脚本家のパスカル・ボニゼールとクリスチーヌ・ロランとともに夜は寝ないで次の日のシナリオを書いて撮影が進んでいったと。エマニュエル・ベアール自身がインタビューで語ってるんですが、彼女が画家に対して反発していくことに快楽を覚えていくという展開は、おそらくリヴェット自身は撮影前にはあまり予期していなかったらしいんです。現実の彼女のリアクションにリヴェットが答えて物語に反映させていって、結果として最初に想像していた作品の形と違うものになっていった。たぶん、その過程はこの作品に限らないと思うんですけど、そのワーク・イン・プログレスのスリリングさを見ているとこちらもキリキリとしてきます。それが二重三重なんですよね。映画の中の画家のフレンホーフェルとモデルの関係と、画面には出てこないリヴェットとベアール、そして他の俳優たちとの関係と。そういう意味では先ほど大寺さんがおっしゃったようにある意味で、本作はリヴェットの頂点といえると思います。もちろん、その後も素晴らしい作品を撮ってますけどね。
大寺:ほんとに映画史的な傑作だと思いますね。4時間の間、全くダレないで緊張して観ていられる。それに、ひとつの形式を作ったっていうのも大きいと思います。さきほど安美さんがおっしゃられたようなワーク・イン・プログレスの映画、究極の絵画を作り上げるプロセスの映画を本当にそのプロセスとして描いたと。単に「凄い絵を描いてますよ」と記号として見せるんじゃなくて、様々な画材を使いながら絵を描くプロセスが映画を成り立たせている。それがすごく長い間続いていく。ただ今回観直して、自分が歳をとったのかペンがスケッチブックの上を走っていくカリカリしてる音が、黒板をひっかいた音みたいで正直ちょっと耐えられなかったんですが(笑)
坂本:私はすごく心地よかったですよ(笑) お疲れだったんだと思います(笑)
大寺:そうかもしれない。まあ、身体性の映画であることは間違いないですよね。
坂本:そうですね。あと、リヴェットは、例えば『修道女』はほぼワンシーン、ワンカットの作品ですよね。『美しき諍い女』も長回しが多いながらも、やはりモデルと画家の作品であるからどうしても切り返しの映画でもあって、その切返しという映画の根本的な構図に対するリヴェットの挑戦というのがすごいなと。“ここで切り返すんだ”って。そのひとつひとつがモデルと画家の緊張関係そのものだった。
大寺:あそこがすごいんですよね。ふたりがお酒を飲んで楽しくなってたのに、バタッと倒れた時に「今そこ動かないで!」ってなる。そこまで楽しいシーンなんですよね。ずっと緊張関係にあったふたりで、フレンホーフェルはマリアンヌにほとんど拷問してるんですよね、耐えられないような辛い格好をさせていて。ほとんどペドロ・コスタ(★10)的というか(笑) そういう非常に身体性の強い映画のなかで、あそこだけ楽しそうにしている。ところが、バタッと倒れた瞬間に、「いまこの角度だ、この瞬間だ!」と言って。そこで持ってきたキャンバスが、(妻の)リズを描いたキャンバスなんですよね。あそこ恐ろしいですよね。
坂本:いや、ほんとうに恐ろしい映画ですよ。
大寺:要するにあそこで、若い女性をモデルに楽しそうに描いていて、「今この瞬間が素晴らしいんだ、決定的瞬間を描けるポーズなんだ」といって、持ってくるキャンバスが、以前、妻をモデルに途中まで描きあげた未完の傑作で。そのキャンバスを塗りつぶしながら絵を描くと。これもうほとんど地獄ですよね。よくやりますよ。
坂本:ですね。ジェーン・バーキン演じる奥さんのリズが後半はほぼ主役のようになってくる。“何かを葬ること”というのが、単に何かを終わらせるということではなくて、葬ることも生きることの一部だというのを映画の後半は怖いくらいに描いてますよね。
大寺:リズもその絵を見るんですよね。映画のなかでは決して姿を見せないその未完の傑作を見て、彼女はその絵の後ろにスッと回って黒い十字架を書く。フレンホーフェルがそれに気が付いてすごいショックを受ける。そのあとふたりが夜にベッドで寝ているシーンになるんですけど、ふたりの上に窓枠の黒い影が映る。十字架が掲げられているように見えるすごい印象的なシーンがあるんですよ。後半のテーマは明らかに“死”ですよね。
坂本:そうですね。そこまで言っちゃっていいのかな(笑) でもこういう風に語られていても、そこからはみ出てくるたくさんの発見がある映画なので、これから初めて観る方も大丈夫です。
大寺:そうです。観直すたびに発見のある映画ですので。あとこの作品ってほかにディヴェルティメント版っていう再編集版があるんです。日本ではDVDにもなってないみたいですけど。それもリヴェットっぽいですよね。
坂本:全然違う映画になっていますね。
大寺:オリジナル版は創作のプロセスに中心があるんですけど、「ディヴェルティメント」のほうは人間関係にポイントを置いていて。それこそ『彼女たちの舞台』みたいに、人と人の輪が出来ていくような、マックス・オフュルス(★11)の『輪舞』(50)的なことをやったのが「ディヴェルティメント」だと思います。ちなみに『美しき諍い女』でこれまで話に出てこなかったもう一人の登場人物のバルタザールという男ですが。あの人、実はリズの愛人ですよね。
坂本:そうですね〜。まぁ、あまり語っちゃうとあれなんですけど…不思議な存在ですよね。いきなりバタンと倒れたり。その意味とか考えちゃいますよね。
大寺:今回気づいたことがあって、普通に見てたら気づかないと思うので言っちゃいますけど、彼、乾杯の時に「ルハイム」っていうんですよね。ヘブライ語です。しかもユダヤ系の英語です。つまり彼はユダヤ人ですね。彼とリズは英語圏なので何か深い関係があったんじゃないかと。バルタザールは画商なんでいわゆるお金に結び付けられた人物なんですが、リヴェットの映画って、その中で不意に現実が現れる時、お金の話が出てくるんですよね。『彼女たちの舞台』でも途中で、入学したいという子が出てくるんですけど、「お金が払えないから入れない」と。あそこも不思議ですよね。
坂本:急に現実的なものが突き付けられる瞬間がありますね。
大寺:やっぱりそれはお金の問題の大きさというか、リヴェットにとっても大きかったからなんですかね。
ともあれ、本日の2本の作品は非常に対照的ですよね。ひとつはものすごく物語性の強い、ディドロ原作のもので。もうひとつは原作の無いある意味オープン・エンドの作品。
坂本:そしてこの『彼女たちの舞台』から『美しき諍い女』が生まれるんですよね。
大寺:そういう台詞が出てきますよね。だから、リヴェットの作品って、いろんなところに別の作品が入り込んでいるんですよね。
坂本:そうですね。ジャック・ドゥミ(★12)なんかは明白にそれがあるんですけど、リヴェットはこうしてもう一度作品を観直していくと、いろいろな鍵が落ちていて、その鍵でまた他の作品が新しく観られるようなところがありますね。女優さんに対しても、例えばエマニュエル・ベアールを『美しき諍い女』で撮って、その十何年後にもう一度彼女を起用する(『Mの物語』('03))時に、やはり『美しき諍い女』のマリアンヌ役を含まれた上でのベアールが見えてくるという。それって素晴らしいことですよね。
大寺:すごいですよね。ドゥミとかマルセル・パニョル(★13)とかっていうのは、描く世界が様々に関連している。リヴェットも好きな作家のバルザックもそうですよね。でもリヴェットは彼らと同じようなことをしているように見えながら、もっと映画そのものや女優であるとか、撮っている私たち自身が地続きにあるという。
坂本:『彼女たちの舞台』にはビュル・オジェが出ていますけど、実はこの映画ができる数年前に彼女は娘であるパスカル・オジェ(★14)を亡くしているんですよね。リヴェットのなかでは、彼女にこの役を演じさせるにあたって、『北の橋』('81)で共演したパスカルの影を映画に存在させているというふうに言っていましたね。
(★10) ペドロ・コスタ…(1959−)ポルトガルの映画監督。代表作『ホースマネー』『コロッサル・ユース』
(★11) マックス・オフュルス…(1902−1957)フランスの映画監督。代表作『忘れじの面影』『歴史は女で作られる』
(★12) ジャック・ドゥミ…(1931−1990)フランスの映画監督。代表作『シェルブールの雨傘』『ロシュフォールの恋人たち』
(★13) マルセル・パニョル…(1895−1974)フランスの小説家、劇作家、映画作家。
(★14) パスカル・オジェ…(1958−1984)フランスの女優。ビュル・オジェの娘で、25歳で急死した。代表作『北の橋』『満月の夜』

大寺:最後にひとつだけお知らせなんですが、『美しき諍い女』はバルザックが原作なんですけど、リヴェットが一番最初にバルザックに取り組んだものがありまして。とはいえ、一応バルザックの「13人組」が原作といいながら、ほとんど俳優たちの即興演技によってつくられたといっていいものですが。『アウト・ワン』('71)という12時間40分もある大作を、なんとか日本語字幕をつけて上映しようとしています。おそらく来年のはじめ、リヴェットの一周忌のあたりに合わせて一回上映をして、プラスもう少し続けられたらと思っています。とはいえ、私たちもお金が無くて、大変な作業ですので、クラウドファンディングをやっています。この期限があと1週間で終わりになるのでこちらにご協力をしていただけたらと思います。援助してくださった方は優先的に観られますし、いろいろと特典もありますのでぜひよろしくお願いします。
坂本:アンスティテュ・フランセでは先ほどお名前が出た黒沢清監督がフランスで撮った最新作『ダゲレオタイプの女』の公開を記念して、フランスの幻想・怪奇映画の特集を9月末に上映します。そこでリヴェットの『嵐が丘』も上映予定ですので、そちらのほうもご覧いただけたらと思います。本日はどうもありがとうございました。