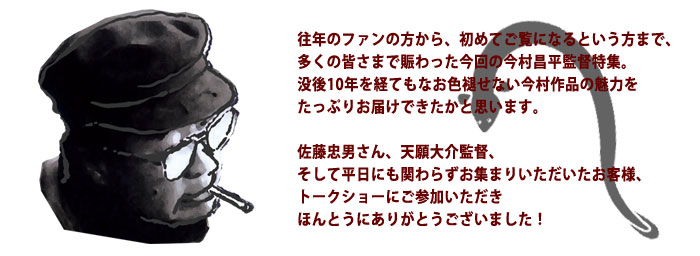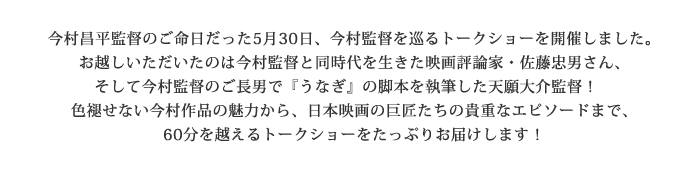
天願:今日はようこそおいでいただきました。 ぼくは脚本家として、今村昌平の映画の最晩年に、何本かの作品に携わっております。手伝えてよかったなと思う反面、戸惑うことも多かったですから、複雑な気持ちで作業しておりました。 いまご覧いただいた『うなぎ』もそうで、この時はさきに『カンゾー先生』の脚本を一緒にやってたんですけど、これがなかなか映画にならずに、今村プロが資金繰りに困っていたんです。そんな時に(当時の)松竹の奥山(和由)さんがはじめた低予算・小規模公開のプロジェクトの一本としてできた作品です。
『うなぎ』の脚本では今村監督と意見が対立して、相当ひどい喧嘩をして一回は降りたんです。最終的にはまた戻って最後まで書き上げたんですが。その時はまだ『うなぎ』というタイトルではなくて、「闇にひらめく」(原作と一緒)だったんです。それが、記者発表の日に突然「この映画のタイトルは『うなぎ』です」と言いだして大騒ぎになったんです。看板には「闇にひらめく」って書いてあるのに(笑) まぁというように、乱暴なところがある人でした。

天願:まずは、佐藤さんが今村昌平に注目したところから伺いたいのですが。
佐藤:わたしは今村さんよりたしか4つ若いのかな。ほぼ同世代ですね。彼が監督としてデビューした頃、わたしも駆け出しの批評家になっていました。だから、若い監督がどこから現れるかと注目していたんです。今村さんは戦争中に青春時代を送り、やはりその経験が作家として非常に重要なテーマになっていると思います。今村さんの上の世代の監督はみな何らかのかたちで戦争に協力的な映画をつくっていました。それが戦争が終わった途端、急に考え方を変えなきゃいけなくなった。だから真面目な監督たちは反省する映画を作ったんです。戦後10年くらいは日本映画は実にセンチメンタルだったんですね。
わたしは「日本映画はセンチメンタルすぎる」と攻撃する文章を書いて花が咲いたという面がありまして(笑)、いつになったら元気のいい映画が現れるんだと思っていたら、やがて現れました。まず注目したのは、大映の増村保造。彼は溝口や小津など巨匠たちを全部否定する文章を書きました。当時は撮影所の先輩を若造が批判するなんて到底想像できなかった時代です。 それが1957年くらい。戦後に撮影所に入ってきて、先輩たちの仕事はどうも納得できないと。戦争に責任のない世代というのかな。沢島忠や岡本喜八とかもそうだったかもしれない。
そして、増村とほぼ同時期に現れたのが今村昌平でした。『盗まれた欲情』という作品が、そういう新しさのひとつの極めつけの作品だって若い人たちの間では言われてましたね。欲望を肯定することを真っ向から打ち出していました。そして、3本目の『果しなき欲望』を観たときに「あ、これは大物だ」と思いましたね。それでインタビューに行きました。 今村さんは早稲田で学生演劇をやってたから、そのあたりの新劇の若手作家には詳しくて、当時話題になってた女流作家と組んで、レイプされた女性がそれと断固として戦うような脚本を書きたいなんていってましたね。あとで考えると、今村さんの作品では、そういう作品が3つくらいあるよね(笑)
会社がつけたタイトルだけど、最初の作品が「〜欲情」とか「〜欲望」とかだったから、「欲望監督」っていわれてね。今村さん、意外と気に入ってたのかなぁ?
天願:嫌がってましたよ(笑)
佐藤:嫌がってたでしょうね(笑) だけど、それがテーマだった。非常に新しい考え方をする人物が現れたなと思いました。
天願:(今村は)戦争中は兵隊に行ってないんですよね。そのことによって、佐藤さんがおっしゃったような反省をしなくて済んだかもしれない。例えば外地に行って酷いことをしてたら反省せざるを得ないですからね。だから、戦争のことを描いてる作品は多いけど、殆ど内地の話です。『カンゾー先生』もそうですし、『復讐するは我にあり』で出てくる場面もそうですが、日本本土の中での戦争の描き方になってます。
最初の『盗まれた欲情』を観ると、今東光が原作なんですけど、やはり佐藤さんがおっしゃったような、その後の作品にも現れる“欲望の肯定”というモチーフと同時に、“知性の敗北”というものも現れます。インテリがダメだっていうことが非常に強く出ています。それは『神々の深き欲望』に至るまで、ずっと続いていく。『にっぽん昆虫記』じゃないですけど、しぶとく虫のように生きていくのが、一番強いのだと。その頂点は女の人で、とにかくどの映画も、最後に至るまで、弱々しい女の人は全然出てこないですね。割とたくましい感じの女性が好きだったんですね。息子から見ていると、あんまりそういうところは見えなかったんですが。ハッキリと物を言ったり、男勝りみたいな人が好みだったのではないかと思います。そういうものが処女作からずっとあるようです。
増村さんのことは、何かの話でチラッと言ったことがあったんですが、割と好きだったという感じでしたね。あんまり人の映画について話す人ではなかったけど、「俺は好きだよ」と言っていたのを覚えてます。ただ、やっぱり近い所もあるけど、随分タイプが違うっていうか、そんな感じが僕はします。女の人の描き方なんかは共通するのかもしれませんが。増村さんは割と撮影所の中で一種の職人監督としても、与えられた企画を次々に撮るっていうタイプの人でしたよね。
佐藤:増村さんの方が観念的なんですよね。自己主張が大事だと打ち出してはいても、主張の仕方が生々しくないんですよね。その後に今村さんの松竹時代の後輩だった大島渚が出て、この三人が揃った時に戦後の日本映画が全く新しい時代に入ったっていう気がしました。そして、私はもっぱらその宣伝係みたいなことを務めておりまして、それで一人前の批評家と認められるようになりました。彼らが揃ってようやく、若い人たちが先輩の巨匠たちの批判をしても構わないんだってことが、常識とまではいかないけれどもハッキリしてきました。そして、時代は変わったと思いますね。
要するにその時に、夜が明けて映画界はエネルギー主義時代になったわけです。映画界ってのは一斉に動くんでね、これはあまり良いことではないと思うんですけれども。1950年代が終わって60年代に入った頃ですね。とにかく元気がよけりゃいいんだという形になりまして、それこそ欲望万歳と、エネルギーのある奴は突っ走れと。多少軽率なところもありましたけどね。でも大きく日本映画界の空気が変わったことは確かでした。その頃、渋谷実っていう松竹大船撮影所の非常に感覚的に洒落た映画を作る巨匠監督がいて、この人と私が雑談していた時に、今村さんが師匠として選んだ川島雄三の話になって、「川島は辛いだろ〜。今や、エネルギーの時代だからな。あいつはエネルギーは無いわ。」って(笑) まぁ渋谷実は川島雄三の師匠だったわけですけどね。「そういうエネルギーなんて元々無いんだから、川島は可哀想だ。」なんて言ってたんです。

佐藤:今村さんは、小津安二郎の助手についていて、『東京物語』の助監督をやっているんですよ。その前の作品か後の作品か忘れてしまいましたが、セットで撮影している時に、笠智衆が原節子の役の「紀子」と呼ぶときのアクセントが違うと。笠智衆は熊本出身で熊本弁なのでね。そしたら、当時サードの助監督だったかなんかだった今村昌平が、「笠さん、アクセントが違います。グリコと言ってください。」と言ったんです(会場(笑)) グリコは誰でも同じアクセントで発音できるんですよね。だから「グリコの発音で紀子と言ってください。」って言ってね(笑) セットの全員がしーん…となったそうです。なにしろ、サードの助監督が偉大な巨匠の前で、そして名優・笠智衆の発音を指導したんですから。これは直接本人から聞いたんですが、今村さんは「あぁ、しまった!」と思ったそうです。出しゃばりすぎたかな〜と。だけど今さら引っ込むわけにも行かなかったようです。
あと、これはハッキリ言ってたんだけど、「小津安二郎が偉大な監督であることを認めないわけじゃないんだけれども、とにかく小津さんの映画は、初めは俳優さんたちが元気に演技してるのに、何十回も繰り返してやってるうちに、だんだん元気がなくなってくる。それで、俳優たちが元気がなくなるとOKになるんだ。」ってね、「こういう先生のところについていても、勉強にならないと思う。」って自分から辞めて、それで、まだ当時としては二流監督だった川島雄三のところに行ったんです。そして川島雄三を師匠と仰いで、川島さんからは非常に多くのことを学んで。川島さんの批判なんかは全くしなかったですね。私が聞いてる限りでは。
天願:アクセントに関して言うと、ものすごくうるさかったんですよ、親父は。僕も子供のころから散々直されたんで。ちょっと訛ったり、違うアクセントで言うと、「違う!」って言われて。耳が良いっていうか、東京っ子だったから、気になるんですかね、あれは。だから思わず笠さんの熊本弁に怒りを覚えてしまったんだと思います(笑)
小津さんに関して僕が聞いているのは、やっぱり最初は評価してなかったと。不満だったというかね、何で芝居がこんなにつまんなくなってからOK出すんだとか言ってて。ただ晩年になって話を聞いたときに、「やっぱり凄いと思う」と言ってて。だから、ずっと尊敬はしてましたね。で、川島さんは歳があんまり離れてないんですね。だから、師匠というより、頼りない兄貴という感じで親父はサポートしてましたね。
川島さんについては、「あんなにモノを不味そうに食う人を見たことがない」って親父とおふくろが喋っているのを聞きました。不味そうにモノを食っていると、「川島さんみたいに食うな」って言われたりね(場内笑)。 川島さんは、タイプとして元気がいい映画を作らなきゃいけないのは辛かったと思います。ちょっと斜に構えるタイプでしたから。
ただ、親父は川島さんからは多大な影響を受けていたようですね。恐らくそれは、年の近い川島さんにくっついていって、大人の遊びを色々学んだんだと思うんですね。小津さんだともう巨匠で偉かったからそんな感じじゃなかったろうし、他の助監督たちだと、たぶん親父の学生時代の遊んでたレベルとそんなに変わってなかった。川島さんは東北の人で、気取ってかなりシャレた遊び方をしていたんだと思います。東京人だった親父はそれに凄く影響を受けたんだと思います。

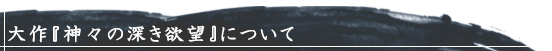
天願:川島さんもまた色んな撮影所を渡り歩いて映画を撮り続けた人だけれども、60年代から、既存の製作会社を飛び出して独立プロで映画を撮るのが活発化したのが日本映画の大きな転換期だったと思いますが、そのあたりの時代の作品についてはいかがですか?
佐藤:『神々の深き欲望』というのは、ほんとに全力で投げ込んだ力作で、これで日本映画の頂点を極めたいという感じの野心作だったと思うんですけど。原作は今村さん自身がつくったお芝居なんですが、この芝居をみると非常に分かりやすい物語なんですよ。あれは奄美の小さな島で、あそこを日本人の原点として捉えて、日本のすべてをここで説明してやろうとした野心作だったと思う。でも、映画ははっきりいってよく分からないんですよね。近親相姦が出てきたりするけど、その意味がわかんなかったりする。
原作はあの島から東京に出てきた若者たちの話が半分、そしてその島の話が半分で構成されていて、東京のパートには家族ぐるみで経営する町工場が出てきて、保険金のために放火したりする。それを身内だからと強制されたりするんです。そうやって東京に出てきた若者が身内意識に悩まされる。日本という国はこの身内意識から出来てるんじゃないか。そして、あの島が身内というものの原点なんだ、さらに身内というのは天皇制とつながると考えていいんだと。非常に明快につながっていくんですね。だから個人の個性が育たないんじゃないかという問題意識がはっきりとわかる。
だけど、あんまりわかりやすい映画を作るのもいかがなものかと、今村さんは悩んだんじゃないかな。それで、結局完成した映画は島の話だけになってしまって、そうなるとわかりにくいんだな。これは日本というより原始的な世界の話じゃないかなって感じになっちゃうんですよね。大変な野心作であることはわかるし、最後の海の場面とか、日本映画史でも指折りの名場面もある。だけど、今村さんの意図したことがうまく伝わらない失敗作なんじゃないかな。
天願:そこらへんは佐藤さんと僕は意見が違っています。撮影時のエピソードなんかを聞いていると、頭で考えた観念的でわかりやすいものを超えたものを求める、肥大した衝動に身をゆだねる作り方をしていると思う。一方で金の計算をしながらですが。だから、ちょっとコッポラの『地獄の黙示録』に似たつくりなんですね。
ただそこにもうひとつ、日本の神話「古事記」を重ねています。古事記が原作だといってもいい。戯曲のほうがもう少しすっきりしてるんです。地域のエリアも狭いし。ただ映画では身内っていうものをどんどんさかのぼっていくことで、近親相姦から生れたという日本の神話に結び付くんです。そこにぜんぶつながっていく。ここにいる我々も島にいる彼らとどこが違うのかっていう形にまでいこうとしたんだと思います。映画の一般的な評価はどうかわかんないですけど、僕自身は割と好きです。

天願:今村がこだわっていたものに共同体って問題がありますよね。共同体に縛られている個人っていう問題。処女作からあるように、知性ってものは否定しているわけです。共同体の中で、欲望のままでは生きていけないけど欲望が強くて振り回されている男と、欲望を選択して前にたくましく進んでいく女、みたいな構造の話をずっと撮っています。初期のころは山内久さんが脚本で、これはとても理性的でした。そこからスタートしたのが、中期に長谷部慶次さんと組むようになってからは、『赤い殺意』や『にっぽん昆虫記』『神々の深き欲望』など、東北であるとか沖縄であるとかに共同体の原型を探して、地方へ地方へと向かうようになっていきます。で、共同体と個人の関係を戦後的なアプローチで探求していたわけです。
ちょっと自分の話をしますが、『うなぎ』で何が起こったかというと僕の解釈ですが、もう共同体は無いのだという話ですね。もう描くべき共同体は無くなってしまった。そこに縛られている人たちも昔と違うんだと。そんなに縛られているわけではない。では、我々はどこに向かえばいいのか。そこで、疑似的な、新しい共同体を模索するっていうのが『うなぎ』って話です。それが世界的には多少評価された。まあ、非暴力というテーマが評価されたとも言われてますけど、それ以降の世界の流れを見ますと、人間の社会のあり方みたいなものがどんどん解体されていって、新しい組み合わせを考えなきゃいけないっていう時期で、そこにちょうどマッチしたんじゃないかと思ってます。その後の今村は好きなようにやるって感じになっていくわけですけど。

天願:海外に関しては、俺の映画は海外では受けないってず〜っと言ってたんですよ。どこ行ってもわかんないって言われるんだって。海外で受ける映画は大島渚に任しとけばいいんだとよく言ってましたね(笑) 海外にもファンの人はいくらかはいたんですが、ある時期までほとんど評価されないままだったんですね。黒澤さんや大島さんのようにうまく海外で紹介されないというのは、本人も若干は気にしてたんだと思います。カンヌに出品されている時でも、行かないでずっと日本で麻雀しているとかね。 一方で、日本では佐藤さんを筆頭に多くの方から評価していただいていました。日本と海外での評価のずれについて佐藤さんはどう思われていますか。
佐藤:やっぱり共同体に縛られ、そこからどれぐらい強く逃れたいと思っているかとか、そういう感覚が日本人にはよく分かるんだけど、外国人にはわかんないみたいなんですね。傑作『赤い殺意』もどこかの映画祭で予選で落ちていたはず。『復讐するは我にあり』もそんな感じだったと思う。日本としては「これこそは日本映画」と思って出品してるんだけど、大手の映画祭はみんな予選で落としていた。
それでも、海外の映画ファンの間で静かな話題になったのはやっぱり『復讐するは我にあり』ですね。あれだけ凄まじい人間の描き方は、外国映画にはないわけです。悪い人を悪い人として描くだけでなく、悪い人の持ってる魅力や内的な葛藤を描いているし、暴力シーンも際立って優れている。それは単に迫力があるというんじゃなくて、何を恨んで行動しているのかがはっきりとはわからない。日本人にとっては何となくはわかるんだけど。その底知れないわからなさが人間の奥深さを考えさせる。そういう表現が、外国人にとっては新しいタイプの暴力映画が現れたと受け止められていました。だから、海外での評価を決定的にしたのはやっぱり『復讐するは我にあり』じゃないかな。


質問1:今村監督の作品では、ガマ蛙と蛇がよく出てくるなぁと思ったのですが、そういう土着的な香りがする生物などに思い入れがあったんでしょうか?
天願:好きでした(笑) 『うなぎ』もそうで、うなぎにこだわったのはもちろん食うのも好きだったけど、ああいうぬめぬめして変な形をしている生き物が好きだったです。
質問2:『復讐するは我にあり』で加藤嘉さんが殺されるシーンは実際に事件のあった鬼子母神のアパートで撮影されたそうですが、今村監督はセットではなくロケーションにこだわっていたのでしょうか?
天願:ロケーションにこだわっていたのは最初からそうですね。撮影所のセットは嘘くさいと、なるべく表に出て撮っていたましたね。ただやはり撮影所出身なので、セットを憎んでいたわけじゃなくて、合理的にセットを組むこともかなりありましたよ。どちらかというと現実のなかにキャメラをもちこむという世代だと思います。
質問3:私は特に映画ファンというわけではなく、たまたま通りかかったら佐藤さんのトークショーがあるというので入って来ました。このあと上映される『復讐するは我にあり』は暴力的な映画だと聞いて観るかどうしようか迷っています。『復讐するは我にあり』はただの暴力映画ではなく、観たら人間の見方や人生観がちょっと変わるよとか、そういうポイントがあったら教えてください。
佐藤:人生観が変わるというのは確実にあると思います。なんでこの男は悪いことをしゃにむにやるんだろうと。いろいろ考えて、この男の気持ちが分かったりして、気味が悪くなったりするのは確かだと思います。
具体的に言うと、主人公の殺人鬼は若い頃は結構ちゃんとした若者だったんですよ。それが、戦争が終わって現れたときには、進駐軍の通訳のフリをして現れるんですよ。それで結構商売が成り立ってるみたいなんですね。少年院ばかり行っていた男で、中学も行ってないのにです。この男は自分がこうなりたいという希望が強くあって、それのためならなんでもやるって考えている男だと、それを見てると思う。そして、俺もそういう部分がないとはいえない。そう強く思うこと自体はたいしたことではないんだけど、それのためなら殺人鬼になってしまうこともあると思う。切実にこの男の気持ちが解って、深く同情する部分もあると思う。だけど、この映画は終わりまでみても、どうしてこの男が殺人鬼になったかはわからないですよ。観る人によって解釈が分かれると思う。
天願:これから初めて観る若い人に私からも補足しておきます。『復讐するは我にあり』はとても面白い映画なので退屈する心配はありません。残酷なシーンもありますが、人生は本来残酷なものなので、これも問題にはなりません。僕から見て何より素晴らしいと思うのは、俳優の演技です。一時期リアリティを模索して劇映画から離れてドキュメンタリーを撮っていた今村が、もう一回劇映画に戻って作られた作品なので、脂ののった素晴らしい俳優たちの、彼らのフィルモグラフィ上でも一、二を争う恐ろしい芝居のぶつかり合いが見られます。映画が好きな人であれば誰でも楽しめると思いますので、是非ご覧ください。