
![]()
監督・脚本■エルマンノ・オルミ
1931年イタリア・ベルガモ生まれ。
53年に映画監督としてデビュー、ネオレアリズモの時代にドキュメンタリー映画や短篇映画を多く監督した。61年、30歳のころに発表した『定職』が、ヴェネツィア国際映画祭でイタリア映画批評家賞を受賞し注目を浴びる。
78年の『木靴の樹』は、第31回カンヌ国際映画祭でパルムドールと審査員エキュメリック賞をダブル受賞、世界中で絶賛される。87年の『偽りの晩餐』はヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞ほか3賞を獲得し、翌88年の『聖なる酔っぱらいの伝説』で、同映画祭最高賞の金獅子賞に輝いた。
08年、ヴェネチア国際映画祭はオルミ監督の長年の功績を讃え、栄誉金獅子賞を贈った。『ポー川のひかり』を自身最後の長篇劇映画とし、今後はドキュメンタリー映画を手がけていきたいと公言していたオルミ監督。しかしその5年後、前言を翻して、現代の黙示録ともいうべき本作『楽園からの旅人』を発表した。
![]()
・定職('61)監督/脚本
・婚約者たち('63)監督/脚本
・一人の男がやってきた('65)監督/脚本
・事情('73)監督/脚本/製作/編集
・木靴の樹('78)脚本/監督/撮影
・どんどん歩いて行くうちに('83)監督/脚本/撮影/編集
・偽りの晩餐('87)脚本/撮影/監督
・聖なる酔っぱらいの伝説('88)監督/脚本
・古い森の秘密('93)監督/脚本
・ジョヴァンニ('01)監督/脚本
・屏風の陰で歌いながら('03)監督/脚本
・明日へのチケット('05)監督/脚本
・ポー川のひかり('06)監督/脚本
・ランジェ公爵夫人('07)製作
・楽園からの旅人('11)監督/脚本
※主に劇場用長編作品のみ
―オルミとの対話―
今週は、イタリアの巨匠エルマンノ・オルミ監督特集です。
「記憶というものは、書いて書類にするものではなく、
心に残り、刻み込まれたものだけを言うのだ」とオルミは語る。
『楽園からの旅人』と『ポー川のひかり』。どちらの作品も、主人公は今までの身の回りにある物質的な物を、失ったり、自ら投げ捨てたりすることで、本当に大切な事、新しい考えを見出している。しかし、それぞれの主人公は今まで生きてきた人生という記憶の道筋は踏み外してはいない。いや、むしろその道筋を振り返ることで、新たな道を歩んでいる。すべてを失う事、すべてを投げ捨てる事で残ったのが、オルミの言う記憶なのだろう。
『ポー川のひかり』は、エルマンノ・オルミ監督最後の長編劇映画と言われた。
その時の彼のコメント。
「私にとってこの決心は、自然な所作なのだ。これまでずっと映画で物語を語り続けてきた。そして、自分の対話者に対して常に誠実であろうと努めてきた。これは私が一度として破ったことのない約束である。だが、自分のしていることがこれで最後になるとわかっているというのは、何を意味するのだろうか? まず、何よりも、最後の所作は自分の一生の意味を集約するものだという自覚である。ここで私が自分に向けた根本的な問いは、「何を語るのか?」「何について語るのか?」そして何よりも「誰について語るのか?」だった。」(『ポー川のひかり』パンフレットより)
最後にするという思いは、様々な事を投げ捨て、オルミ自身の人生を振り返り、
新たな道を切り開くことにも思える。
『ポー川のひかり』を創りだし、オルミは何を思ったのか。
対話者である世界の人々は何を思ったか。
劇中のセリフで主人公が次のようなことを語る。
「世界中の本よりも、友人と飲むコーヒーのほうがいい。」
人と人が対話することの重要性。
映画の中でも主人公たちは冷静に、誠実なまなざしで人々と対話する。
オルミも映画を作ることで、世界の顔も知らないどこかの人と対話する。
そして5年後の2011年。
それまでの間に我々は、何も変わらず日々に追われて来てしまったように思える。
オルミは、世界の人々と再び語り合うために前言を撤回し、
新作『楽園からの旅人』を、世に送り出した。
技術が進み、便利になり、物や情報であふれかえる世の中。
たくさんの人々が平和を訴えているが、今も争いはどこかで起こっている。
何かが、誰かが、苦しんでいる。何か分らないが、うまくいっていない。
人間自ら生み出した糸が、複雑に絡み合いほどけなくなっている。
ほどこうとすると、さらに絡み合い、
自らも絡み合った結び目になってしまってはいないだろうか?
人はなぜ穏やかに暮らせないのだろう。
人はなぜ心豊かに暮らせないのだろう。
オルミが投げかける言葉に、私たちはこれからどんな返事を返していけるのだろうか。
ポー川のひかり
CENTO CHIODI
(2006年 イタリア 94分  ビスタ/SRD)
ビスタ/SRD)
 2014年3月1日から3月7日まで上映
■監督・脚本 エルマンノ・オルミ
2014年3月1日から3月7日まで上映
■監督・脚本 エルマンノ・オルミ
■製作 ルイジ・ムジーニ/ロベルト・チクット
■撮影 ファビオ・オルミ
■音楽 ファビオ・ヴァッキ
■編集 パオロ・コッティニョーラ
■出演 ラズ・デガン/ルーナ・ベンダンディ/アミナ・シエド/ミケーレ・ザッタラ/ダミアーノ・スカイーニ/フランコ・アンドレアーニ/アンドレア・ランフレーディ
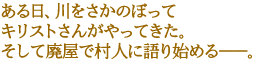
 イタリアの古都ボローニャ。夏休みに入った人気の無い大学で、守衛は大量の古文書が太い釘で打ち抜かれているのを発見する。この書物の大虐殺に、学内は一転大騒ぎとなる。容疑者として浮かび上がったのは、若くして将来を嘱望されていた哲学科の主任教授だった。近く国際舞台で論文を発表することになっていたが、前日の学年末の授業を最後に忽然と姿を消していた。
イタリアの古都ボローニャ。夏休みに入った人気の無い大学で、守衛は大量の古文書が太い釘で打ち抜かれているのを発見する。この書物の大虐殺に、学内は一転大騒ぎとなる。容疑者として浮かび上がったのは、若くして将来を嘱望されていた哲学科の主任教授だった。近く国際舞台で論文を発表することになっていたが、前日の学年末の授業を最後に忽然と姿を消していた。
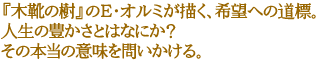
 絶え間ない紛争、環境問題、さらに経済危機と、今日、世界は急速に破局の危機を迎えようとしている。深い精神性を湛えた作品を撮り続けてきたオルミ監督は、この病める時代に、新約聖書の世界を通して、人生の豊かさとはなにかを問い、希望のしるしを探ろうとした。そして完成したのが、イエス・キリストの寓意をひそめ、心を癒す優しさに満ちた本作である。まさに誠実な人生の結実を感じさせる渾身の作で、余韻は限りなく深く、しかも突きつける 問いは根源的である。ここには「温もりのある、真に豊かな生活を得るために、もう一度始まりに帰ろう」という、オルミ監督の現代社会に対する痛切なメッセージがこめられている。
絶え間ない紛争、環境問題、さらに経済危機と、今日、世界は急速に破局の危機を迎えようとしている。深い精神性を湛えた作品を撮り続けてきたオルミ監督は、この病める時代に、新約聖書の世界を通して、人生の豊かさとはなにかを問い、希望のしるしを探ろうとした。そして完成したのが、イエス・キリストの寓意をひそめ、心を癒す優しさに満ちた本作である。まさに誠実な人生の結実を感じさせる渾身の作で、余韻は限りなく深く、しかも突きつける 問いは根源的である。ここには「温もりのある、真に豊かな生活を得るために、もう一度始まりに帰ろう」という、オルミ監督の現代社会に対する痛切なメッセージがこめられている。
ポー川とは、イタリア北部を西から東へ、茫漠とした平原を蛇行し、ゆったりと流れる大河だ。古くからイタリアの芸術家に愛されてきた、このポー川流域の美しく牧歌的な時間のなかに、オ ルミ監督は現代の寓話を見事に描き出した。


楽園からの旅人
IL VILLAGGIO DI CARTONE
(2011年 イタリア 87分  ビスタ/SRD)
ビスタ/SRD)

2014年3月1日から3月7日まで上映
■監督・脚本 エルマンノ・オルミ
■製作 ルイジ・ムジーニ
■撮影 ファビオ・オルミ
■撮影 パオロ・コッティニョーラ
■音楽 ソフィア・グバイドゥーリナ
■出演 マイケル・ロンズデール/ルトガー・ハウアー/アレッサンドロ・アベル/マッシモ・デ・フランコヴィッチ
![]()
 イタリアのある街で、半世紀の間、市民が集ってきた教会堂が取り壊されようとしている。キリスト像も無残に下された。長い年月、老司祭は神の愛を唱えてきたが、人々の望みは別のものに代わろうとしていた。
イタリアのある街で、半世紀の間、市民が集ってきた教会堂が取り壊されようとしている。キリスト像も無残に下された。長い年月、老司祭は神の愛を唱えてきたが、人々の望みは別のものに代わろうとしていた。
夜、ひとりの男が傷ついた家族をつれて司祭館にやってくる。男は技師で、家族は不法入国者だった。そして教会堂には、さまよう人が次々とやってきた。多くがアフリカから長い旅を経てきた人だった。そして即席の小さな村が作られてゆき…。

かつてオルミ監督は、『ポー川のひかり』を自身の映画人生における最後の劇映画と語った。しかし5年後、前言を翻して、現代の黙示録ともいうべき本作『楽園からの旅人』を発表する。
 映画では、さまよう人々への心優しい描写が印象的だ。彼らの境遇は苛酷だが、みなこよなく高貴で美しい。子どもは顔を輝かせ、母親がいて、新しい生命が誕生し、流す涙、淡い恋もある。オルミ監督にとって人間の存在そのものが喜びなのだ。「世界を温もりのあるものに戻す」という彼の人間性への信頼は失われることはない。不安に満ちた現代社会のなかで、旅人たちの神々しさを示し、すべては破局の中から新しく始まり、未来は私たちが築くものと語る『楽園からの旅人』は、まさに希望の映画である。
映画では、さまよう人々への心優しい描写が印象的だ。彼らの境遇は苛酷だが、みなこよなく高貴で美しい。子どもは顔を輝かせ、母親がいて、新しい生命が誕生し、流す涙、淡い恋もある。オルミ監督にとって人間の存在そのものが喜びなのだ。「世界を温もりのあるものに戻す」という彼の人間性への信頼は失われることはない。不安に満ちた現代社会のなかで、旅人たちの神々しさを示し、すべては破局の中から新しく始まり、未来は私たちが築くものと語る『楽園からの旅人』は、まさに希望の映画である。
エデンの園には「善悪の知識の木」と「命の木」がある。
かつて神は人間に「命の木」の実まで食べてはならないといった。
しかし現代の私たちは「命の木」にも手をのばしている。
私たちは何をしようとしているのか。
――――エルマンノ・オルミ
