「kawaii」という言葉がファッション界で共通言語になりつつあり、
世界的にも注目されている街、東京。
渋谷原宿を歩けば、今の流行がひとめでわかるし、
安くて、トレンドに乗った店が軒を連ね、欲しい洋服はすぐ手に入ります。
その東京で暮らす私も、やっぱり曲がりなりにも洋服が好きだし、
街行く人たちのファッションをついついチェックしてしまいます。
でも実は、そうしてよく感じるのが、「同じだなぁ」ということ。
同じ柄のシャツ、同じ形のスカート、同じ髪型と同じメイク…。
みんな可愛いのだけれど、みんなよく似ているのです。
本物のおしゃれとは、何をもってして言うのでしょうか。
雑誌の最新号をくまなくチェックして、流行りの服に身をつつむこと?
確かにそれも、おしゃれだと言えるでしょう。
「新しい服を着るだけではダメ。その服でいかに生きるかなの。」
と、ずばり言うのは、モード誌「ハーパーズ・バザー」や「ヴォーグ」で長年に渡り活躍し、
“ファッション界の女帝”と呼ばれた伝説的編集者ダイアナ・ヴリーランド。
彼女はそれまでの、ただ服を着たモデルが立っているだけの誌面ではなく、
そのモデル自身が持つ個性を生かしたポーズやアングルにこだわり、
スタジオを飛び出して世界の様々な場所を背景に撮影しました。
ダイアナは、それぞれのページで流行の服だけではない“スタイル”そのものを提唱したのです。
「ファッションは日々を生き抜くための鎧なんだ。手放せば文明を捨てたも同然だよ。」
NYのストリートファッションを追い続けて約半世紀。
タイムズ紙の名物フォトグラファー、ビル・カニンガムはそう言います。
ビルの写真には、時代と共に変化してきたNYのファッションの歴史が刻まれています。
にこやかな笑顔の下に隠された鋭い観察眼で、キラリと光るファッションを彼は常に探します。
たとえどんな有名人やスターでも、魅力的でなければビルの眼には全く映りません。
この二人のファッショニスタ、ライフスタイルはまるで反対です。
ダイアナは社交界にも積極的に出入りするような、自他共に認める目立ちたがり屋でした。
自宅のリビングは、自ら“地獄の庭”と呼ぶ一面真っ赤な部屋。
その色と同じ真っ赤なネイルも、いつも完璧に塗られていました。
いっぽうビルの生活は極めて質素。
カーネギーホールのキッチンもない狭いアパートで、膨大なネガに囲まれて暮らしています。
パリの清掃作業員着だという青い上っ張りに、雨が降ればテープでつぎはぎだらけの雨合羽。
(それが何故だかとてもかっこいいのですが…。)
3ドルのコーヒーでじゅうぶん満足だと言います。
けれど、ダイアナもビルも、ファッションにかける想いは同じです。
彼らがともに信じているのは、
おしゃれというものはパーソナリティであり、アイデンティティであるということ。
ファッションはただの衣服なんかではなく、最も身近な自己主張の場なのです。
誰かの真似なんかじゃなく、自分が本当に似合うものを探し、
誰かに着せられるのでなく、自分が着たいものを着ればいい!
ファッションの最先端を見つめ続けてきたふたりの偉人は、私たちにそう断言します。
流行に敏感になることも大事だけど、個性を生かすことを忘れてはいけない。
なんだかこれは、ファッションだけに言えることとは限らない気もしますね。
そしてこの信念は、ふたりのストイックな生き方にそのまま現れています。
映画を観た後、家に帰ったら自分のクローゼットをもう一度見てみてください。
もしかしたら、いつもの服がちょっと違う風に見えてくるかも…?
今週の早稲田松竹は、珠玉のファッション・ドキュメンタリー二本立てを、お届けします。
(パズー)

 ビスタ)
ビスタ)

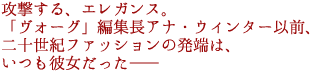
 ファッション、アート、音楽──すべてのカルチャーが、ダイナミックかつ刺激的に変化し続けた二十世紀において、華麗なるファッション界の中心に50年間にわたって君臨したひとりの女性がいた。伝説のファッショニスタ、ダイアナ・ヴリーランド。「ハーパース・バザー」で25年間に亘って活躍し同誌の黄金期を築き上げると、1962年にはライバル誌である「ヴォーグ」に移籍、編集長として輝く才能を次々と世に送り出した。70歳で世界最大規模を誇るメトロポリタン美術館衣装研究所の顧問に就任、常識を越えた衝撃的な衣装展を数多く成功させる。だが、そんな華やかな経歴だけでは、とてもこの稀有なる存在を説明することはできない。
ファッション、アート、音楽──すべてのカルチャーが、ダイナミックかつ刺激的に変化し続けた二十世紀において、華麗なるファッション界の中心に50年間にわたって君臨したひとりの女性がいた。伝説のファッショニスタ、ダイアナ・ヴリーランド。「ハーパース・バザー」で25年間に亘って活躍し同誌の黄金期を築き上げると、1962年にはライバル誌である「ヴォーグ」に移籍、編集長として輝く才能を次々と世に送り出した。70歳で世界最大規模を誇るメトロポリタン美術館衣装研究所の顧問に就任、常識を越えた衝撃的な衣装展を数多く成功させる。だが、そんな華やかな経歴だけでは、とてもこの稀有なる存在を説明することはできない。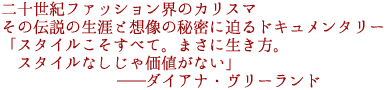
 ファッション誌においてモデルがモデルとしてポーズするのが当たりまえの時代に、ダイアナは個性を持ったパーソナリティとしてのモデルを賞賛した。ローレン・ハットン、ツィギー、シェール、バーブラ・ストライサンド、イーディ・セジウィックを見出し、時代のイット・ガールにしたのはダイアナだ。二十世紀を代表する写真家リチャード・アヴェドンやデヴィッド・ベイリーもダイアナが起用したことにより才能を開花させた。デビューしたばかりのミック・ジャガーをいち早く誌面に取り上げたのもダイアナだ。あのマノロ・ブラニクに「靴のデザインをしてみれば?」と提案したのも、ジャッキー・ケネディが夫の大統領就任式に着る服をアドバイスしたのも彼女なら、王冠を賭けた恋として知られる英国のエドワード8世とウォリス・シンプソンの恋の一夜にナイトガウンを用意したのも彼女なのだ。
ファッション誌においてモデルがモデルとしてポーズするのが当たりまえの時代に、ダイアナは個性を持ったパーソナリティとしてのモデルを賞賛した。ローレン・ハットン、ツィギー、シェール、バーブラ・ストライサンド、イーディ・セジウィックを見出し、時代のイット・ガールにしたのはダイアナだ。二十世紀を代表する写真家リチャード・アヴェドンやデヴィッド・ベイリーもダイアナが起用したことにより才能を開花させた。デビューしたばかりのミック・ジャガーをいち早く誌面に取り上げたのもダイアナだ。あのマノロ・ブラニクに「靴のデザインをしてみれば?」と提案したのも、ジャッキー・ケネディが夫の大統領就任式に着る服をアドバイスしたのも彼女なら、王冠を賭けた恋として知られる英国のエドワード8世とウォリス・シンプソンの恋の一夜にナイトガウンを用意したのも彼女なのだ。
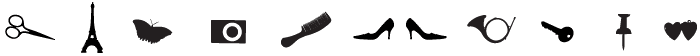

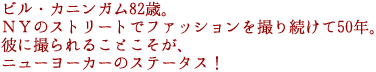
 ニューヨーク・タイムズ紙の人気ファッション・コラム「ON THE STREET」と社交コラム「EVENING HOURS」を長年担当するニューヨークの名物フォトグラファー、ビル・カニンガム。ニューヨークの街角で50年以上にもわたりファッショントレンドを撮影してきたニューヨークを代表するファッション・フォトグラファーであり、ストリートファッション・スナップの元祖的存在だ。そんなカニンガムにリチャード・プレス監督が8年がかりで撮影交渉し、撮影と編集に2年、通年10年の制作期間を経て完成した本作で、カニンガムの知られざる私生活や仕事ぶりが初めて明かされた。
ニューヨーク・タイムズ紙の人気ファッション・コラム「ON THE STREET」と社交コラム「EVENING HOURS」を長年担当するニューヨークの名物フォトグラファー、ビル・カニンガム。ニューヨークの街角で50年以上にもわたりファッショントレンドを撮影してきたニューヨークを代表するファッション・フォトグラファーであり、ストリートファッション・スナップの元祖的存在だ。そんなカニンガムにリチャード・プレス監督が8年がかりで撮影交渉し、撮影と編集に2年、通年10年の制作期間を経て完成した本作で、カニンガムの知られざる私生活や仕事ぶりが初めて明かされた。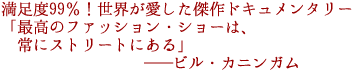
 雨の日も風の日もストリートに自転車で繰り出しては写真を撮り続け、夜になればチャリティーパーティーや社交界のイベントに出かけて行き、ときにはパリのファッション・ウィークにも遠征する。しかしビル自身はいつもお決まりのブルーの作業着姿で、雨の日にかぶる安物のポンチョは新調することもなくテープで修繕して着続けている。コーヒーは安ければ安いほど美味しいと言い、ニューヨーク・タイムズ紙の写真家としての客観的な立場を保つために、パーティー会場では水一杯すら口にしない。50年以上暮らしていたスタジオアパートの小さな部屋はネガフィルムが入ったキャビネットで埋め尽くされ、簡易ベッドが置いてあるのみ。仕事以外のことには全く無頓着で、頭の中はいつもファッションのことだけでいっぱいといったような質素な生活ぶりなのである。
雨の日も風の日もストリートに自転車で繰り出しては写真を撮り続け、夜になればチャリティーパーティーや社交界のイベントに出かけて行き、ときにはパリのファッション・ウィークにも遠征する。しかしビル自身はいつもお決まりのブルーの作業着姿で、雨の日にかぶる安物のポンチョは新調することもなくテープで修繕して着続けている。コーヒーは安ければ安いほど美味しいと言い、ニューヨーク・タイムズ紙の写真家としての客観的な立場を保つために、パーティー会場では水一杯すら口にしない。50年以上暮らしていたスタジオアパートの小さな部屋はネガフィルムが入ったキャビネットで埋め尽くされ、簡易ベッドが置いてあるのみ。仕事以外のことには全く無頓着で、頭の中はいつもファッションのことだけでいっぱいといったような質素な生活ぶりなのである。