

監督・脚本■レオス・カラックス
1960年11月22日、フランス生まれ。本名アレックス・オスカー・デュポン。 16歳で学校をやめ、翌年17歳で『La Fille Aimee(愛された娘)』という初の短編を撮る。18歳で「カイエ・デュ・シネマ」に映画評論を書き、80年にはイエール映画祭でグランプリを獲得した短編第2作目「Strangulation blues」を製作。
83年には長編処女作『ボーイ・ミーツ・ガール』で衝撃的に84年のカンヌ国際映画祭に登場、ヤング大賞を受賞し一躍脚光を浴びる。86年の『汚れた血』で“神童”“アンファン・テリブル(恐るべき子供)”カラックスの名を世界中に知らしめた。
91年には、2度の中断に見舞われながら完成させた『ポンヌフの恋人』を発表。『ボーイ・ミーツ・ガール』、『汚れた血』と同じくドニ・ラヴァンがアレックスの名を持つ主人公を演じた“アレックス3部作”の最終章であるこの作品で、その才能への評価は更に高まることとなった。99年の『ポーラX』では新境地に挑み世界に新たな衝撃を与えた。08年には東京を舞台にしたオムニバス映画の一篇『Tokyo!<メルド>』を発表。その内容は本作でムッシュ・オスカー演じるメルドのパートへ受け継がれている。本作『ホーリー・モーターズ』は『ポーラX』以来、実に13年ぶりの長編作品となる。

・ボーイ・ミーツ・ガール('83)監督/脚本
・汚れた血('86)監督/脚本
・ゴダールのリア王('87)出演
・ポンヌフの恋人('91)監督/脚本
・ポーラX ('99)監督/脚本
・ミスター・ロンリー('07)出演
・TOKYO!('08)監督/脚本
・ホーリー・モーターズ('12)監督/脚本/出演
カラックスがデビューした当時の熱狂を私は知らない。
『汚れた血』が日本で公開された時の興奮も、パンフレットで読むばかりだ。
だから2008年の『TOKYO!』を除けば、『ホーリー・モーターズ』が
初めて体験する“リアルタイムのカラックス”になる。
13年という月日はあまりに長い。世界中が待ちに待った。
もちろんカラックス本人が誰よりも一番待っただろう。
(曰く、「映画を撮れなくて気が狂いそうだった」。)
とにかく早く1本撮るために舞台はパリ、ラッシュは見ない、ビデオを使うという、
今までのカラックスの映画作りからは想像できないようなルールを作り、
ついに完成した『ホーリー・モーターズ』。
結論から言うと、“リアルタイムのカラックス”にまんまとくらわされた。
オスカーという1人の男が、
白いリムジンに乗って11の人格に成り代わる1日を描いたこの作品は、
映画の冒頭で眠りから醒める男(演じるのは他でもないカラックス自身)のごとく、
待ちくたびれた私たちを覚醒させてくれるような傑作だった。
物語のあらすじなどはもはや無い。
オスカーの行動をなぜ? どうして? と追求するのは序盤でやめてしまうだろう。
「君がこの仕事を続ける原動力が知りたい。」
映画のなかで、ミシェル・ピコリ演じるあざのある男がオスカーに問う。
オスカーは答える。
「行為の美しさだ。」
この会話こそ、カラックスの映画へ対する答えなのだ。
13年の間に、映画とは何かをカラックスはひたすら考え続けてきたのだと思うが、
導き出した結論は驚くほどシンプルなものだった。
そして多分カラックスはその答えを最初から知っていたのだと思う。
なぜならドニ・ラヴァンという俳優を使い続けてきたからだ。
映画というのは元来“動きを見ること”。
身体的・視覚的な“motion picture”に立ち返ったカラックスは、
ドニ・ラヴァンに、彼の稀有な身体を使い、ありとあらゆる人生を演じさせた。
そこに内気でナイーブな少年アレックスはもういない。
『ポンヌフの恋人』の、
橋のそばで煌々とネオンを輝かせていたサマテリーヌ百貨店。
『ホーリー・モーターズ』では廃墟化したその場所で、
物語の終盤にオスカーのかつての恋人ジーンはこう囁く。
who were we/ who were we/
when we were/ what we were/ back then?
私たちは誰だったの?
私たちが私たちだったあの頃。
映画とは何だったか。カラックスが、
映画が映画だったあの頃に想いを馳せてみようと語りかけている。
(パズー)
ポンヌフの恋人
LES AMANTS DU PONT-NEUF
(1991年 フランス 126分 
![]() ビスタ/ドルビーA)
ビスタ/ドルビーA)  2013年12月14日から12月20日まで上映
2013年12月14日から12月20日まで上映
■監督・脚本・台詞 レオス・カラックス
■製作 クリスチャン・フェシュネール
■撮影 ジャン=イヴ・エスコフィエ
■編集 ネリー・ケティエ
■音楽 ベンジャミン・ブリテン
■主題歌 デヴィッド・ボウイ/リタ・ミツコ
■出演 ジュリエット・ビノシュ/ドニ・ラヴァン/クラウス=ミヒャエル・グリューバー/ダニエル・ビュアン/マリオン・スタレンス/エディット・スコブ
■1992年ヨーロッパ映画賞主演女優賞・撮影賞・編集賞受賞
![]()
 パリで一番古く美しい橋“ポンヌフ”で暮らす天涯孤独の青年アレックスは、いつものごとく酒を飲みながら夜のパリを放浪していたが、車に足を轢かれてしまう。そこに通りかかったのが、空軍大佐の娘でありながら、恋の痛手と生涯治る見込みの無い目の病とで絶望的な放浪の毎日を送っている女学生ミシェル。アレックスはミシェルの美しさに初めて恋を知り、ポンヌフ橋のもうひとりの住人ハンスに頼み込み、二人は橋での生活を始めるのだが…。
パリで一番古く美しい橋“ポンヌフ”で暮らす天涯孤独の青年アレックスは、いつものごとく酒を飲みながら夜のパリを放浪していたが、車に足を轢かれてしまう。そこに通りかかったのが、空軍大佐の娘でありながら、恋の痛手と生涯治る見込みの無い目の病とで絶望的な放浪の毎日を送っている女学生ミシェル。アレックスはミシェルの美しさに初めて恋を知り、ポンヌフ橋のもうひとりの住人ハンスに頼み込み、二人は橋での生活を始めるのだが…。
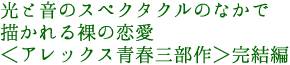
 パリのポンヌフ橋を舞台に、天涯孤独の青年と失明の危機に晒された女学生との愛を描いた、カラックス監督<アレックス青春三部作>の完結編である本作。撮影当時カラックスの恋人であったジュリエット・ビノシュと、“カラックスの分身”ドニ・ラヴァンが純粋な恋人たちを演じ切った。
パリのポンヌフ橋を舞台に、天涯孤独の青年と失明の危機に晒された女学生との愛を描いた、カラックス監督<アレックス青春三部作>の完結編である本作。撮影当時カラックスの恋人であったジュリエット・ビノシュと、“カラックスの分身”ドニ・ラヴァンが純粋な恋人たちを演じ切った。
当時のフランス映画史上最高額の38億円という総製作費や、同じくフランス映画史上最大のオープンセット(南仏モンプリエにパリの街並みを再現)、加えて2度の撮影中断に相次ぐ破産など、完成前から伝説化した『ポンヌフの恋人』。公開自体が絶望視されていたが、なんとか封切されると2週間で14万人という驚異的な大ヒットを記録。日本でも初公開時6ヶ月以上の超ロングランヒットとなった。
 物語は失意と闇から始まり、息もつかせぬスピードで希望と光へ疾走していく。躍動するパリの息吹を背景に、どんな甘さも妥協もよせつけず、エゴイスティックなまでに恋愛の本質を見つめた、紛れも無いカラックス監督最高傑作である。
物語は失意と闇から始まり、息もつかせぬスピードで希望と光へ疾走していく。躍動するパリの息吹を背景に、どんな甘さも妥協もよせつけず、エゴイスティックなまでに恋愛の本質を見つめた、紛れも無いカラックス監督最高傑作である。


ホーリー・モーターズ
HOLY MOTORS
(2012年 フランス/ドイツ 115分  ビスタ)
ビスタ)
 2013年12月14日から12月20日まで上映
2013年12月14日から12月20日まで上映
■監督・脚本 レオス・カラックス
■製作 マリティーヌ・マリニャック/モーリス・タンシャン/アルベール・プレヴォ
■撮影 キャロリーヌ・シャンプティエ/イヴ・カープ
■編集 ネリー・ケティエ
■メイク・ヘアデザイン ベルナール・フロック
■美術 フロリアン・サンソン
■衣裳 アナイス・ロマン
■出演 ドニ・ラヴァン/エディット・スコブ/エヴァ・メンデス/カイリー・ミノーグ/エリーズ・ロモー/ミシェル・ピッコリ/レオス・カラックス/ナースチャ・ゴルベワ・カラックス
■2012年カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品/2012年シカゴ国際映画祭ゴールド・ヒューゴ賞、シルバー・ヒューゴ賞主演男優賞、撮影賞受賞/2012年ロサンゼルス映画批評家協会賞外国語映画賞/2012年セザール賞9部門ノミネート/「カイエ・デュ・シネマ」誌2012年度ベストワン
![]()
 ひとつの人生からもうひとつの人生へ、旅を続けるオスカーの1日。ある時は富豪の銀行家、またある時は殺人者、物乞いの女、怪物、そして父親へと、次々に姿を変えてゆく。オスカーはそれぞれの役になりきり、演じることを楽しんでいるように見えるが…、どこかにカメラはあるのだろうか?
ひとつの人生からもうひとつの人生へ、旅を続けるオスカーの1日。ある時は富豪の銀行家、またある時は殺人者、物乞いの女、怪物、そして父親へと、次々に姿を変えてゆく。オスカーはそれぞれの役になりきり、演じることを楽しんでいるように見えるが…、どこかにカメラはあるのだろうか?
ブロンドの運転手セリーヌを唯一の供に、オスカーはメイク道具を満載した舞台裏のような白いリムジンで、パリの街中を移動する。まるで任務を遂行する隙のない暗殺者のように。行為の美しさを求めて。アクションの原動力を求めて。そして彼の人生に登場した女たちや亡霊たちを追い求めて。だが彼の家、家族、そして休息の場所はいったいどこにあるのだろうか?
![]()
 『ポーラX』以来実に13年ぶりとなる長編『ホーリー・モーターズ』は、カラックスならではの映像美とミステリアスな物語に長年の想い、そしてカラックス自身の人生が投影された、堂々たる傑作である。主人公オスカーを演じるのはもちろんドニ・ラヴァン。特殊メイクを駆使して11の人格に次々と扮し、本作に驚くべき高揚感を与えている。また、カイリー・ミノーグやエヴァ・メンデスなど異色でゴージャスなキャストたちが脇を彩る。
『ポーラX』以来実に13年ぶりとなる長編『ホーリー・モーターズ』は、カラックスならではの映像美とミステリアスな物語に長年の想い、そしてカラックス自身の人生が投影された、堂々たる傑作である。主人公オスカーを演じるのはもちろんドニ・ラヴァン。特殊メイクを駆使して11の人格に次々と扮し、本作に驚くべき高揚感を与えている。また、カイリー・ミノーグやエヴァ・メンデスなど異色でゴージャスなキャストたちが脇を彩る。
 夜明けから深夜までの1日をめぐるオスカーの旅。彼によって演じられる年齢も立場も違う11の人格は、喜びや欲望、苦悩そして後悔がこめられた人生のアバタ―である。白いリムジンはオスカーを乗せ、美しく、そして気高くパリ市内を走りぬける――。久しく待たれたこの新作は、カンヌ国際映画祭で衝撃と熱狂をもって迎えられ、仏誌「カイエ・デュ・シネマ」が発表する年間ベストテンで1位に輝いたほか、世界各国で軒並み絶賛された。
夜明けから深夜までの1日をめぐるオスカーの旅。彼によって演じられる年齢も立場も違う11の人格は、喜びや欲望、苦悩そして後悔がこめられた人生のアバタ―である。白いリムジンはオスカーを乗せ、美しく、そして気高くパリ市内を走りぬける――。久しく待たれたこの新作は、カンヌ国際映画祭で衝撃と熱狂をもって迎えられ、仏誌「カイエ・デュ・シネマ」が発表する年間ベストテンで1位に輝いたほか、世界各国で軒並み絶賛された。
