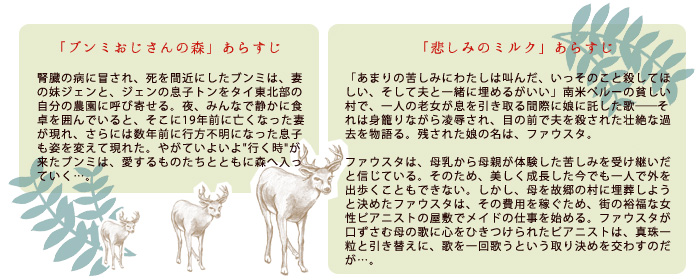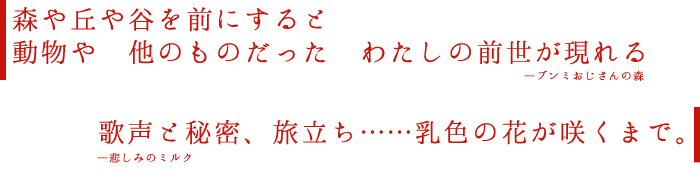

 ブンミおじさんは、この森で何度も生まれてきた。彼は転生する度に姿を変えた。ある時には水牛、またある時には象を狩る人、精霊というように。しかしその度に生まれるのはこの森だったという。
ブンミおじさんは、この森で何度も生まれてきた。彼は転生する度に姿を変えた。ある時には水牛、またある時には象を狩る人、精霊というように。しかしその度に生まれるのはこの森だったという。
僧侶が書いた『前世を思い出せる男』という小冊子に着想を得て作られたという『ブンミおじさんの森』は、タイ東北部のある村と、その村を取り囲む密林地帯の、生と死を巡る大きなサイクルを描いた作品。前作『トロピカル・マラディ』(2004)でも、中島敦の『山月記』を作品中に取り入れるなど、アピチャッポン・ウィーラセタクンの映画の物語は伝承や民話など、古い物語のエッセンスが散りばめられているのにも関わらず、新鮮な驚きに満ちている。
日本の昔話『竹取物語』が中国や東南アジアなどの別の場所で、似たような内容や構成の物語として発見されるように、自然と人の間で紡がれた物語は世界各地で多数存在する。かつて自然が人間の存在以前のすべての時間を有し、“恐怖の対象”であったことはそのことと無関係ではないだろう。
都会で暮らしているとわからなくなってしまうが、山や森の夜の闇は本当に恐ろしい。人は多くのものを自然に見い出してきた。時に密林の生い茂った木々に光を遮られた薄闇、霞の中に夢と幻を創出し、大地の奥深く根を張った植物の、土を捕えて育つ力、広大に拡がる地下茎の持つ構想力に憧れて、昔の人たちにとっては、私たちが今感じる以上に大きく神経を刺激されながら、その得体の知れないものたちの存在を感じてきたのだ。
 『悲しみのミルク』もまた、アンデスの伝承や習慣とともに、自然と文明の未分化な環境から得た想像力にインスピレーションを得たペルーの映画だ。しかし、彼女たちの“恐怖の対象”は自然ではなく人間。1990年代後半まで、ペルーの近現代は恐怖の時代だった。
『悲しみのミルク』もまた、アンデスの伝承や習慣とともに、自然と文明の未分化な環境から得た想像力にインスピレーションを得たペルーの映画だ。しかし、彼女たちの“恐怖の対象”は自然ではなく人間。1990年代後半まで、ペルーの近現代は恐怖の時代だった。
 ゲリラ側と治安部隊の双方の間で攻撃の対象となった農村の被害者の多くは先住民であり、主人公のファウスタとその母親の故郷(だと思われる)、アヤクーチョ(「死者の一隅」という意味の)という街も、ゲリラ側の基盤になった。ファウスタは、その恐ろしさを母乳から伝えられたという。“ススト”と呼ばれる病[恐乳病]は、一般的には夜驚症を指すもので、子供がお腹にいるときに、母親が大きなショックを受けたり、ひどく驚いた後に授乳することで発症するといわれている民間伝承だ。
ゲリラ側と治安部隊の双方の間で攻撃の対象となった農村の被害者の多くは先住民であり、主人公のファウスタとその母親の故郷(だと思われる)、アヤクーチョ(「死者の一隅」という意味の)という街も、ゲリラ側の基盤になった。ファウスタは、その恐ろしさを母乳から伝えられたという。“ススト”と呼ばれる病[恐乳病]は、一般的には夜驚症を指すもので、子供がお腹にいるときに、母親が大きなショックを受けたり、ひどく驚いた後に授乳することで発症するといわれている民間伝承だ。
残酷な歴史は彼女を引きこもらせて、臆病にさせる。外を一人では歩けない彼女の、壁の隅から先の様子を伺う瞳の中の黒々した怯え。己の身を護るために身体に潜ませたジャガイモは、歴史を背負わされた彼女の閉じた孤独をますます増幅させていく。
恐怖。しかし西洋文明の多くが自然の持つ光の力に魅了され、何も見ることのできない闇の恐怖を追い払うことで発展してきたことに比べると、彼女たちの未分化な文明の多くは、闇を自分の中に引き入れて共に暮らしてきたのだった。
『ブンミおじさんの森』の密林の中で動物たちが少し動くだけで、伝わってくる躍動感。水牛の震えている筋肉、それを覆う皮膚の黒々とした鈍い光の照り返し。密林の葉と葉の重なり合いの隙間から、太陽を透かしてみたときに感じるのは、その温かさよりもむしろ、自分の足の下にある堆積した落ち葉や土の圧倒的なボリュームを伝えてくる、その冷たさ。それはかつての“恐怖の対象”のようにではなく、むしろ親愛なる友のように信頼感のあるものだ。
 かつての多くの命が森で失われて、その上に木々や生き物たちが栄える。歴史の悲劇が堆積して、臆病に生まれたファウスタもまた、ブンミおじさんと同じような大きな循環を生きている。自然や時間の残酷なまでの平等さの前で、動物たちと並置された人間の存在(なんて不確かなもの)はいつしかフワフワと漂流し始める。そんな抜け殻のような人間の姿を見たときに、私たちはなんとも言えない清々しい気持ちになってしまう。私たち動物と人間の境界を曖昧にして、未分化な世界へと再統合されていく喜び。まだ夢と現実の境のなかった、恐怖と驚きが入り混じったプリミティブな生の興奮。
かつての多くの命が森で失われて、その上に木々や生き物たちが栄える。歴史の悲劇が堆積して、臆病に生まれたファウスタもまた、ブンミおじさんと同じような大きな循環を生きている。自然や時間の残酷なまでの平等さの前で、動物たちと並置された人間の存在(なんて不確かなもの)はいつしかフワフワと漂流し始める。そんな抜け殻のような人間の姿を見たときに、私たちはなんとも言えない清々しい気持ちになってしまう。私たち動物と人間の境界を曖昧にして、未分化な世界へと再統合されていく喜び。まだ夢と現実の境のなかった、恐怖と驚きが入り混じったプリミティブな生の興奮。
アピチャッポン・ウィーラセタクンは言う。「考えないで、流れにまかせて」。
闇がいくら深くなって自分たちの前に立ちはだかろうとも、「闇に慣れればまた見える」のだから。
(ぽっけ)