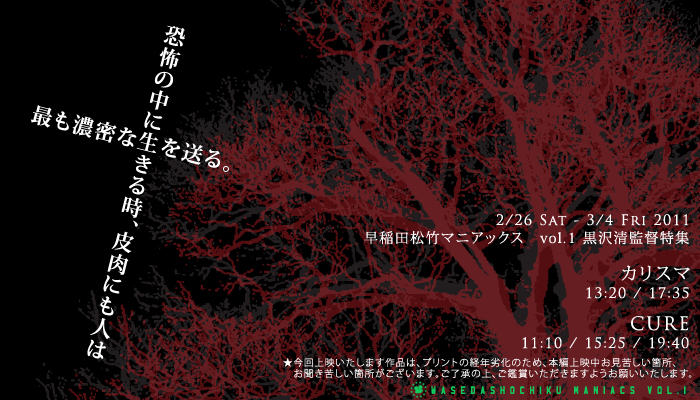
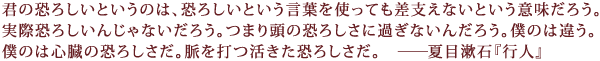
自分が自分である気がしない。現実ではなく夢の中にいるようで、どんなに努力してどこまでいっても何も見えてこない。
様々な関係のなかで、がらんとした淋しい光景のなかで、孤独と自己欺瞞に苛まれながら、正体のわからないものを相手に
徒手空拳で“自分”たらんとする。黒沢清の映画の中の人物たちはそんな顔をしている。
いや、もしかしたらむしろこういうべきかもしれない。そんな顔をしているのは黒沢清映画を観ている私たちだ。
黒沢清監督の作品世界を形づくる数々の要素は私たちを不安にさせる。
『CURE』の何度止めても回り出す空っぽの洗濯機に、ただ置かれた椅子の上で狂う“不在”に私たちは戦慄し、
『カリスマ』のだだっ広い廃墟・空間、荒涼とした平原、そこに立つ一本立ちの樹木と森全体の非情で残酷なまでの平等さに、
わたしたちは未だ恐怖を拭いきれないでいるのだ。
もしそこに我々自身の自意識の過剰(なんて出鱈目なもの)を読み取れば、それこそが病のような気さえしてくる。
どこまでも不穏で、どこまでも広がっていくこの伝染病のような狂気(なんていい加減なもの)の正体を誰も知らない。
皮肉にも人々にとって、この得体の知れなさこそが何よりも近くにいるというのに。
長く続いてきた不況のせいか、東京のあちこちでテナント募集の看板を見かける。
空きビルに、空き家に、いなくなった人たちがいる。
その途端に襲いかかる、人が生存するという理由もない孤独。
黒沢清映画のこの星空を覗くような寂しさは、現在を通過した。
「そろそろバカバカしくなってきたんじゃないんですか?」(『カリスマ』神保千鶴の台詞より)
その通り。しかし、冒頭に引用した夏目漱石の小説の一節は百年も前に書かれたもの。
そろそろどころではなく、もう随分前からバカバカしくなるほど出鱈目な世界を私たちは生きているのだ。
今回上映する『CURE』『カリスマ』は黒沢清監督作品の代表作とも言われる重要な映画です。
作品ごとに人々を驚かせる現代日本の誇る映画監督。黒沢清監督特集。
「早稲田松竹マニアックスvol.1」としてお届けします。
カリスマ
(1999年 日本 104分 ビスタ/SRD)
 2011年2月26日から3月4日まで上映
2011年2月26日から3月4日まで上映
■監督・脚本 黒沢清
■撮影 林淳一郎
■音楽 ゲイリー芦屋
■出演 役所広司/池内博之/大杉漣/洞口依子
■1999年日本映画プロフェッショナル大賞作品賞・ベスト10(第1位)
★プリントの経年劣化により、本編上映中お見苦しい箇所・お聞き苦しい箇所がございます。ご了承の上、ご鑑賞いただきますようお願いいたします。
![]()
人質をとった立てこもり犯から藪池(役所広司)が受け取ったメモにはそう書かれていた。カリスマは一本立ちの樹木だ。独立不羈に見えるこの枯れかけた樹木は、森全体を殺すことで自らを生きながらえさせる怪物のような木。さらに森全体、むしろ若い木から順番に喜んで命を捧げるように倒れていくという魅力的な木だと言われる。カリスマを取り巻く人々もまた、たった一本の木に狂わされていく。
 弱肉強食の自然の摂理こそが「世界の法則」であると言いカリスマを守る桐山(池内博之)。一方、森の保全を目的にその木を切ろうとして憚らない植物学者である神保姉妹(風吹ジュン:洞口依子)や、中曽根(大杉漣)ひきいる植林作業員。
弱肉強食の自然の摂理こそが「世界の法則」であると言いカリスマを守る桐山(池内博之)。一方、森の保全を目的にその木を切ろうとして憚らない植物学者である神保姉妹(風吹ジュン:洞口依子)や、中曽根(大杉漣)ひきいる植林作業員。
回復すべき「世界の法則」とは一体なんだろう。弱肉強食:自然の摂理=世界の法則だろうか、それとも秩序を満たすべく、怪物的で暴力的なものを取り去り、平和な世界を回復するべきだということだろうか。
 人間にこの問いが課せられるとき、すでに意識と自然の如何ともしがたい対立が始まる。自然の一部から乖離し、違和としてしか存在しえない苛酷な人間の姿が浮き彫りになってゆく。
人間にこの問いが課せられるとき、すでに意識と自然の如何ともしがたい対立が始まる。自然の一部から乖離し、違和としてしか存在しえない苛酷な人間の姿が浮き彫りになってゆく。
「自由というのは反面、責任を伴う非常に厳しいものです。それを真にわかってはじめて、自然の中で、社会の中で、人は生きていけるのだと思います」――黒沢清


CURE
(1997年 日本 111分 ビスタ/SR)
 2011年2月26日から3月4日まで上映
2011年2月26日から3月4日まで上映
■監督・脚本 黒沢清
■撮影 喜久村徳章
■音楽 ゲイリー芦屋
■出演 役所広司/萩原聖人/うじきつよし/中川安奈
■1997年日本映画プロフェッショナル大賞作品賞・助演男優賞・ベスト10(第1位)
★プリントの経年劣化により、本編上映中お見苦しい箇所・お聞き苦しい箇所がございます。ご了承の上、ご鑑賞いただきますようお願いいたします。
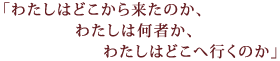
 わたしたちはこの問いに答えることができない。記憶喪失の不思議な青年・間宮(萩原聖人)は催眠術をかけるとき、執拗なまでに相手に質問を投げかける。「あんた、誰だ?」何か答える度に「なぜなんだ? どうして?」と相手を追い詰める。そのうちに、相手は本当の自分である根拠を失いだす。「オレはあんたの話が聞きたい」
わたしたちはこの問いに答えることができない。記憶喪失の不思議な青年・間宮(萩原聖人)は催眠術をかけるとき、執拗なまでに相手に質問を投げかける。「あんた、誰だ?」何か答える度に「なぜなんだ? どうして?」と相手を追い詰める。そのうちに、相手は本当の自分である根拠を失いだす。「オレはあんたの話が聞きたい」
冒頭で『青髭』の朗読をする高部(役所広司)の妻(中川安奈)は分裂病を患っている。彼女は病院に行く道すら忘れてしまう。行き先を見失い彷徨う彼女が迷いながら向かう場所を、私たちはきっと一度は同じように彷徨ったことがあるはずだ。
 人間と人間が関係づけられて存在するときに起こる、われわれにどうすることもできない違和や虚偽。それはきっと現代を生き抜く人々の生存条件として欠かすことのできないものだ。ついにはこの悩みを悩み抜く、その誠実さゆえに常に裏切られる者に訪れるのが「死ぬか、気が違うか、宗教に入るか」しかないとしたら、何度も何度も目的を再生し続ける高部の行為は「癒し」(cure)と呼びうるものなのだろうか。もしそうでないとしても、このある種の爽やかさを 観客は決して忘れることができないだろう。
人間と人間が関係づけられて存在するときに起こる、われわれにどうすることもできない違和や虚偽。それはきっと現代を生き抜く人々の生存条件として欠かすことのできないものだ。ついにはこの悩みを悩み抜く、その誠実さゆえに常に裏切られる者に訪れるのが「死ぬか、気が違うか、宗教に入るか」しかないとしたら、何度も何度も目的を再生し続ける高部の行為は「癒し」(cure)と呼びうるものなのだろうか。もしそうでないとしても、このある種の爽やかさを 観客は決して忘れることができないだろう。
「画面のいたるところに恐怖(=死)が貼りつき、同時に、その中にくっきりと人間(=生)の輪郭が浮かび上がること、そんな出鱈目な表現は映画にしかできぬ芸当かもしれない」――黒沢清
(ぽっけ)
