
このたびはビクトル・エリセ監督の作品 『ミツバチのささやき』と『エル・スール』を上映します。 エリセ監督はたいへん寡作な映画作家で、 長編作品は3作品しかありません。 10年に1本の監督なんて言われたりもします。 でもその一つ一つが映画史に残る傑作で、 名工が手を込み熟すように重厚な作品です。
ピカソが『ゲルニカ』で描いたスペイン内戦(1936〜39)。 その歴史の傷あとはエリセ監督の映画にも刻まれています。 左派の人民戦線政府と、フランコ将軍率いる右派の反乱軍との内戦。 結果反乱軍が勝利してフランコ独裁制(1940〜75)が続き、 共和国派は民族独立派によって迫害されました。
敗れ去った大人たちの心の傷。 彼らを見つめる少女の“まなざし”。 底深く、微細に震え、詩が浮かんで来るよう。 それは単に子供がピュアだからではなく、 少女たちが始めて知る世界を描いているからだと思います。 世界に存在する“悲しみ”を受け止める瞬間。
「ぼくが思うに、映画が我々に対して果たしてきた役割の一つは“啓示”です」とエリセ監督は語っています。
今回上映する両作品とも、“映画”が少女たちに 自分の外の世界を知るきっかけを与えます。 公民館のスクリーンに映る、怪物フランケンシュタイン。 「なぜ、殺したの?」 一心不乱に見つめる少女アナの“まなざし”は、 生々しい現実を見つめているように切迫したものです。 そして映画の生にもぎとられた彼女は、映画の中で出会った フランケンシュタインに心魅かれることになります。
エリセ監督が描くのは、 小さく、孤独で、静謐な世界です。 私自身も欠落した自分や世界に気がついた時、 大人になった実感を得ました。 切なく澄みきったその時の感情が、 映画からまざまざと伝わって胸を打ちます。
『ミツバチのささやき』と『エル・スール』の間“10年の空白”。 続けて観ると彼の中で、時によって失われたものが深く見えてきます。 少女の視線と父親の視線。 エリセ監督は両方に同化し、そこから自分を見つめ返す 内省的な姿勢をとり続けます。 自分に誠実であること。 映画に誠実であること。 今回はそんなひたむきな映画たちのささやきに、 耳を傾けてみましょう。
監督:ビクトル・エリセ
1940年、スペイン・バスク生まれ。スペイン内乱の余塵さめやらぬ、内戦直後の世代である。『エル・スール』のエストレリャは1957年に15歳という設定であるから、同じ世代ということになる。南に魅了される北の少女(少年)というモチーフはエリセの人生と重なりあっているのだろう。
映画学校でいくつかの習作を手がけた後、映画監督としての資格を取得したが、しばらくは映画雑誌に批評やエッセイを書きながら過ごす。
68年にオムニバス映画『挑戦(LOS DESAFIOS)』の一篇で劇監督デビュー。73年の『ミツバチのささやき』が長編映画の第一作目。約10年に1本しか撮らない、非常に寡作な監督として知られるが、そのいずれの作品も高い評価を得ている。

・挑戦(1969)*未公開
・ミツバチのささやき(1973)
・エル・スール(1982)
・マルメロの陽光(1992)
・10ミニッツ・オールダー 人生のメビウス(2002)
エル・スール
EL SUR
(1983年 スペイン・フランス 95分 ビスタ・MONO)
 2009年11月7日から11月13日まで上映
■監督・脚本 ビクトル・エリセ
2009年11月7日から11月13日まで上映
■監督・脚本 ビクトル・エリセ
■原作 アデライダ・ガルシア=モラレス
■出演 オメロ・アントヌッティ/ソンソレス・アラングーレン/イシアル・ボリャン/ロラ・カルドナ/ラファエラ・アパリシオ/ジェルメーヌ・モンテロ/オーロール・クレマン/フランシスコ・メリノ
■1983年シカゴ国際映画祭グランプリ(ゴールド・ヒューゴー賞)
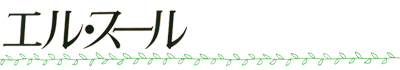
『エル・スール』は娘エストレリャから見た、 父アグスティンとの関係を軸に描かれている。 映画の中で語られることのない、父の過去。 娘はそんな父の真実を追い求める。
エストレリャが父はもう帰って来ないと予感したのは 15歳の時、1957年の秋の朝だった。 枕の下の小さな丸い箱に、父が愛用していた 霊力で動くふりこが残されていた。
旅を重ね、父が北の川沿いの町で病院の医師の仕事を得て、 一家が郊外で暮らし始めたのはエストレリャが7歳か8歳の頃。 その一軒家は<かもめの家>と呼ばれ、 屋根の風見のかもめはいつも“南=エル・スール”をさしていた。
家の前の道を国道と呼び、そこでバイクに乗せてくれる父。 ふりこで水脈を発見し、その使い方を教えてくれる父。 エストレリャはそんな父と一緒にいられることが嬉しくて、 父の過去を謎に思うことすらなかった。
冬の雪の日。南では雪は降らないとの母の一言から、 父と南の謎が幼いエストレリャの心に芽生える。 確かにあなたの父は南の出身だけれど、 祖父と大喧嘩して二度と戻らぬ決心で南を出たと母は言う。 そして、エストレリャの、想像のエル・スールへの旅が始まる…。
この映画の中で、父アグスティンの過去は説明されない。 それが見えないところで物語は進展する。 この映画の想像性は観客に委ねられている。 私たちはエストレリャを通して、 彼女と一緒に父の過去を追わなくてはならない。 そして歴史の縦軸と父娘の横軸が交差し、 寡黙の内に父に秘められた愛と革命の灯を感じることになる。 それは大いなる喪失感と悲しみを伴って。
『エル・スール』はエリセ監督の実人生と結びつけることができる。 彼自身も両親が南出身なのに、北で育った。 しかもエリセ監督とエストレリャは、 スペイン内乱直後生まれの同世代である。 彼が少年時代に見た大人たちに通じるもの。 敗北を知ってしまった人間の孤独や懊悩が、 アグスティンの佇まいには宿っている。
そして何よりも完璧な“父親”に成れない苦しみ。 父親を見失った“娘”の孤独。 すれ違い悲しみを背負った人間たちに通底する感情を、 エリセ監督は自らの人生(親であり、子である自分)に重ねて描いた。 これは全身全霊の行為だ。
父を見つめる、エストレリャの微細に震える“まなざし”。 そのフィルムに刻まれた一瞬の奇跡に出会うために、 私たちは映画を見続ける。

ミツバチのささやき
EL ESPIRITU DE LA COLMENA
(1973年 スペイン 99分 ビスタ・MONO)
 2009年11月7日から11月13日まで上映
■監督・原案・脚色・脚本 ビクトル・エリセ
2009年11月7日から11月13日まで上映
■監督・原案・脚色・脚本 ビクトル・エリセ
■脚色・脚本 アンヘル・フェルナンデス=サントス
■出演 アナ・トレント/イサベル・テリェリア/フェルナンド・フェルナン・ゴメス/テレサ・ギンペラ/ケティ・デ・ラ・カマラ/ラリ・ソルデビリャ/ミゲル・ピカソ/ホアン・マルガリョ/エスタニス・ゴンザレス/ホセ・ビリャサンテ/マヌエル・デ・アグスティナ/ミゲル・アグアド
■1973年度サン・セバスチャン国際映画祭グランプリ(黄金の貝殻賞)/1973年度シカゴ国際映画祭シルヴァー・ヒューゴー賞
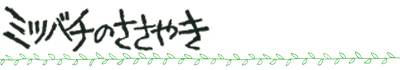
『ミツバチのささやき』といえば、やっぱり少女アナ。 エリセ監督は学校の砂場の隅で一人遊ぶアナを見て、 主役に抜擢したという。 万人を魅了する彼女のつぶらな瞳。 観る前からこの映画には何かあると思わせる予感があった。
1940年頃、スペイン中部のカスティーリャの小さな村に、 移動巡回映画のトラックが入っていく。 公民館のスクリーンに映し出されるのは、 怪物映画の大傑作『フランケンシュタイン』。 アナと姉イサベルは、村人と一緒に息をつめて映画に見入っている。 スクリーンのなかの少女メアリーが殺されて、アナは姉に聞く。 なぜ殺したの? なぜ殺されたの? 姉は後で教えてあげると言って答えようとしない。
映写機の音にも似たミツバチのささやきの中で、 父フェルナンドが養蜂の仕事をしている。 母テレサは部屋にこもって手紙を書いている。 外国にいる兄弟か、内戦でのかつての同志に宛ててか、 母は毎週のように手紙を駅の列車便に投函し続けている。
夜、イサベルはアナに、フランケンシュタインは 怪物ではなく精霊で、死んだのではなく、 村外れの井戸のある家に生きていて、 “ソイ・アナ(私はアナよ)”と声をかければ 出てきて友達になってくれると教える。 アナはその話を信じた…。
この映画の原題は『ミツバチの巣箱の精霊』。 画面に映し出されるのは、小さな生命の集積。 まさに“精霊”たちが集う映画。 アナにとっていちばんの精霊は“フランケンシュタイン”。 毒キノコを踏みつぶしてしまう父は、 アナの世界では悪い精霊。 映画に魅せられたアナは、姉の作り話を信じ込み、 精霊に導かれてしまう。
少女は周りのすべてに“生命”を吹き込む。 そして物語を創る。 傷ついた兵士はフランケンシュタインという名の精霊。 アナはその大切な精霊に、リンゴをあげる。 その時リンゴは、少女の“生命のカケラ”になる。
「お友達になれば、いつでもお話ができる… 目を閉じて、呼びかけるの… ソイ、アナ…私はアナよ」
映画の中で大人たちは過去と悲しみの現実を背負い、 精霊たちは想像の世界を生み出す。 小さな精霊たちがたてる羽音に耳を澄ましてみる。 “想像”こそが“現実”に息吹をもたらし、 大きな夢として開花する。
『ミツバチのささやき』を観て、私は子供の時 大切にしていた宝物に再会したように胸が熱くなった。 小さく、静かに、ささやくように。 観て本当によかったと心から思える映画です。
(mako)
