
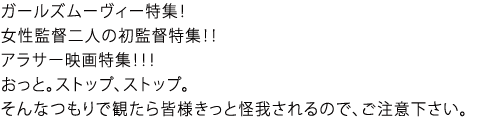
そんなわけで、慎んで二人の女性監督を紹介いたします。
1人は言わずと知れたポップクイーン―マドンナ―ちなみに元旦那はガイ・リッチー、ショーン・ペン。
もう1人は、映画監督ジョン・カサヴェテスと女優ジーナ・ローランズの娘―ゾエ・カサヴェテス―
さてと、突然ですが彼女たちの周囲の人ってどんな人たちだと思いますか?
ちょっと想像してみて下さい。
周りは一流のアーティストとか、アーティストの卵だらけ?
例えば…こんな感じでしょうか?
仲間と一緒に音楽を聴き、踊り、
色鮮やかな洋服を着て映画を観る。
本を読む。写真を撮る。彼氏がミュージシャンだ。
かと思えば、友達が映画を撮っている。
知り合いが俳優だ。デザイナーだ。絵描きだ。
スタイリスト、コーディネーター、アスリート、建築家、小説家etc…
あるいは、それを目指している。
きっと周囲には、夢や計画が満ち満ちているはず。
いつかきっと。という感情。
生活だって、夢だって、恋愛だって、
なんでもかんでも充実させたいっ。
充実しなきゃ、人生じゃない!!
アタシだって。オレだって。
なんか私たちの周りにいる人たちとあまり変わりない気がしませんか?
若い人たちは今、夢を追いかけて仕事にしようとしている人が多いはず。
その分仕事を苦痛に感じたり、挫折する機会が多いと聞きます。
その中心とも言える環境で暮らしているであろう監督たちが、
それぞれいくつかの夢と生活を描きます。
夢を追う。希望を探す。幸せになる。
しかし触れたら切れる。希望とはそういうものではなかったでしょうか?
その得難さを何故彼女たち=女性監督が描くのか。
そこには彼女たちのどんな「痛み」が伴っているのか。
さぁ、皆様。
この映画たちの中で目指されるのは
純度の高い「Happy Life」
―夢と現実。男と女。希望と後悔。―
背筋を伸ばせ。目を見張れ。
気軽に触れたら火傷するわよ

ワンダーラスト
FILTH AND WISDOM
(2008年 イギリス 84分 ビスタ・SRD) 
 2009年5月16日から5月22日まで上映
2009年5月16日から5月22日まで上映
■監督・脚本・製作総指揮 マドンナ
■脚本 ダン・ケイダン
■出演 ユージン・ハッツ/ホリー・ウェストン/ヴィッキー・マクルア/リチャード・E・グラント/インダー・マノチャ/エリオット・レヴィ
AKはミュージシャンとしての成功を、ホリーはバレエの舞台で踊る日を、ジュリエットはアフリカの子供たちを救うことを夢見ながら、理想からは程遠い現実を生きている。でも、希望の光は、暗闇の中でこそ見出せるはず!ロンドンの片隅で、恋をする。現実を知る。でも、夢を見続ける。そんな若者たちの物語。マドンナ初監督作品。
Look at me!
ゆやーんゆよーんの泣き笑い。
「これが、マドンナの堕落論」とはキャッチーな触れ込みだ。堕落論とは坂口安吾の代表的な著作。「生きよ堕ちよ、その正当な手順の外に、真に人間を救い得る便利な近道が有りうるだろうか。」という安吾は、「それでも人間は堕ちきることはできない」という。しかし、それでは宙づりではないか?
 歌手を目指すAK(ユージン・ハッツ)、バレエ・ダンサーを目指すホリー(ホリー・ウェストン)、アフリカ救済を目指すジュリエット(ヴィッキー・マクルア)。この主人公たちのそれぞれがSM調教師、ストリップ・ダンサー、万引き常習犯という現実。この二面性を抱える主人公たちの姿は現実と理想のように表裏。どちらが仮面なのかさえ、わからない。
歌手を目指すAK(ユージン・ハッツ)、バレエ・ダンサーを目指すホリー(ホリー・ウェストン)、アフリカ救済を目指すジュリエット(ヴィッキー・マクルア)。この主人公たちのそれぞれがSM調教師、ストリップ・ダンサー、万引き常習犯という現実。この二面性を抱える主人公たちの姿は現実と理想のように表裏。どちらが仮面なのかさえ、わからない。
しかし、やっていることが表裏なのだとしても、彼女たちはまっすぐではないだろうか。うまく踊りたいから踊る。客が喜ぶ。救済に行くにはお金が必要だから、盗む。お金は貯まる。歌手や詩人が声を震わせれば、顧客の歪んだ欲望と屈折した心にもたらすものは、変態的な調教にも似ているかもしれない。
 そんなのダンスじゃない。そんなの救済じゃない。それは、芸術じゃない。という人たちにマドンナはNOと言っているようにも思う。ホリーが行うポールダンス(ポールに絡みつくような踊り)は、相当な実力を必要とする。ジュリエット以外の誰ならば、アフリカ救済のために「銀行強盗をしてでも」と言えるのか?AKは苦心している。顧客を喜ばせるプレイの手伝いをルームメイトにしてもらうほどだ。
そんなのダンスじゃない。そんなの救済じゃない。それは、芸術じゃない。という人たちにマドンナはNOと言っているようにも思う。ホリーが行うポールダンス(ポールに絡みつくような踊り)は、相当な実力を必要とする。ジュリエット以外の誰ならば、アフリカ救済のために「銀行強盗をしてでも」と言えるのか?AKは苦心している。顧客を喜ばせるプレイの手伝いをルームメイトにしてもらうほどだ。
彼らは社会から堕ちていけばいくほど、周囲の人間関係や自分の未来に絶望し、傷つき、悩めば悩むほど彼らは強くはっきりとしたパフォーマンスを手に入れていく。生きる=即表現。彼らを地面に激突させまいとする一本のロープは、彼らが創り出したのだ。
 ロンドンの片隅。地面すれすれから、強大なエネルギーを発して顔を上げる若者たちがいる。彼女らは皆マドンナのような顔をしていないか?マドンナはスターの仮面でさえも利用して、何かを伝えようとし続けてきた。そのマドンナのエネルギーと魅力の原点を見るようなしぶとい一作。各界著名人の猛烈な支持を受けるAK役ユージン・ハッツの魅力がそれを実現した。
ロンドンの片隅。地面すれすれから、強大なエネルギーを発して顔を上げる若者たちがいる。彼女らは皆マドンナのような顔をしていないか?マドンナはスターの仮面でさえも利用して、何かを伝えようとし続けてきた。そのマドンナのエネルギーと魅力の原点を見るようなしぶとい一作。各界著名人の猛烈な支持を受けるAK役ユージン・ハッツの魅力がそれを実現した。
タフになりたければ、喰らってみて下さい。


ブロークン・イングリッシュ
BROKEN ENGLISH
(2007年 アメリカ・日本・フランス 98分 ビスタ・SRD)
 2009年5月16日から5月22日まで上映
2009年5月16日から5月22日まで上映
■監督・脚本 ゾエ・カサヴェテス
■出演 パーカー・ポージー/メルヴィル・プポー/ジーナ・ローランズ/ドレア・ド・マッテオ/ジャスティン・セロー/ピーター・ボグダノヴィッチ
恋に落ちるのがこわかった。もう魔法なんて起きないと思ってた。ノラ・ワイルダー、30代、独身。仕事中心の日々。男性とつきあおうとすれば失敗する。「そのままの自分」を愛してくれる人に出会いたい、でももう誰からも愛されないかもしれない。ソフィア・コッポラに続くサラブレッド、ゾエ・カサヴェテス初監督作品。
夢を実現する魔法は、いつでも近くに。
愛は流れのようなものよ。決して絶えることはない。
―映画「ラヴ・ストリームス」より
主人公であるノラ・ワイルダー(パーカー・ポージー)は美しい女性である。周りの友人からも出会った人からも嫌われてはない。むしろ好かれている。仕事もホテルのVIP担当。重要な仕事で、恋愛もしていないわけではない。まるで「アリーMylove」や「Sex and the city」のような世界。働く自立した女性。しかし何度も恋愛の失敗を重ねるうちにノラは臆病になっていく。自分は不器用だ、と。
 一体何がいけないのだろうか?周りの人から見ても自分でも、わからない。愛される資格がないのか、幸せになる資格がないのか。もっと不幸な人に比べたら大して深刻な状態でもないはずなのに…
一体何がいけないのだろうか?周りの人から見ても自分でも、わからない。愛される資格がないのか、幸せになる資格がないのか。もっと不幸な人に比べたら大して深刻な状態でもないはずなのに…
「何か大きな間違いを犯しているのかもしれないのに、それがなんだかわからない」
彼女は本当に大きな間違いを犯しているのだろうか?ノラはとても痛ましい様子だ。しかしそんな様子になるほど傷つけられた瞬間は見えない。では一体この映画の底を流れる”痛み”の正体はなんだろうか?
ゾエ・カサヴェテスのスケッチはとても正確で緻密。主人公ノラの姿態をユーモラスかつ大胆に描いていく。特筆すべきは、会話やシチュエーションの細部に張り巡らされている扉のようなものだ。それは時に、友人や母親や知りあった人の言葉でノックされる扉。ノックされる度にノラは心が震える。彼女はその扉を自ら開くことを恐れ、躊躇っているのだ。
 その躊躇う姿は映画館の安全な暗闇にいるはずの私たちの大きな不安感さえ誘発する。扉を開けたら飛び出すしかないことを皆知っているのだと思う。その困難さを。飛び出した先はきっと今得ているものを失くし、得ていないものを得られる未知の世界―ブロークン・イングリッシュ―だから。
その躊躇う姿は映画館の安全な暗闇にいるはずの私たちの大きな不安感さえ誘発する。扉を開けたら飛び出すしかないことを皆知っているのだと思う。その困難さを。飛び出した先はきっと今得ているものを失くし、得ていないものを得られる未知の世界―ブロークン・イングリッシュ―だから。
これは映画の、そしてゾエ・カサヴェテスのラディカルな挑戦である。彼女が撮り起こしたのは、淀みない流れに流されていってしまう不安感や、声出せずにすれ違ってしまう人の手を掴むことの難しさ。そして、多くの人は自分の周囲に溢れている「魔法」に気付かずに、魔力だけを欲しがっているだけだということ。
しかし、いとも簡単に起こるからこそ奇跡なのだ。
(ぽっけ)

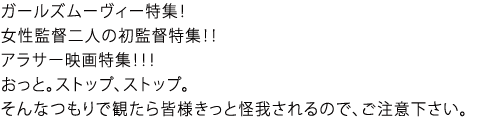



 歌手を目指すAK(ユージン・ハッツ)、バレエ・ダンサーを目指すホリー(ホリー・ウェストン)、アフリカ救済を目指すジュリエット(ヴィッキー・マクルア)。この主人公たちのそれぞれがSM調教師、ストリップ・ダンサー、万引き常習犯という現実。この二面性を抱える主人公たちの姿は現実と理想のように表裏。どちらが仮面なのかさえ、わからない。
歌手を目指すAK(ユージン・ハッツ)、バレエ・ダンサーを目指すホリー(ホリー・ウェストン)、アフリカ救済を目指すジュリエット(ヴィッキー・マクルア)。この主人公たちのそれぞれがSM調教師、ストリップ・ダンサー、万引き常習犯という現実。この二面性を抱える主人公たちの姿は現実と理想のように表裏。どちらが仮面なのかさえ、わからない。 そんなのダンスじゃない。そんなの救済じゃない。それは、芸術じゃない。という人たちにマドンナはNOと言っているようにも思う。ホリーが行うポールダンス(ポールに絡みつくような踊り)は、相当な実力を必要とする。ジュリエット以外の誰ならば、アフリカ救済のために「銀行強盗をしてでも」と言えるのか?AKは苦心している。顧客を喜ばせるプレイの手伝いをルームメイトにしてもらうほどだ。
そんなのダンスじゃない。そんなの救済じゃない。それは、芸術じゃない。という人たちにマドンナはNOと言っているようにも思う。ホリーが行うポールダンス(ポールに絡みつくような踊り)は、相当な実力を必要とする。ジュリエット以外の誰ならば、アフリカ救済のために「銀行強盗をしてでも」と言えるのか?AKは苦心している。顧客を喜ばせるプレイの手伝いをルームメイトにしてもらうほどだ。 ロンドンの片隅。地面すれすれから、強大なエネルギーを発して顔を上げる若者たちがいる。彼女らは皆マドンナのような顔をしていないか?マドンナはスターの仮面でさえも利用して、何かを伝えようとし続けてきた。そのマドンナのエネルギーと魅力の原点を見るようなしぶとい一作。各界著名人の猛烈な支持を受けるAK役ユージン・ハッツの魅力がそれを実現した。
ロンドンの片隅。地面すれすれから、強大なエネルギーを発して顔を上げる若者たちがいる。彼女らは皆マドンナのような顔をしていないか?マドンナはスターの仮面でさえも利用して、何かを伝えようとし続けてきた。そのマドンナのエネルギーと魅力の原点を見るようなしぶとい一作。各界著名人の猛烈な支持を受けるAK役ユージン・ハッツの魅力がそれを実現した。

 一体何がいけないのだろうか?周りの人から見ても自分でも、わからない。愛される資格がないのか、幸せになる資格がないのか。もっと不幸な人に比べたら大して深刻な状態でもないはずなのに…
一体何がいけないのだろうか?周りの人から見ても自分でも、わからない。愛される資格がないのか、幸せになる資格がないのか。もっと不幸な人に比べたら大して深刻な状態でもないはずなのに… その躊躇う姿は映画館の安全な暗闇にいるはずの私たちの大きな不安感さえ誘発する。扉を開けたら飛び出すしかないことを皆知っているのだと思う。その困難さを。飛び出した先はきっと今得ているものを失くし、得ていないものを得られる未知の世界―ブロークン・イングリッシュ―だから。
その躊躇う姿は映画館の安全な暗闇にいるはずの私たちの大きな不安感さえ誘発する。扉を開けたら飛び出すしかないことを皆知っているのだと思う。その困難さを。飛び出した先はきっと今得ているものを失くし、得ていないものを得られる未知の世界―ブロークン・イングリッシュ―だから。